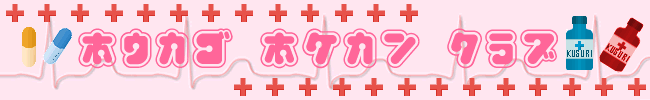
その一歩が大きいことを僕は知ってますから・・・
もう一回やったら、本当に気持ちが見える?
本当にそんなことあるのだろうか、いやそれよりも・・・・・・
「もう一回やるって?俺と先生が?!」
夢の中で3回もあんなことして、現実の世界でもあんなことされて、想像しただけで、煌成
の体は変なスイッチが入りそうになる。
やれるかやれないかだけを考えれば、出来る気がしてならない。本来、煌成はただのエロ
ガキで、セックスの相手を求めて真桜を口説いていたくらいだ。そこに恋愛感情がなく
たって、ある程度の許容範囲なら誰とでも出来る男だ。
セックスのハードルは至って低い。伊純が女だったら、学校の先生だからなんていう柵
などお構いなしにがっついていただろうと思う。
問題なのは、伊純が男で、伊純が自分に対して恋愛感情を持っていることだ。
身体から入る関係だってあるだろうと袴田は言っていたけれど、煌成はそれこそドツボ
に嵌ってしまいそうで怖いのだ。
伊純を好きになったことで背負うリスクを考えると、煌成はまだ自分の感情を直視出来
なかった。
「わかんねえよ・・・・・・」
あんなに冷たくされていたと思っていたはずなのに、踏み込んでみたら、いきなり懐に
飛び込まれてしまった。内側から弄られ、煌成の感情はグチャグチャだ。
なるようにしかならないと思いながらも、煌成は再び保健室から遠ざかり、一度目の
日曜日を煌成はスルーしてしまった。
夏に向かって加速していく季節の中を煌成は鬱々として過ごした。
真桜は上機嫌で保健室に向かっていた。その後ろを、無理矢理引き摺られるようにして
煌成が付いていく。今日は久しぶりに再開されたホケカン倶楽部があるのだ。
伊純の懲戒免職がただの噂に過ぎないことが判明して以来、噂は急速に消えてゆき、教師
の噂よりも生徒同士の噂の方が美味しいのか、話題はすっかり別のものに摩り替わっていた。
周りの噂に疎い煌成もこの時ばかりは、伊純の噂がこれ以上広がっていないか神経を
尖らせていて、噂が消えていく事に安堵した。そして、噂の去った今、残されたのは煌成
の中のグズグズしたやりきれない感情だけだった。
一つ意識すると、伊純のことが朝から晩まで頭の中を埋め尽くして、煌成は自ら首を
絞めた。
伊純に告白され、あんなことをされ、更に家にまで誘われて、完全に逃げ道を奪われた
と思う。これだけ包囲されれば、答えを出すしかないとは分かっているし、本当は答えなど
出ているような気もするのだけれど、煌成にだって常識がある。超えられない一線が深い
溝のように横たわって、煌成の思考をそこでぶった切ってしまうのだ。
今まで、男同士の恋愛なんて考えたこともなかった。知識としてそういう人種がいる事
は理解してても、自分には関係ない世界だった。
今でも、自分がそこに足を踏み入れるなんて想像できないでいる。
ただ、あの行為は伊純だから許せるのだということだけは確かだった。他の男ならば、
ぶん殴ってでも逃げ出していただろう。気持ちよかったなどという感想がくっついてくる
のは、伊純が特別だからだ。
それを認めても、煌成はまた自分の意識の袋小路に入り込んでしまうのだった。
保健室には既に藤も井沢も来ており、真桜と煌成が入ってくると、一瞬微妙な空気が
漂ったが、藤が直ぐに取り仕切った。
「なんだか、久しぶりのクラブになったけど、一応資料も集まったことだし、今日から
アンケート作成ってことで宜しく」
「はぁー、面倒くさい」
「今更何言ってんのよ。ちゃんとやりなさいよ?」
「ハイハイ」
そう言って煌成が手元の資料に目を落とすと、そこには既にアンケートのたたき台が作って
あった。
「これ、藤が作った?」
「そうだけど。気になるところある?」
「・・・・・・すげえ。さすが委員長」
根が真面目なのか責任感があるのか、几帳面にアンケートは作られていた。
「ある程度形になってた方が皆も話し易いだろうと思ってね」
「これだけ作ってあれば楽勝じゃん」
「だからって他人任せにしないでよ?」
煌成が真桜に小言を言われている隣で、井沢はアンケートを見てまたほくそ笑んでいた。
「お前また悪いこと考えてるだろ」
「別に」
「言っとくけど、アンケートの結果以外に使用するのは禁止だからね」
真桜も睨みつけて言うと、井沢は真桜を軽くあしらった。
「分かってるって。大体アンケートなんて無記名なんだから、特定なんて出来ないだろ?」
それを嗅ぎ分けて、噂を捏造するのが井沢だ。
真桜も藤も煌成も、井沢の噂に対する執念を肌身を持って知ったクチだから、素直に
井沢の言い訳に頷けなかった。
「まあ、結果の話はともかく、とりあえずアンケート作成の方で意見出し合おうよ」
藤の声で、メンバー達は無理矢理思考を切り替えることになった。
アンケート作成、そして実施とホケカン倶楽部の活動は真面目な藤の努力と伊純の指示
もあって、着々と進んでいた。
そして全ての学年でアンケートが実施され、ホケカンのメンバーの下に回収されてくると
煌成たちは再び保健室に集まった。
「なんとか全クラス分集まったな」
「藤君のおかげね」
真桜が嬉しそうに笑う。藤もそれを照れくさそうに受けた。
「みんなが真面目にやってくれたからだよ」
その景色を煌成は、ギスギスとした気持ちで見ていた。
普通の男女ならこうやって楽しめるのに・・・・・・。
自分と伊純のことを思うと、どうしても卑屈になってしまう。伊純の事が好きか嫌いか
の前に、煌成は周りの視線ばかり気になっているようだった。
自分の噂には殆ど無頓着だった。何を言われようが平気で受け流せた。けれど、自分と
伊純が少しでも噂になるような事が起きたらと考えただけで、煌成は顔が引きつりそうに
なる。それが、自分がゲイだと後ろ指をさされるのが嫌なのか、伊純と噂になるのが嫌
なのか、煌成にはよく分からなかった。ただ真桜が藤と噂が立った時、本気で怒っていた
あの気分は分かるような気がした。
4人は黙々と作業を進めていた。自分の担当分のアンケートの項目を集計して、記録して
いく。初めは誰がどんな思いで答えを選んでいるのだろうかと、逐一想像していた煌成も
次第に機械のように数字だけを拾って書き込んでいった。
暫く誰もが集中していると、井沢がニマニマ笑って一枚のアンケート用紙をみんなの前
に晒した。
「なあ、これちょっと見てよ」
「ああ?」
「・・・・・・」
3人は作業の手を止め、井沢の示したアンケート用紙に目を落とした。
「何よ?」
「よく見てみなよ」
煌成も覗き込んで、上から順に書き込まれた結果を確認していった。
井沢の集計している部分は井沢が自ら真っ先に担当をやりたいと手を上げた部分だった。
それは下世話好きな井沢らしく、高校生のフリーセックスについての部分だった。
前半の質問には気になる点など一つもなく、何が井沢をそんなに楽しませているのか
分からなかったけれど、後半の質問のところで、煌成は目を丸くして固まってしまった。
『男女との付き合い方について』の項目の中にある『性行為をしたことありますか』の質問
に、この回答者は『はい』を選んでいた。
煌成も、そこまでは特に驚くことはなかったのだが、その後のフリースペース欄に『ただ、
僕が性行為をしたことがあるのは、異性ではなく同性とです』と堂々と書かれていることに
煌成は固まった。
「・・・・・・」
「な?面白いこと書いてあるだろ」
井沢の口調が耳につく。煌成は耳鳴りを感じた。
更にその回答者の文章は続いていた。『男女の付き合い方という質問の仕方自体に、憤り
は感じないけれど、切なくはなる。世間から見たら僕は異端だと思うし、そこまで配慮しろ
とは言えないけれど、こういうとき自分だけ違うんだと実感する。でも、付き合ってる相手が
異性か同性かの違いだけで、悪いことをしてるわけじゃないから、僕は真実を書きました』
胸がヒリヒリしている。この言葉に共鳴しているのか、それとも背中を押されているのか
分からないけれど、湧き上がってくる感情を煌成は塞ぎきれなくなっていた。
この生徒はどんな気持ちでこれを書いたのだろう。
「ホモ発掘〜」
ニタニタ笑う井沢の厭らしい顔を今すぐ殴ってしまいそうになるのを煌成は我慢した。拳
が震えそうになっていると、思わぬところから厳しい声が聞こえた。
「そういう事言わない!井沢、噂好きなくせにキャパが狭い」
顔を上げると、藤が真剣な顔で井沢を諌めていた。
「なんだよ、自分だけ理解者ぶってんの?」
「そういうわけじゃないけど、井沢だって自分のマイノリティを軽視されたら気分悪い
んじゃない?」
「・・・・・・藤、何知ってんだよ」
井沢が急に声のトーンを変えた。藤はそれに臆することもなく、例えばの話だよと軽く
受け流した。
煌成は2人のやり取りを見ながら、このアンケートの回答者に対する評価が自分であって
も可笑しくないことを実感した。
もし、自分が伊純との関係をばらされたら、軽蔑する人間も出てくるのだろう。煌成は
それが怖いのだ。
妙な沈黙が続いた所為か、ホケカン倶楽部のメンバーの隣で事務作業をしていた伊純が
その手を止めて、生徒達に呼びかけた。
「みんなちょっといい?」
「・・・・・・」
「今の話、聞こえてたから、一言いいかな」
「・・・・・・はい」
伊純は先生らしい顔だったけれど、内情を知っている煌成にはその言葉は重かった。
「同性愛者を軽視する気持ちも、擁護する気持ちも人それぞれあって、それを相手に押し
つけることは出来ないと思うんだ。気持ち悪いって思うこと自体、自然な感情だと僕は
思うし。・・・・・・でも、彼らはそういう世間の目を浴びても、自分の心に嘘を吐きたくない
んじゃないのかな。彼らだって、どうして自分の好きな相手が同性なのか、どうしてそう
いう風になってしまったのか、理由なんて付けられないんじゃないかって思う。彼らは
世間の風と戦って、自己矛盾と戦って、それでもその道を歩んでる。それは、君達が好きな
人を思うこととなんら変わりがないからだよ。彼らの中では、顔のカッコイイ子が好き、
スタイルのいい子が好き、そういう嗜好と同じなんだと思うよ」
伊純の声が少し震えた。真桜は驚いて伊純の顔を見詰めている。バツの悪そうな井沢は
目を泳がせたままだった。
「伊純先生・・・・・・」
藤が声を掛けると、伊純は一瞬弾けたように身体を揺らした。それから現実の世界に戻って
くると、ゆっくりと呼吸をし始めた。
「アンケート集計はまだ時間掛かると思うし、今日はこれくらいで終わりにしましょう。
そろそろ下校の時間ですよ」
煌成の心のバリアに小さな亀裂が幾つも走っていた。
尻切れトンボのような幕切れで今日のホケカン倶楽部が終わりになると、メンバー達は
手早く片付けを終わらせた。真っ先に保健室を出て行ったのは井沢だった。
「お疲れ。明日も来いよ」
「・・・・・・へいへい」
藤が井沢に声を掛けると、井沢は面倒くさそうに手を振って去っていった。
真桜も鞄を手に取って藤の隣に並んだ。そこで、煌成がさっきから殆ど動けないでいる
ことに気づく。
「煌成、具合でも悪いの?」
「・・・・・・ああ?・・・うん。ちょっと。休めば大丈夫だから先帰ってて」
「そう?」
真桜はそう言うと、さほど心配する様子もなく、藤とともに保健室を後にした。
しんとした空気が煌成と伊純の間を通り抜けていく。
煌成はさっきの伊純の言葉が頭の中を駆け巡っていた。
あの言葉は伊純自身の気持ちで、それから煌成に向けた言葉でもあることくらい、煌成
にも痛いほど分かった。
多分、自分が一番引っかかっていた一線はこれなんだろうと煌成は思う。同性だから、
恋愛の対象にはならないと決め付け、告白してきた伊純にも、どこかで踏み込まれたくない
というバリアを張っていた。
噂は気にしないと常日頃思っていたはずなのに、いや、実際今までは気にも留めていな
かったはずなのに、伊純と自分が噂の的にされるのが怖かった。
世間体や噂なんていう形のないモノに脅かされて、自分の心を覗こうとしていなかった
ことに、煌成はやっと気づいた。
そして、覗いた先にあった感情に、煌成は驚きと同時に安堵を覚えた。
「・・・・・・」
ぎゅいっと胸の辺りが苦しくなる。
やっぱりそういうことなのだ。
「海老原君?胃痛ですか?本当に大丈夫?」
伊純が心配そうに覗き込んできた。
「・・・・・・うん。わかってる」
身体の奥から力を沸き上がらせて、煌成は立ち上がる。鞄を取って、帰り支度をすると
煌成は伊純を振り返った。
「センセー」
「はい?」
「・・・・・・今度の休み、先生のうちに行くわ」
「え?!」
「だって約束したの先生だろ」
伊純の顔は驚いた表情で固まって動かなくなっていた。煌成は目を逸らして保健室を出て
行った。
――>>next
よろしければ、ご感想お聞かせ下さい
nakattakotonishitekudasai ©2006-2010 kaoruko since2006/09/13