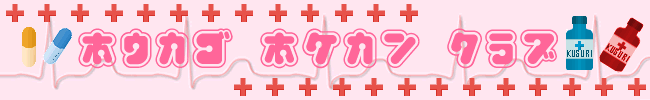
押してダメなら押し倒すまで・・・
息を切らして、保健室のドアを開けると、そこには伊純がいつもの様子でコーヒーを
口に運んでいた。
「せんせっ・・・」
「海老原君、どうしました?顔色悪いですね。貧血ですか?」
暢気そうに問いかける伊純に煌成は一瞬たじろいだ。
「先生、辞めるって・・・・・・」
継ぐ息の合間から、声を振り絞ってそう言うと、伊純は目を見開いて煌成を見詰めた。
しかし、直ぐにその目を細めると、煌成に保健室に入るように促して、そっとドアを
締めた。
「この学校は、本当に噂が早いんだなあ。気をつけないとね」
「先生・・・・・・?」
「まあ、いいや。とにかく座って、お茶飲んだら?海老原君の事だから、貧血でも胃痛でも
起しかねない」
頭の中にハテナマークを浮かべたまま、煌成は長椅子に腰を下ろした。
「先生、辞めるんじゃねえの?」
「噂だとそうらしいですね」
「違うのかよ!?」
「辞めさせられそうになった瞬間もありましたけど」
「なんだ、違うのかよ!」
一気に身体の力が抜けて、煌成は頭を抱えた。衝動に駆られてここまで走ってきた自分が
恥ずかしいやら虚しいやらで、隠した顔が上げられなくなる。
「海老原君・・・・・・」
伊純は、「きゅん」という表現をそのまま表情にした。伊純の今の顔を見たら、煌成はドン
引きするだろうが、伊純はお構いなく、目を潤ませていた。
あんなことをした自分を心配して、あの煌成がここまで走ってきてくれたのだ。これに
感動せずに、何をしろと言うのだ。
伊純は煌成の隣に座ると、軽く背中を撫ぜた。
びくりと身体を揺らして煌成が顔を上げる。伊純は苦笑いして、少しだけ煌成との距離
を置いた。
「海老原君は、どんな噂を聞いてきたんですか」
「色々・・・・・・」
煌成はここ数日聞いた噂を躊躇いながらも話した。伊純は初めこそ驚いていたが、最後には
困ったような笑いを浮かべて首を振っていた。
「白衣の中、見てみます?下着くらいはつけてますよ?」
「見ねえよっ」
辟易して煌成が答えると、伊純は小さな溜息を吐いた。
「君だから言いますけど、2年の男子生徒に告白されたのと、職員会議に掛けられたのは
本当です」
「え?」
「はい。それは本当です。・・・・・・それ以外は全てデタラメですけど」
伊純は事の真相を話し始めた。
「海老原君にあんなことして、本当はちょっと気が滅入ってたんですよ。当然だとは思って
ましたけど、次の日から海老原君、一切保健室に寄り付かなくなっちゃったし」
「それはっ・・・・・・」
「・・・・・・まあ、いいんです。自業自得だと思ってますから。で、僕にも隙が出来てたんで
しょうね。放課後に保健室に来た男子生徒に告白されて・・・・・・」
煌成は無駄にゴクリと喉を鳴らした。
「勿論答えは分かってると思いますけど」
「・・・・・・」
「あ、海老原君は僕の気持ち、まだ信じてないんですか」
「信じるって・・・!」
やっぱりあれは本当だったのかと、改めて思い出すと顔が熱くなる。
「僕は、他人の恋愛には寛容ですけど、自分の恋愛にはそれなりに責任持ってるつもり
ですよ」
「・・・・・・」
「まあ、疑われても仕方ないか。でも、ちゃんとその場で断りましたよ。・・・・・・だから、
君が思ってるようなことは起きてませんし、片っ端から取って喰ったりなんてこともあり
ません」
煌成はほっとしたような、それでいて、むず痒い気分で尻の座りが悪くなった。
伊純は声のトーンを変えると、煌成にだけ見せる茶目っ気たっぷりの笑顔になって言った。
「大体ね、僕はウケかタチかって言われたら100%ウケなんですよ。入れるより、入れられ
たいの。海老原君の綺麗なお尻には興味ありますけど、入れたいなんて思いませんから」
「なっ・・・・・・!」
煌成は尻の単語に無駄に反応して思わず立ち上がっていた。夢の中で伊純が「桃尻」と
称した自分のケツを、またも評価されてしまったのだ。
「綺麗ってなんだよ、綺麗って!」
「制服の上からでも分かりますよ。あ、この前身体測定でトランクスの越しに眺めさせて
もらいましたけど、海老原君のお尻は綺麗な形してますよ」
「そんなとこ、見てんなよ!!」
「まあ、それよりも、海老原君のコッチでいっぱい突いてほしいって夜な夜な妄想してる
くらいだし、間違っても海老原君のお尻を狙うことはありませんので、安心して」
しれっとした顔で、この男は何を言うんだと、煌成は目を丸くした。
「先生っ、あんた開き直ってねぇ?!」
「それくらい本心言わないと信じてもらえないんでしょ?」
伊純はほんのり照れたような顔でぷいっと顔を逸らした。
大胆なのか奥手なのかよく分からない伊純の態度に、煌成はどう対処していいのか戸惑い
を隠せない。
しかし、あんなことをされた後だから、この変貌も今は伊純の一部なのだろうと煌成は
頷けた。
「・・・・・・噂っていうのは本当に怖いですね。職員室でも真偽はどうなんだって、ちょっと
問題になって。結局は誤解は解けたんだけど。・・・・・・告白してきた子が飛び込んできて、
全部自分が勝手にしたことだから、僕の事責めるなって。生徒に庇われたのは初めてだった
ので、申し訳なかったです」
伊純はまた声のトーンを下げて先生らしい口調に戻った。
「・・・・・・よかったじゃん」
「はい。海老原君の誤解も解けたみたいだし」
「別に俺は・・・!」
なんでこんなに苦しい気持ちで保健室に走ってきたのか、今思うと自分でもよく分からない。
伊純に二度と会えなくなると考えた瞬間、無我夢中でここまで来たのだけれど、その根本
にある気持ちは何なのだろう。
考えると、直ぐに立ち行かなくなってしまうこのもやもやとした気持ちに、煌成はまだ
答えをつけることができないでいる。
けれど、こうやって保健室に駆けつけてしまったという事実は、自分が伊純を意識して
いるという証拠だ。
告白の答えを強要しないと言った伊純に、わざわざ答えるつもりもないけれど、少なく
とも自分の中で決着はつけたいと思った。
「授業始まってるっていうのに、心配してきてくれてありがとう。どうしますか?このまま
教室帰りますか」
「・・・・・・帰ったら変だろ」
「じゃあ、貧血にでもしてベッドで寝ていってもいいですよ」
保健医の勧めるべき行為ではない。伊純の親切心なのか下心なのか分からないお誘いに
煌成は疑いながら伊純を見下ろした。
「変なことすんなよ?」
「寝込みを襲う趣味はありません」
寝起きを襲った男が何を言うかと、煌成は眉を顰めたが、伊純はぷいっと顔を逸らして
しまい、どんな顔をしていたのか確認できなかった。
「先生!!」
伊純と煌成が長椅子で話していると、突然保健室のドアが開いた。
大声とともに飛び込んできたのは真桜だった。
「真桜?!」
「塚元さん?」
「・・・・・・なんで、煌成がいるのよ!」
「なんでって・・・・・・まあ、いろいろ」
「ふふん。あんたも心配で駆け込んできたのね」
真桜はそう言って、2人を見比べた後、急に真面目な顔付きになって伊純に向かって頭を
下げた。
「塚元さん?!」
「何してんだよ?」
「・・・・・・先生、ごめんなさい。先生がこんな目に遭ったのは、私の所為なんです」
きっぱりとそう言うと、真桜は暫く頭を下げたまま動かなかった。
「は?!・・・・・・真桜、何したんだよお前?!」
「塚元さん、とりあえず頭上げて?」
真桜は言われて頭を上げると、申し訳なさそうな顔で伊純を見た。
「噂を流したのは、井沢です。でも、そう仕向けたのは私・・・・・・」
「はあ?!」
「・・・・・・藤君と煌成の噂を流されて、私噛み付いたのよ、井沢に」
「そういえばそんな噂話も流れてたな」
周りはすっかり伊純の話題で持ちきりになっていて、藤と煌成と真桜の三角関係の噂なんて
すっかり下火になっていた気がする。
「私ね、井沢の弱み、一つだけ握ってて。それチラつかせて、何とかしないとそればらす
よって迫ったのよね・・・・・・まさかそれで、伊純先生の新しい噂流してかき消すなんて、思い
も寄らなかったけど。しかも、井沢も相当悪乗りしてたみたいだから・・・・・・気がついたら
こんな酷い噂が蔓延してたのよ・・・・・・。伊純先生が辞めさせられるって聞いて慌てて井沢
のところに言ったら、それも噂で嘘だって教えられてね。とりあえず私だけでも、謝りに
いこうと・・・・・・。だから、先生、本当にごめんなさい」
煌成も伊純も真桜の説明を唖然として聞いていた。この噂話にそんなカラクリがあったとは
伊純ですら気づいていなかったようだ。
「そういうことだったんですね。どうして、いきなりこんなに話が大きくなっていくんだろう
って自分でも不思議に思ってたんですよね」
伊純はふふっと笑って真桜に答えた。
「先生、暢気に言ってていいのかよ?」
それを聞いてイラつきを隠せなかったのは煌成の方だった。幾ら他の噂を消すためと言え
伊純のありもしない噂を流して、伊純をこんな風に陥れた井沢の行為に煌成は明らかに
ムカついていた。
「別にいいですよ、先生の噂なんて生徒同士の噂に比べれば大したことありません。それに
僕はこうしてちゃんと職を追われずに済んでますから」
「先生、本当にごめんなさい」
真桜は段々泣きそうな顔になっていた。普段の強気の彼女から見れば、真桜自身もこの件
については相当責任を感じているようだった。
「はい。謝罪はちゃんと受け取ったから、もういいですよ。それよりも、授業始まってる
けど、大丈夫?」
見れば真桜はジャージ姿で、体育の授業を抜け出してきたようだった。
「ちょっと足捻ったって言って抜け出したの。あ、でもちゃんと戻ります。煌成は?」
「俺、貧血」
煌成は元気そうな顔でしれっと言った。
「・・・・・・そう」
真桜は何も言わず、保健室を出て行った。
伊純と向かい合って時間潰すのも躊躇われ、煌成はそそくさと保健室のベッドに横に
なった。このベッドにこんな健康体で寝そべっていることが後ろめたさを感じさせ、煌成は
早々に目を閉じた。
頭の中で伊純が渦巻いている。何で自分はここまで走ってきたのか。どうして、こんなに
伊純の事で頭が一杯になっているのか。出てきそうな答えは、後一歩の所で、煌成を翻弄
させていた。
好きと言われて、その気持ちを理解することまではなんとか辿りつけたけれど、自分の
気持ちはどうだと問われても、そこにはやっぱり飛び越えられない一線がある。
自分は男だし、ゲイでもない。真っ向から否定するには切なくて、受け入れるには苦しい。
「・・・・・・」
煌成は顔を擦って、伊純を頭の中から追い出そうとした。
「海老原君、起きてる?」
「・・・・・・うん?」
カーテン越しに声を掛けられて、煌成は掠れた声で返事をした。
「・・・・・・わざわざ、心配して来てくれてありがとう」
「別に、心配してたわけじゃねえよ」
「そう?でも、こうやって会いに来てくれたって、脈アリなんでしょうかね?」
緊張しているのか伊純の声は少し震えているようにも感じた。
真剣な空気が漂って、煌成も身体を硬くする。今一番されたくない質問だった。
「・・・・・・」
違うと即答できないところで、既に煌成は伊純に引っ張られているのだけれど、煌成は
まだ認めることが出来ない。
「あれから・・・・・・」
「はい?」
「あれから、確かに先生のことで頭一杯で、よくわかんないんだよ。俺さ、確かに先生に
あんなことされても、すげえ嫌とは思わなかったし、気持ちよかったくらいには思ってる
けど、先生の事好きか嫌いかって言われるとさぁ・・・・・・」
よく分からないのだ。死ぬほど嫌だとは思わないけれど、男同士の恋愛も、自分と伊純が
付き合うことも、想像できない。
曖昧な答えの煌成に伊純は甘い誘惑の言葉を掛けた。
「じゃあ、もう一度やってみる?」
「はあ?!・・・・・・なんでそういう展開になるんだよ・・・・・・」
「最後までやってみたら、わかるかもしれませんよ」
「どんな誘惑の仕方だよ、それ」
「今度の日曜日、うちに来てください。待ってますよ」
伊純は一方的に話を進めると、カーテンの前から気配を消した。
「強引過ぎじゃねぇ・・・・・・?」
ベッドの上に残された煌成は呆然と天井を見詰めていた。
――>>next
よろしければ、ご感想お聞かせ下さい
nakattakotonishitekudasai ©2006-2010 kaoruko since2006/09/13