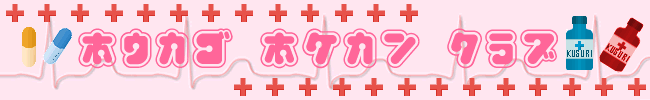
今時、10歳の年の差カップルなんて珍しくない・・・
緑川伊純はゲイだ。カミングアウトしているわけではないので、その事実を知っている
のは、ごくごく親しい人間だけだが、紛いも無く伊純はゲイだ。
ただ、カミングアウトしていなくても、自分の気持ちにマイナスな要素一杯で塞ぎ込んで
いるわけではない。
自分がゲイであることに疑問を持ったり、恥だと思ったり、どうしたら女性を好きに
なれるのかと悩んだり、そういう時期はとっくに過ぎて、今はそういうもんなのだから仕方
ないと諦めている。
大学の同級生や同僚は結婚し、そろそろ子どもが出来た人間もいる。そういう幸せな家族
の形を見ていると、自分の置かれた立場は切ないとは思うけれど、ゲイでも幸せになれる
瞬間はあると信じてるし、今までもそれなりに楽しい恋愛もしてきたつもりだった。
けれど、今度と言う今度ばかりは、自分でも絶望的な恋をしてしまったと思ったと、恋
に落ちた瞬間に伊純は後悔した。
緑川伊純はゲイだ。カミングアウトされた親しい人間ですら、いまいちそのタイプまでは
理解はしていないが、伊純は紛れも無くゲイで、しかも面食いで、年下好きだ。
今まで、2、3歳若い男とは付き合ったことがある。見た目はもっと5歳くらい若く見えた
けれど、中身はやっぱりちゃんと年相応で、後ろめたさなどなかった。
・・・・・・が、今回伊純を一発でとりこにしてくれた男は、10歳も年下の、未成年だ。
未成年に手を出すなんて、聖職者としてはあるまじき行為だと分かっているが、好み
の顔を見つけてしまったものは仕方が無い。
緑川伊純は、あの最低の出会いの中で、海老原煌成の顔に一目惚れしてしまったのだ。
確かに、顔だけはいい煌成は一目惚れされ率はかなり高い。これで煌成が中身を伴った
好青年でにっこりでも微笑めば、ころっと落ちていく人間がゴロゴロいそうなもんだが、
実態はただのエロ高校生で、その辺歩いてるエロガキと大差ない。
伊純もそんな性欲マックス丸出しの状態で出会ってしまった、のにだ。
更に、彼には沢山の噂が付きまとっているらしく、それを吹き込んでくれた生徒の話を
半分くらいしか信じなかったとしても、恋愛の対象として考えるのは、普通なら「なし」だ。
・・・・・・が、煌成の顔は、伊純の好みのど真中ストライクで、こうして再び目の前に現れる
と、やっぱり尋常ではいられなくなるのだった。
「・・・・・・先生?」
覗き込まれて、伊純は我に返った。至近距離に煌成のアップがある。息でも吹きかかりそう
で、伊純は動揺をごまかすために眉間に皺を寄せた。
「・・・・・・っ、血圧、測りますよ」
煌成の腕に器具を巻きつけて、伊純は血圧を測り始める。握っている手から煌成にこの熱
が伝わってしまわないかと伊純は必要以上に殻を被った。
そんな伊純の心情など考えにも及ばず、煌成は未だキリキリと痛む胃を押さえながら、
伊純の顔を間近で覗き込んでいた。
「・・・・・・なんですか」
「いや、なんか先生ってさー、まつげ長いね。あ、しかも瞼のとこホクロある?すげえ、
それどうなってんの?」
煌成に他意はなく、ただ見たままを口にしただけなのに、覗き込まれた伊純は、思わず
驚いて椅子を引いてしまった。
血圧計がくっ付いたままで腕を引っ張られた煌成は派手に痛がっている。
「痛てえ、先生、痛いって」
「・・・・・・」
慌てて血圧計を机に戻すと煌成は顔を歪めて呟いた。
「そんなに、露骨に嫌な顔しなくてもいいのに・・・・・・」
ファーストインパクトは最悪だったのだから、伊純が煌成に抱いている感情もよくないと
煌成は勝手に思っていたし、さっきの事だって、不審がられているからこその対応なのだ
ろうと思う。普通ならばそうだ。
「お、驚いただけです」
フォローはそれくらいしか出来なかった。煌成は「別に先生に嫌われても、ちゃんと寝か
せてもらえれば構わないけどね」とぼそぼそと言って、血圧計の外れた右腕を擦った。
それから煌成は、オバチャンに一言二言声を掛けると、勝手知ったるといった風にカーテン
を閉めてベッドに潜り込んでしまった。
伊純は複雑な気分でそのカーテンを見詰めていた。
目が覚めると、煌成は見慣れた天井の模様を見詰めていた。ここが保健室で、自分は
胃痛が酷くて眠っていたのだと思い出す。
胃の辺りに手を置いてみて、酷い痛みは過ぎていったことを知った。薬が効いたのだろう。
煌成は寝返りを打ってポケットからケータイを取り出した。
時間は、4時間目の真ん中辺りで、中途半端に起きるよりはこのまま4時間目が終わるまで
ここでゴロゴロしていようと思っていると、保健室のドアを開ける音がして、少し慌てた
感じの声がした。
「先生ぇ〜!」
「どうしました」
対応したのは伊純で、その声は自分に掛けてきた声よりも数倍優しく聞こえた。
「この子、テニス場で転んじゃって・・・・・・左足のココ、結構血が出てるんだけど・・・」
付き添いの女子が説明をすると、伊純の「痛そうですね、大丈夫?」という声がした。
煌成は何故だかその伊純の声に釘付けになって、息を潜めてその会話に集中した。
「先生〜、痛い!」
怪我をした生徒が高い声を出している。
「はいはい。慌てなくてもいいですよ。とりあえず、そこで砂を洗い流しましょう」
水の流れる音に、生徒の泣きそうな声、それから伊純の心地よい声が煌成の元に届いた。
「随分派手に転んだんだね」
「ボール追いかけてたら、足が絡まっちゃって・・・・・・先生、しみるよー!」
「ちょっとだけ我慢できる?砂がついてると消毒できないから」
「うう〜痛いよー!」
「うんうん。頑張れ」
優しい伊純の声に、煌成は驚いていた。
この男は、こんな優しい対応が出来るんじゃないか。何で自分の時はあんな無愛想で
意地悪い事してきたんだろう。
伊純の声を聞いていると、段々と腹が立ってきた。
「先生、治る〜?痕残っちゃう?」
「ちゃんと手当てしていれば、治りますよ。はい、じゃあ消毒するよ。ちょっとしみる
けど、我慢してね」
「・・・・・・いったーい!」
「頑張れ〜、頑張れ〜」
そうか、分かった。この男は極度の女っタラシで、女には優しいけど男には冷たいんだ。
煌成は伊純のヘラヘラしている顔を想像して、小さく舌打ちした。
あの眉間に深く入った皺の男が今どんな顔をしているのか想像するだけで気分が悪い。
最低な女タラシだ。
煌成は、これ以上伊純の甘い声を聞くのが耐えられなくて、布団をひっぱり上げると
頭のテッペンまですっぽりと被った。
真っ暗闇の中で、ブツブツ小言を呟くと、またキリっと胃の辺りが傷んだ。
「別に、嫌われてたって、構わないっつーの・・・・・・」
けれど、そう思う一方で、自分もあんなふうに伊純に対応してもらえたらよかったのにと
考えてしまったのは、自分が弱っているからなのだと、煌成は目を閉じて無理矢理そう思い
込ませた。
新学期は決め事が多い。クラス委員から各種委員会の委員、掃除当番まで、今日のホーム
ルームで一気に決められてしまった。
大抵の役は立候補、決まらないものはジャンケンなのだが、どういうわけか、煌成の役
だけは、多数決で決められてしまったのだ。
煌成は黒板に書かれた文字を眺めて、溜息を吐いた。
『保健管理委員――海老原煌成』
何で俺が・・・と何度も呟きながら、再び大きな息を吐くと、前の席の袴田がブルっと震えて
振り返った。
「いやん。首筋に煌成の息が掛かって感じちゃうん」
「キモいわっ」
「そりゃ、こっちの台詞!さっきから、はぁはぁ、鬱陶しいっつーの!」
「だって、なんで俺が保健委員なんだよ!?」
「そりゃあ、お前が一番保健室使ってるからだろ」
「その理論がおかしいだろ。保健委員は体調の悪いやつを保健室に連れてったり、応急
処置をする人間だって、前置きがあっただろ」
「自分で自分を世話してくださいって事じゃねえの?」
「んな、無責任な」
「煌成こそなんでそこまで嫌がるんだよ。大して仕事あるわけでもないのに」
そう言われて煌成はぶすっと口をひん曲げた。イケメンも台無しだ。
確かにそれ程多くの仕事は無い――だろう。保健委員会の仕事など大して聞いたことが
ない。煌成が知ってるのはせいぜい体調の悪い生徒の付き添いで、保健室まで連れて行く
ことだ。しかも、余程一人で行けない場合を除いては、自分で行くし、委員なんて名があって
無いようなもんだとも思っている。
けれど、保健室には、あの男がいるのだ。新しい養護教諭、緑川伊純が。
自分だけにはやたらと厳しい、天敵かもしれないとまで思わせる男。極力会いたくは無い。
女子生徒に優しくしていた伊純を女タラシだと思っていたが、あの後、煌成ははっきり
と思い知ることになったのだ。
あんなに厳しい対応をしてくるのは自分だけだと言うことを。
煌成が胃痛で保健室で眠っていた日のことだ。昼休み少し前、4時間目の授業も残り5分、
そろそろ起きようと、身体を起したとき、今度は男子生徒が入ってきた。
「せんせ〜、やべぇ、超痛いんだけど」
「どうしました?」
「指、突いた」
「・・・・・・ああ、ホント。痛そうだね。内出血してるし、骨折してるかもしれないなあ・・・・・・
固定してアイシングするから、今日中に病院行ってみてもらいなさい」
伊純の優しい声が煌成の元にも届く。ちょっと前に来た女子生徒と同じような柔らかい
口調だ。女タラシではなく、普通に平等に優しいのだろうかと、煌成は耳を澄ませた。
「げぇ・・・マジで〜?俺、そんなに酷いの?」
「うーん、内出血してるからねえ、見てもらった方がいいなぁ。突き指だって甘く見てると
後で酷い目に遭うこともあるし」
「マジ?」
「最悪、関節が曲がらなくなっちゃう事だってあるよ。で、何やってたの?バレー?バスケ?」
「・・・・・・鬼ごっこ」
「・・・・・・ぶっ」
「笑うことないじゃん。バスケのコート待ちで暇だったんだよ」
クスクスと伊純の笑い声が聞こえてくる。あのしかめっ面がどうやったら笑えるのか、煌成
はにわかには信じられなかった。
「まあ、授業中の出来事だから、共済からもお金が下りるし、一度担任の先生に連絡して。
書類はこっちで揃えておくから」
「金出んの?!」
「多少ね」
親切丁寧に、そして多分的確に(多分・・・と言うのは、煌成からは見えないし、どれが的確
なのか煌成には分からないから)応急処置をされて、男子生徒は保健室を後にしていった。
煌成は釈然としないまま、ベッドに座っていると、カーテンの隙間から伊純と目が合って
しまった。
伊純はゆっくりと近づいてくると、カーテンを開けて、やっぱり仏頂面で煌成を見下ろ
したのだ。
「昼休みです」
「・・・・・・分かってるよ」
なんなのだ、この男は。幾ら自分が能天気だの楽天家だの言われても、流石にここまで露骨
な態度を取られれば、煌成だって腹は立つ。
「ちょっとは気分よくなったんで、戻ります、よ!」
嫌味ったらしく言い捨てると、煌成は保健室を出て行った。
伊純が吐いた溜息の意味など、知る由も無く。
「今週の金曜日には、委員会の顔合わせがあるので、委員になった人は、昼休みに集まる
ようにー」
新しく決まったクラス委員が、黒板に委員会の場所を書き終えるとそう言った。
「・・・・・・面倒くさい」
「伊純ちゃんが、美人のお姉さまだったら、ソッコウ替わってやるんだけどな」
「何で俺なんだ・・・・・・」
体調不良で会うのだって、避けたいのに、どうして委員会でまで顔を会わせなくてはなら
ないのか。
煌成は、もうどうやっても覆らないだろう黒板の文字を見て、もう一度溜息を吐いた。
金曜日の昼休み、煌成はイヤイヤながらも、保健室に足を運んだ。
「失礼しまー・・・」
保健室のドアを開けると、一斉にそこにいた生徒が振り返って、煌成を見た。
「な、に?」
「おそーい。やっと最後の一人が来たー」
おそらく3年の女子に突っ込まれて、煌成はぺこぺこ頭を下げると、空いている席に急いで
座った。
周りを見ると、オバチャンと、今日は機嫌のよさそうな伊純。それから、何故だか今年
も保健委員の井沢と、今は会うと気まずい真桜までいた。
「・・・・・・」
煌成は益々肩身を狭くして、デカイ身体を丸めた。
「えー、では、第一回の保健管理委員会を始めます。改めまして、今年からこの学校に
養護教諭として赴任してきた緑川伊純です。今年は国村先生と二人体制で保健室を支えて
いきますので、どうぞ宜しく。皆さんにはこれから半期、保健管理委員として活動してもらう
ことになります。保健管理委員の仕事は皆さんに配ったプリントに書いてありますので、
順を追って説明しますね」
手元のプリントに目を落とすと、煌成は保健委員が意外と仕事の多い委員会であることを
初めて知った。
伊純がプリントに沿って説明をしている。煌成はそれを適当に聞き流した。
「・・・・・・説明は以上です。では、最後に委員会のメンバー自己紹介と委員長を決めて終わり
たいと思います。では、そちらの席からお願いします」
そう言われて、順番に自己紹介が始まると、この部屋に微妙な空気が流れ始めたことを
煌成は感じた。
「・・・・・・?」
順々に生徒が名乗って頭を下げていく。2年生のメンバーは半分以上は顔は知っている生徒
だった。
「2年6組の、藤です」
藤は学年1,2とも言われる秀才だ。それくらいは煌成だって知っている。こんなヤツでも
保健委員なんてするのかと思いながら辺りを見渡すと、真桜が藤とをチラチラと見ていた。
「・・・・・・?」
それから、膝に置いた拳をきゅうっと握り締めたのが煌成の席から丁度見えてしまった。
「!」
真桜の頬がほんの少し赤くなっている気がして、煌成は滅多に働かない勘が動いたようだ。
『本気で狙ってる人いるんだから』
真桜の言葉が蘇る。真桜の本気は、コイツか。
今は彼女でもなんでもないが、やっぱり面白くない気がして、煌成は正統派優等生な
雰囲気満点の藤を見て、眉を顰めた。
その姿を、歩く拡声器井沢がニヤニヤ見詰めている。新しいメシのタネがまた一つ舞い
込んできたとでも思っているのだろう。
伊純は、そんな生徒達を見回しながら、心の中で小さく溜息を吐いた。
かくして、保健管理委員会は、数々の思惑を抱きながら始まることとなった。
――>>next
よろしければ、ご感想お聞かせ下さい
nakattakotonishitekudasai ©2006-2010 kaoruko since2006/09/13