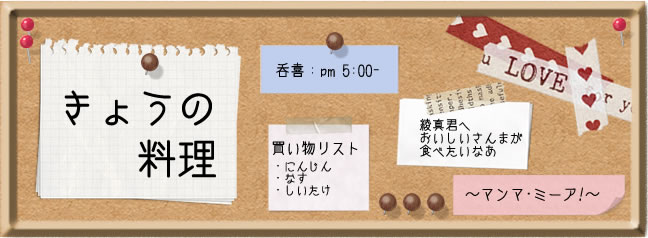
レシピ7:ほっこり粥で良薬口に苦くない!―中編
「先週は、不本意ながら忙しくてね。……ずっと気にはなってたんだけど、中々お店に
行けなくてやっと仕事が片付いたと思った途端に、これだよ。呪われたかな……」
誠史は先ほどより、幾分マシな顔をしているが、それでも熱っぽい顔で綾真を見上げた。
掠れた声から、熱があるだろう事は余裕で察することができる。綾真はこんな状態で、
クレープなんて食べられるのか心配になったが、誠史が手を伸ばすので、流れのままクレープ
を渡してしまった。
「あの、本当に無理しないでくださいね?」
「無理して食べなきゃいけないものを、俺が食べたことがある?」
「ないと思います」
「なら大丈夫だよ」
クレープは冷凍庫から冷蔵庫に移され、半解凍状態になっていた。誠史は包んであった
ラップをゆっくりとはがすと、出てきたクレープを見て、ほお、と小さく唸った。
「そうそう、そういえばこんな形だった。懐かしいなあ。手触りもこんな感じだったよ」
綾真は急に緊張がやってきて、思わず立ち尽くした。拳に力が加わり、誠史の口を凝視し
ている。誠史はかぶりつく口を止め、苦笑いで綾真を見た。
「……とりあえず、座ったら?」
「え?あ?」
「そんなに見詰められると、こっちまで緊張しちゃうじゃない」
誠史はダブルベッドの隅っこをポンと叩くと、そこに座るように促した。綾真は緊張していた
自分に恥ずかしくなったのか、素直に誠史に従った。
誠史は綾真の姿勢に満足したようで、にっこり笑うと、今度こそクレープに口をつけた。
「あっ!?」
誠史は一口、口に含んだ後一言を発して固まってしまった。
「……」
綾真はその反応の意味が分からず、膝の上で拳を握った。誠史の喉が動いて、クレープが
体の中へと入っていく。誠史は何も言わず手にしたクレープを見詰めていた。
「……」
「あの……誠史、さん?」
思い出の味とは違ったのだろうかと心配になって声を掛けると、誠史はゆっくりと綾真を
振り返った。
「小5の夏がフラッシュバックした」
「はい?」
「匂いとか味とかって、生きてきた時間を遡れるんだって今分かった」
「誠史さん?」
誠史はもう一度クレープを口に運ぶと、思い出を噛み締めるように食べ進めた。綾真は
掛ける言葉を失って、ただそれを見詰めた。
火照った身体を冷やしてくれるのか、誠史は熱で食欲のなさそうな割にはするりとクレープ
を完食した。誠史は食べ終わると、暫く無言で手の中を見詰めていた。さっきまでそこに
あった物がまるで幻だったかのように、あるいは消えてしまったクレープの名残を惜しんで
いるかのように、掌を見詰めている。
何度か瞬きをした後で、誠史はやっと言葉を発した。
「……やばいなぁ……参った」
誠史は顔を擦って唸る。綾真は自分の心臓が高鳴って止められなくなっていた。試験前の
緊張によく似たそれは、不安よりも期待でいっぱいだった。
「大丈夫ですか!?」
「完全に綾真君にやられたよ。すっかり思い出さなくてもいいものまで思い出した」
誠史の声が鼻声に変わった。忘れかけていた思い出をクレープと共に引きずり出された
らしい。
「ということは、クレープの味としては、成功なんですよね?」
「……そのものだね」
綾真は小さくガッツポーズを決め、ほっと肩の力を抜いた。けれど見上げた誠史の顔は
晴れ晴れとはしておらず、それは熱の所為だけではないように思えた。
「誠史さん?」
「うん。ちょっと、話してもいい?俺がこの前、テレビに出ることになった経緯」
「え?……はい」
誠史は熱の声で昔話を語りだした。
「俺の母親はさ、アイドルだったんだ。売れないアイドル。小さい頃から夢見て夢見て
夢を見すぎて、本気になっちゃった人。アイドルになりたくて劇団所属して、ボイトレや
演技の勉強して、そしたらさ、念願の新人発掘のオーディションで準優勝しちゃったんだ」
「凄いじゃないですか!」
芸能人の家系なのかと、綾真は誠史の整った顔を見て妙に納得した。
「そのオーディションっていうのは、優勝者も準優勝者もスポンサーが付くことで有名で、
アイドルを夢みていた母親も、それ一本にかけていたんだそうだ。それで、準優勝なんて
しちゃったもんだから、夢にまで見たトップアイドルになれると本気で思ってたらしい。
まあ実際、晴れてアイドルになったわけで、いよいよテレビに出て活躍できる、期待を胸
に踏み出したんだけどさ」
誠史はそこで溜息を吐いた。『売れないアイドル』というのだから、うまく行かなかった
のだろうことは推測が付く。その理由に綾真は耳を傾けた。
「母は、多分運がなかったんだよ。大船麗美って知ってる?」
「女優ですよね?」
その名前は綾真でも知っている女優の名前だった。50を当に過ぎてるはずなのに、華麗な
身のこなしでいくつもの役をこなす大女優だ。
「そう。そして、母が準優勝したオーディションで優勝した人」
大船麗美は並の新人ではなかった。超が付くほど大型の新人で、デビューが決まった瞬間
にすでに10社とCM契約をしていたという逸話まである。綾真が知ってる大船麗美はすっかり
大女優になった顔だが、新人のころはプリプリのアイドルとして売り出されていたのだ。
「だからね、折角準優勝したにもかかわらず、すっかり霞んでしまったんだ、母は」
それでも、最初は頑張ってたんだという。歌手デビューも果たし、CMもドラマにもそれ
なりに出ていたらしい。
しかし、次第に仕事は減り、ついに誠史の母は引退してしまった。
「似てたんだ。彼女と母は。背格好から顔の作り、性格のタイプまで何もかも似ててさ、
そうなると、知名度が上の方が使いたくなるもんでしょ」
「そういうものなんですか」
「そういうものみたいだね……ゴホッゴホッ」
そこまでしゃべると誠史は盛大に咽た。綾真は誠史の為に水を差し出すとありがとうと
言って少しずつ喉を潤した。
「大丈夫ですか?」
「ああ、大丈夫。続き話してもいい?」
「はい」
彼女は芸能界を引退し、一般企業に就職した後、お見合いで知り合った男性と結婚した。
誠史の母はもう芸能界に未練はないと、そのときは思っていたそうだ。誠史を身ごもり、
家族3人幸せな生活をしようと描いていたそのころ、大船麗美が先輩俳優と電撃結婚という
ニュースをワイドショーで知った。さらに、大船麗美のお腹には新しい命が宿っている
という事も大きく報じられ、誠史の母はバチンとスイッチが切り替わってしまったのだと
いう。
「それって……」
「まあ、ある意味復讐?あっちが自分の子どもをタレントにするつもりがあるのかない
のか知らなかっただろうし、完全にうちの母の思い込みなんだけど、自分で負けた借りは
子どもで果たすって思ってたらしいよ」
それが誠史が芸能界に入るきっかけだったのだ。綾真は胸の奥から湧き上がる不快感を
飲み込みながら言葉を吐いた。
「子どもは道具じゃないでしょう……」
「母親に聞かせてやりたいよ」
「あ、すみません……」
誠史は慣れた風に苦笑いして首を振った。
「生まれたときからどこかの劇団に入れられたんだ。初めての仕事はCMだったかな。勿論
全く覚えてないけどね」
「そんな小さい時から?!」
「俺の子役人生は順風満帆だったよ。なんせ忙しすぎて、全く記憶にないんだから。凄い
でしょ?仕事してた記憶も、学校行ってた記憶も、友達と遊んだ記憶もないの」
子どもの頃の記憶が殆どないと言っていた意味を綾真は初めて理解した。そしてそれを思う
ととても悲しくなって、それから自分と誠史の生きてきた環境の違いに愕然とした。
「自分で言うのも何なんだけど、売れっ子だったと思うんだ。僅かに残る記憶の中の俺は
大体ふてぶてしい嫌なガキなんだけど、周りがそれを許してたってことは、多分そういう
待遇されてたからなんだと思う。ガキが天狗なんて手付けられないよ。でも、子役生活は
あるとき突然終わったんだ」
綾真はてっきり誠史がクビでも切られたのかと思ったら、そうではなかった。
「俺ね、初めて自分で自分の意見を言ったの。『子役辞めます』って」
それが小学校6年の夏で、最後の映画を撮る前の事だった。誠史は自分で決めて、自分で
周りの大人を説得して回った。
「その代わり、最後の最後だから、絶対にいい作品を作るって豪語してね。それは今でも
覚えてる。そこからは普通に中学行って、高校行って、大学行って」
「就職して、結婚して?」
「そうそう。離婚して、綾真君に出会って」
「客としての印象、最悪でしたけど」
「でも、好きになっちゃった」
「……その冗談、もうそろそろ止めませんか」
「何?まだ冗談だと思ってたの。そんな頑固な頭はこうして、こうだ!」
「うわぁっ、ちょっと、やめてっ……」
綾真は手を引かれると、誠史の胸に抱え込まれた。誠史の身体の熱は高いままで、心臓が
早く波打っているのも分かる。こんな至近距離に近づいてもあからさまに拒否できないのは
きっと誠史が病気だからだと綾真は自分に思い込ませた。
誠史の腕はすぐに解けそうなほど緩かった。熱で力が入らないのだろう。誠史の熱が綾真
にまでうつりそうな距離に、綾真の心臓もトクンと鳴った。
「忙しいのが慣れると怖いんだよ。俺は2回も失敗してるしね」
そういえば誠史の離婚理由も忙しい自分とのすれ違いだったはずだ。
「どんな子ども時代だった?って綾真君に聞かれて、本当は俺が一番最初に思い出したのは
大人たちの操り人形って言葉だったんだ。綾真君は幸せな幼少期を過ごしてきたんだろ?
お父さん亡くされたのは悲しい事だと思うけど、正直綾真君がちょっと羨ましいって思った」
10歳までの記憶が殆どない誠史と13歳までの記憶に縋っている自分は、どっちが不幸なんだ
ろうかと綾真は思った。
綾真が胸の中で居心地悪そうにしていると、誠史は綾真の頭を優しく撫でた。
「あー、はいはい。不幸自慢なんてしてるわけじゃないよ。後悔もしてないし。それが俺
の人生だって今はちゃんと受け入れてるし。給食のクレープはね、俺が子役辞めるきっかけ
になったデザートなんだ」
「え?そうなんですか?」
誠史はほんの少しだけ懐かしそうな顔をして、静かにしゃべりだした。
「今思うとね、あの頃が一番感覚が麻痺してたんだと思う。小5の夏、俺は本当に王子様
だったんだよ。学校行っても俺だけ特別扱いだったのを普通だと思ってた」
綾真は誠史の胸の中で目を閉じた。小学五年生の誠史が目の前に現れた気がした。
――>>next
よろしければ、ご感想お聞かせ下さい
nakattakotonishitekudasai ©2006-2010 kaoruko since2006/09/13