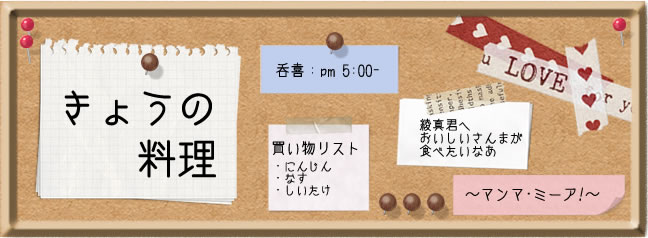
レシピ11:ドルチェ・ドルチェ・ドルチェ―前編
誠史に好きだと言ってしまった……。
好きという言葉に胸がきゅうっと苦しくなる。好きだと認めたら、黙っていられずには
いられなかった。
綾真の内側は「誠史が好き」で満たされて、少しでも揺れたら溢れてしまいそうだった。
これ以上余計なことを口走らないように、綾真はしっかり口を塞ぎ、身体を固めて車の
シートに座り直した。
「ねえ?」
山を下りながら、誠史はちらりと綾真を振り返った。綾真は頬を赤くしたまま硬直している。
「綾真君?」
もう一度呼ばれて、
「はい!」
と体を揺らして返事をすると、綾真は漸く誠史を見上げた。ぎこちなさを隠すことも出来
ず、照れて笑える余裕もなく、目に溜まった涙は乾ききらないまま綾真の全てが停止して
いる様だった。
誠史は苦笑いして車を走らせる。下り坂を器用にシフトチェンジさせながら走っていたが、
ふとシフトレバーに置いていた手を離すと、綾真の紅潮した頬をさらりと撫でた。
びくりと身体を飛び跳ねさせ、綾真はシートにぶつかった。誠史は再びシフトレバーに
手を戻すと一目綾真を見下ろした。
「どっちがいい?」
「え?はい?!」
その反応に誠史はクスクスと笑う。
「愛を紡ぐ話と明日の晩ごはんの話」
「……へ?」
「どっちが楽しい?」
「……あ、あの……」
問われて、綾真は自分の置かれている立場を漸く考え始めた。
先ほど自分から告白して、晴れて自分たちは「恋人同士」になったのだ。10分前、1時間前、
半日前、一ヶ月前どの誠史とも変わらないはずなのに、今、目の前にいる誠史は明らかに
別の存在なのだ。自分が一人誠史のことを好きなわけではない。ちゃんと打てば答えが返っ
てくる。いや、正確に言うなら放たれた問題の答えを返したのは自分の方だ。恋人という
単語に一人で反応し、綾真は益々余裕がなくなってしまった。
「綾真君?」
「あの!ちょっと待っててもらってもいいですか。色々気持ちの整理がつかなくて、自分
がどうしていいのか、わかんないんです」
「君ってどこまで真面目なの」
ため息を吐かれて、綾真は誠史の余裕に逆ギレしそうになった。自分はいつだって掌で転
がされている。一度は社会人も経験した23の男なんだから、充分大人だと思ってたけど、誠史
の前じゃ子ども同然だ。
悔しくて、綾真は誠史を睨みあげた。
「俺ばっかテンパっててかっこ悪いんです」
「そこが可愛いんだけどね」
「もう、ちょっと誠史さんは黙っててください!!」
「……はいはい」
誠史は軽く肩を揺らして返事をすると、無言で車を走らせていった。
理屈なしに好きだと思う瞬間がくる。
例えば、車を運転する横顔を見てかっこいいと思ったり、目が合ってにっこり笑った顔を
見せてくれたり、優しく髪を撫でてくれたり。無性に好きだと思い、胸がきゅんと鳴った。
同時に自分が浮かれているのが恥ずかしくて綾真はそっと窓の外に目をやった。
車は街中に戻ってきて、賑やかなイブのイルミネーションの下をカップル達が手を繋いで
歩いている。先ほどと同じ光景なのに、見える世界が違う。自分にもあの甘ったるいピンク
のオーラが出ているのかと思うと、走り出したい気分だった。
誠史にもこの甘く恥ずかしくなるような空気がまとわりついているのだろうか。
「綾真君、本当に大丈夫?」
声を掛けられて振り返る。けれど、誠史は先ほどの誠史と変わりなく、綾真は急に不安が
心をよぎった。
誠史は自分のことをどれくらい好きなんだろう。自分のどこが好きなんだろう。なんで
自分を好きだと言ってくれたんだろう。
今まで疑問にすら思っていなかったことが頭を支配し始めた。そして一度その悪魔に取り
つかれると、もうそのことしか考えられなくなっていた。
綾真が思考の悪魔に取り憑かれている間に、車は誠史のマンションの駐車場に滑り込んだ。
「で?君の言うところの気持ちの整理は付いた?」
車を降りてからも、綾真は真面目くさった顔で誠史の後ろを歩き、玄関を入ってソファに
埋もれるまで一言も言葉を発することができなかった。
その間、綾真はずっと誠史の気持ちを考えていた。自分が気持ちが揺れて、誠史のことを
好きになったことは今はちゃんと認められるし、実感も出来る。けれど、誠史はどこで自分
のことをそう思うようになったのか、振り返ってみると分からなくなるのだ。誠史の「好き」
と自分の「好き」を天秤に掛けたら、自分の方が重いんじゃないか。そんなことすら頭を
よぎり、浮かれていた自分の心に自ら水を注してしまった。
「綾真君?」
誠史は部屋を暖め、キッチンからコーヒーを運んで来た。綾真は、珍しく誠史さんが働い
ていると、その姿を眺めた。
ローテーブルの上に置かれたコーヒー見つめていると、隣に誠史が座った。ソファが沈んで
身体が僅かに傾く。綾真はバランスを取ろうと身体を起こして誠史との距離を開けた。
「ひょっとして警戒してる?」
誠史は自ら淹れたコーヒーを口に運んだ。全ての行動が余裕に見えて悔しくなる。
綾真は掌を無駄に動かしながら誠史を見上げた。
「誠史さんは……」
「なあに?」
「誠史さんは本当に、お、俺の事、本気で好きなんですよね?」
思い詰めた末のその質問に誠史は呆気にとられていた。
「綾真君はこの後に及んで、まだそんなこと言ってんの?」
「……」
「やっぱり男同士の恋愛って抵抗あるか……」
俺だって信じられないけどね、と誠史は付け足す。綾真自身それについては超えなくては
ならない問題が山積みなことは承知してるけれど、自分の中では吹っ切ったつもりだ。
「そう言う意味じゃなくて……。そりゃあ抵抗がないわけじゃないですけど、そこはもう
自分の中で踏ん切りがついたというか……」
「煮え切らない答えだなあ」
「なんで俺なんですか?誠史さん、俺に初めて告白してきたときって、俺、そんなに親し
くなかったし……」
誠史は自分の言いたいことを理解してくれたようで、ふっと息を抜いて、綾真に向き合った。
「そう。そうだね。正直言えば、初めて君に告白した時は、綾真君をどうにかしたいとか
自分のモノにしたいとか、そういう激しい欲求は少なかったと思うよ。美味しいものを食
べさせてくれて、胃袋掴まれたなあって。分かる?胃袋掴まれた男は弱いよ?」
「そうなんですか?」
「そりゃあ、食欲なんて人間の本能なわけだからね。しかも生死のかかった本能。そこを
抑えられたら、男なんて一たまりもないさ」
「考えたこともなかったです」
「そりゃあ、君は自分で料理するから。でもキッチンにまともに立ったこともない男から
すればそこはでかいね。……だからさ、あの頃は君の料理を食べられるだけで満足してた
んだよ。本来なら告白するつもりもなかったし」
「え?!」
「君が可愛くて、うっかり口が滑った。まあ、嘘じゃないし、言っちゃったもんは仕方
ない。そうなれば、落とすまでのことかなって思った」
綾真は唖然として誠史の言葉を聞いた。誠史はそんな軽い気持ちで自分のことを好きと
言ってきたのか。悩んで悩んだ末に出したこの気持ちが重すぎて不釣合に感じてしまう。
「うっかりって……!それに、そんなに好きじゃなかったってこと?」
「確かに、初めはそんな気持ちだったよ」」
「それで俺は振り回されたんですか」
怒りすら湧き上がりそうになる。自分ひとりが踊らされてバカみたいだ。さあっと感情が
ひきかけて、綾真は拳が震えた。綾真の表情が曇っても誠史は慌てることなく、暢気に答え
を返した。
「振り回したかなあ。愛情をたっぷり注いでただけだなんだけど」
「そ、そういうセリフが白々しく聞こえるんです!そんなに大して好きでもないのに、俺
のこと振り回すなんて、ひどいです!」
綾真が悲しくなりながら訴えると、誠史は珍しく真顔になって綾真を見下ろした。
「だから、それは最初の頃の話だって。でも、今は違う。君を知れば知るほど、綾真君が
欲しい」
「!!」
「欲しいってわかる?君を抱きたい。全部自分のものにしたい。そう言う意味で、君が
欲しい」
「誠史さん……」
誠史はゆっくりと綾真の頬に手を伸ばした。大きな手が綾真の顔を優しく撫でる。
「もう遠慮はしないから。好きだよ、君が。愛してる」
誠史の顔が近づいてきて、誠史の息が頬を掠めた。
「最初から、誠史さんは遠慮なんてしてなかったじゃないですか」
綾真は泣きたい気分だった。初めてまともに会話したときから、サイオンジガーデンでの
食事と告白、風邪を看病したり、鍋会をしたり、距離が近づく度、自分の気持ちが揺れて、
否定していたのに、否定しきれないほど惹かれていった。
それはいつも誠史が遠慮なく愛情を降り注いできたからだなのだろう。世間体や、自分の
中でのモラルで、自分と同性の人間など恋愛対象になどならないと決め付けてきたのに、
凝り固まった器の中に愛情が少しずつ満ちていくのは嫌ではなかった。押しが強すぎて否定
していたけれど、綾真は嬉しかったのだ。
鼻をぐすっとさせると綾真は近距離で誠史を見上げた。
「もう、遠慮、しなくていいです……」
誠史の唇が近づいてきて、無遠慮とは程遠い優しいキスが注がれた。
ちゅっちゅっと小さな音を立てて綾真の下唇を啄むと、綾真はくすぐったそうに口を開いた。
誠史は綾真の中にコーヒーの香りを運んでくる。綾真は誠史の腕に手を伸ばすと、シャツ
の袖を握り締めた。緊張で震えそうな身体を誠史はゆっくりと撫でてくれた。
恋愛経験がないわけではないし過去に何度か経験はあるが、こんな風にリードされながら
キスをされたことのない綾真は、自分の立場に戸惑った。
「こういうの、嫌?」
息の隙間で誠史が尋ねる。綾真ははにかんだ。
「嫌っていうか……どうしていいのか勝手がわからなくて……」
「じゃあ全部俺に任せて」
言われる言葉がくすぐったい。けれど、任せてというのなら全て委ねてしまおうと思える。
それが自分の気持ちの証なのだから。
綾真は強ばる身体を誠史の方へと預けた。髪をとかす誠史の手が心地よくて綾真の肩の力
が抜けていく。
再び誠史の唇が近づくと、今度は自分からそれを受け入れた。軽く開いた口に誠史の舌が
滑り込んでくる。綾真の口内を優しく撫で、綾真の舌と絡んだ。
誠史の舌先は器用に綾真の舌の上を滑り、上あごを伝った。
「んんっ」
敏感な部分を掠っていく所為か、綾真はぴくりぴくりと身体を揺らし、口の隙間から声が
漏れた。その反応が可愛くて、誠史はわざとらしく敏感な部分を刺激した。
そろり、舌の裏側を伝い、逃げようとする綾真の舌を絡めて吸い上げる。誠史の唾液が綾真
の中に流れ込んできて、綾真は苦しくなった。
「!!」
綾真の腕が誠史の顔を引き離そうともがく。その腕を封じ込めて誠史は深いキスを続けた。
「んん!!んんっ」
綾真の目尻に涙が溜まり始めると、誠史は漸く唇を離した。
離れていく誠史と綾真の唇には銀色の糸が伸び、ぽちゃりとソファに落ちた。
「せっ……誠史さんっ!!」
綾真は瞳を瞬かせ誠史を睨んだ。けれど真っ赤になった頬と潤んだ瞳では今の誠史には逆
効果で、うっとりと腰を引き寄せられた。
「ホント予想通りなんだから」
「あなたは意地悪だ……」
「でも好きなんでしょ?」
「き、嫌いですっ」
子供じみた切り返ししか出来ない自分が恨めしくなるが、そんな態度ですら誠史は楽しい
らしく、腰に回した手で脇腹をゆるゆるとさすりながら笑った。
「これで可愛いっていったら今度はなんて答えてくれるんだろうね」
「誠史さんは目か脳の検査受けたほうがいいです!」
「俺の視力は両目とも1.2だよ。まあ、君の滲み出る可愛さは機械でなんて測れないと
思うけど」
誠史はしれっと恥ずかしいことを織り交ぜてきて、言われるほど身体中が熱くなる。耳の
先がジンジンして少しでも触られたら飛び跳ねてしまいそうなほど敏感になっていた。
「もう、やめて……」
綾真は脇腹を上下する誠史の手から逃げようと身体をくねらせる。誠史は当然それを追い
かけて、綾真はソファの上に倒れ込んだ。
真上に誠史の顔を見つけて、また胸がぎゅうと跳ねた。
「やだね。まだ始まったばっかりなのに。やめないよ」
誠史は子どもっぽい顔でニヤっと笑う。さっきまで脇腹の感触を楽しんでいた手は今度は
綾真の髪の毛を弄り始めた。さらさらとした髪の感触を楽しみ、やがてその手は頬を撫で
指先が耳を掠めた。
その途端、綾真の身体がびくりと揺れた。
「耳、やっぱり弱いんだ」
弱点を見つけた誠史は嬉しそうに顔を近づけて、綾真の耳に舌を這わせた。
「あっ!」
びりっとしたしびれが耳から身体中に行き渡り綾真の口からは声が漏れた。自分の声に驚き
恥ずかしそうに目を伏せる顔が誠史を更に煽った。
「やばいなあ、君にはまりすぎだ……」
「誠史さん?」
誠史は再び綾真の唇に近づく。見慣れない角度から見上げる誠史は雄の香りが漂っていた。
――>>next
よろしければ、ご感想お聞かせ下さい
nakattakotonishitekudasai ©2006-2010 kaoruko since2006/09/13