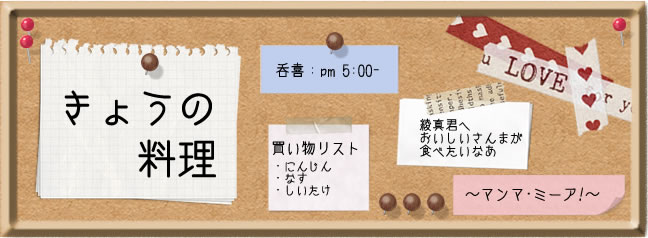
レシピ6:包んで包んで包まれて!あなたと蕩ける懐かしデザート―前編
腑抜けた日曜日を過ごした後で、月曜日になっても絶賛腑抜け中は続いていた。
父親の10回忌を親族と共にし、誠史と過ごした週末。密度の濃い土曜日を終え、くすぐっ
たすぎる日曜日の朝を誠史と共に迎えた。
誠史は紳士的に振る舞い、綾真はその誠意に甘えた。冗談交じりに色の付いた話を振って
くるくせに、絶対超えてこない一線を綾真に見えるように敷いてくれたのは、誠史にまだ
余裕があるからなのだろう。綾真は自分が踊らされているようなむず痒い気分を味わいつつも
誠史の大人な部分に頼ってしまった。
そして帰宅すると同時にもぬけの殻となってしまったのだ。
「溜息の数、数えたろか」
隣に座った美浦に指摘されて綾真は我に返った。休憩時間の教室は、親しいグループが
集まっておしゃべりに花を咲かせている。
教室が雑談で溢れる中、一人呆けていた綾真は、美浦に指摘されるまで、自分がどれだけ
溜息ばかり吐いていたのか、まるで覚えていなかった。
「俺そんなに溜息吐いてた?」
「サブイボ立つ位には」
「そう」
「なんだ?まさかの恋のお悩みか」
「……」
半分図星を付かれたような気分で綾真は美浦を見上げた。恋ではない。それは断言できる。
ただ、このぼんやりと揺れ動く気持ちが自分でもなんなのか分からないのだ。
「……恋じゃないけど、自分の気持ちが分からない」
ぼそりと綾真が呟くと、美浦は噴出して笑った。
「女子中学生みたいな台詞やな。そういうのって、気づいたときにはもう手遅れって言う
んじゃない?」
「だから、恋にはならないって。絶対に」
流石にそれはないと思う。自分が男相手に恋愛感情を持つなんて考えられないし、誠史と
キスしたり、それ以上の事など想像だってできなかった。
けれどありえない、ありえないと否定する一方で誠史と一緒にいる空間が心地よく感じ
られたり、この人の為においしい料理を作ってみたいと思うのは一体何なのだろうと、綾真
は分からなくなってしまっていた。
「恋に絶対はないって、あそこのお肌ツヤツヤ姐さん方が言ってますぜ?」
美浦が顎で差す方向にはクラスメイトの仲のよい女子がいた。
彼女達は週末、彼に作ってあげたスイーツの話で盛り上がっている。
「……あんたこそ、この前言ってたチョコ好き男どうなったのよ」
「ふふん!昨日、テンパリングを見せてあげたらさ、食いつく食いつく!」
「入れ食い状態?」
「やだあ、下品!」
女子の間からガサツな笑いが起きた。
「あんた、テンパリング上手いもんね」
「落としちゃったんじゃない、これは」
テンパリングとはチョコレートを湯せんで溶かし、滑らかな状態にすることで、上手く
テンパリングできたチョコレートはツヤがあり口解けのよいものとなるのだが、守らな
くてはならない手順が沢山あり、製菓初心者にはやや難のあるものだ。
しかし、綾真のクラスである調理師専門学校本科生は、製菓も必須で、基礎中の基礎である
テンパリングで転んでいるようでは試験も通らないという出来て当たり前のものだった。
綾真は半分呆れた顔で美浦に呟く。自分にはない輝きがそこにはあって、綾真は何故彼女達
と同じ空間にいるのか不思議に思ってしまうほどだった。
「ツヤツヤ姐さんって誰だよ。テカテカの間違いじゃないか」
「そりゃあ自称恋愛の上級者達だから……」
美浦が言い終わらないうちに女子集団が目ざとく二人を振り返った。
「ちょっと!聞こえてるわよ綾真君」
「失礼ね、盗み聞きなんて」
「ごめんごめん。綾真が人生の選択で悩んでて、是非お姐さん方の話を参考にしたいんだっ
てさ」
綾真が謝るより先に美浦が口を出すと、女子集団は一斉に食いついてきた。
「きゃあ。綾真君何悩んでるの?」
「コイバナ?聞きたい!」
「綾真君の相手、誰?このクラス?」
「違うって!別に悩んでもないから!ほら、美浦が変な事言うから……」
暴走する女子集団を綾真は抑えようとするが、美浦の援護射撃に綾真は打ち砕かれた。
「『恋になりそうな予感、後ろにハートマーク』なんだってさ」
「ばっ!馬鹿!何言ってんだよ、美浦!!」
「きゃあ。綾真君甘い。楽しい!」
「だから違うって」
「いいのいいの。綾真君って凄くいい人っぽいけど、真面目だから全然そういう話出て
来なかったじゃない?ありだよ。うん」
「あたし達、全力で応援するから」
女子軍団に囲まれて綾真はげっそりした。ただ人のゴシップを聞きたいだけじゃないかと
突っ込みを入れようかと思ったが、その気力すらも奪われてしまった。
こんな宙ぶらりんな気持ちは誰にも覗かれたくない。この気持ちに名前など付けられたく
ないし、誠史との関係もどうにもなりたくないのだ。
今のままがいい。からかわれているのは多少我慢すれば流せる。リップサービスもスキン
シップも他の人より若干多いと思えば済むことだ。大体誠史が本気で自分の事を好きな
はずがない。綾真はそう思い込み、これ以上の話をぶった切りにした。
「心配ありがとう。それよりも次の授業、レポート提出だけど大丈夫?」
「あ!やば!忘れてた!」
「やだ、あんたやってないの?」
「うん。なんだっけ?」
「学校給食のありかたについてだよ」
「やる!今からやる!」
女子生徒の一人が集団から脱落したところで、綾真のコイバナもそこで終了となった。
綾真は再び溜息を吐いた。
日曜の朝焼けを眺めながら誠史は綾真の淹れたコーヒーをおいしそうに口にした。
「いいね、こういう朝も」
「はい?」
誠史は振り返ると、ソファに座る綾真の隣に近づいた。
「なんだかさ、愛が深まった気がしない?」
ニヤニヤした顔で覗き込む誠史に綾真は口にしていたコーヒーを噴出しそうになった。
「全然しません!」
「そうかなあ。こうやって、綾真君の入れてくれたコーヒーを日曜日の朝から頂けるなんて
普通じゃ考えられないじゃない。俺、あんまり覚えてないけど、実は何かあった?」
「あるわけないじゃないですか!何言ってるんです」
綾真が真っ赤になって反論を始めると、誠史はニヤけた顔を逸らしてまた窓の外を見てし
まった。
暖簾になんとやらで、綾真の反論などするりと通過してしまう。全くつかみどころのない
男に朝から心を振り回されて、綾真は心が落ち着く時間がなかった。早く家に帰って自分の
ベッドでもう一度眠りたい、その一心で綾真は誠史の家を抜け出した。
「じゃあ、また明日」
「へ?」
「お店いるでしょ?」
「……いますけど」
どの面下げてこの男は明日も来るんだと突っ込みたい気持ちは山々だったが、綾真は全て
飲み込んで誠史の家を出たのだ。
マンションを出るとすっかり日はのぼり、街中は観光客でごった返していた。
「……君」
「……」
「綾真君」
「……」
「おーい、綾真君。戻っておいで」
「誠史さん!?」
たった今、思い出の中で動いていた人物から声を掛けられて、綾真はにわかに動揺した。
「あ、い、いらっしゃいませ……」
腑抜けた月曜日はバイトの時間になっても続いていて、一つ仕事をしては、誠史との週末
を思い出し、自分の心がどこに向かっているのか袋小路に追いやって自滅しているのだ。
「どーしちゃったの、ぽやっとして」
自分の手が動いてないことを覗き込まれて、誠史にニヤっと笑われた。この、人をからかう
視線が昨日の続きのようで、綾真は何故か心が苦しくなる。切り替えろと心の中で唱えて
綾真は料理人の顔を作った。
「……別になんでもないです。すみません」
「ふうん?」
誠史の痛い視線を無視して、慌てて作業に戻ると、誠史は追い討ちを掛けるように言った。
「週末にいいことでもあったんじゃないの?」
「あ、あ、ありません!」
ムキになって否定すると誠史はおかしそうに笑った。事情を知る誠史には綾真の心の内が
手に取るようにわかるのだろう。
「あやしいなあ」
自分の口から何を言わせたいのか、綾真は動揺する心の中から当たり障りのない話題を
一生懸命選び出した。
「昼間に学校のみんなで話してたことを思い出してたんです!」
「どんなこと?」
「小学校の頃、給食に出たデザートの話です」
「へえ」
授業で提出させられたレポートの話から、今日の昼休憩は給食の話題で盛り上がっていた。
「給食って時々凄いデザートでませんでした?俺、小さい頃あんまりオシャレなオヤツって
食べたことなかったので、ブラマンジェって初めて給食のデザートで食べたんですよ。初めて
食べたときのあの感動と言ったら……旨すぎて無言になって食べきりました。……それから
伯父さんに作ってって強請ったんですよ」
そういうと、隣で調理していた高森も懐かしそうに頷いた。
「あれは、参ったね。俺なんて料理人っていっても和食一本なわけだし、あの頃、そんな
洋風のデザートなんて作ったこともなかったから。でも、料理人の意地が絶対に出来ない
なんて言いたくないんだよ」
その言葉に綾真が笑った。
「今なら伯父さんの気持ち分かるなあ。……でも、おじさん、ちゃんと作ってくれたんですよ」
「最初プリンみたいなものかと思って、プリンなら簡単だとか思ってたら、蒸すんじゃ
なかったんだよ。茶碗蒸しならテリトリーだから、いけるかと思ったんだけどなあ」
その後、洋菓子専門の友人にレシピを貰い、無事綾真の前にブラマンジェが出てきたのだが
あの体験は高森にとっても、プラスの産物となった。新しいものへのチャレンジが今の店
を支える根幹となっているのだ。
懐かしい思い出のやり取りに誠史の顔もほころんだ。
「好きだったデザートは圧倒的にブラマンジェだったんですけど、最悪に不味かったって
いうデザートもあったんですよ。柿ゼリーって言って、一度しか出たことないのに、強烈
な不味さで未だに結構な人が覚えてるっていう超失敗デザート。給食であんなもの出して
いいのかってみんなの語り草ですよ。誠史さんはどうでした?」
話を振られて誠史はかすかに眉を顰めた。
「昔の記憶って殆ど覚えてないんだよね。まあ、覚えてる給食のデザートっていえば、冷たい
クレープかなあ」
「何ですか、それ」
「あれ?綾真君達の学校にはなかった?…うーん、なんていうかな、形は丸いクレープを
半分に折ってある半月形でさ、中にアイスでもない、冷たいクリームみたいなのが挟んで
あって、半解凍の状態で配られるんだよ」
「へえ!おいしそうですね。クリームってどんなんだろう。どんなのか分かります?」
「食べれば、ああこれだって言えるんだけど……」
曖昧な答えに、綾真の料理人魂に火がついてしまった。その味を再現してみたいと、思いつく
限りの食材を並べてみる。
「フローズンヨーグルトみたいなものです?」
「ああ、近いね。でももうちょっと甘かったかなあ。もたっとした食感だったような」
「じゃあ……クリームチーズとかかなあ」
「クリームチーズを冷凍するとあんな感じになるか、俺には分からないな。でもレモン
っぽいというか、ちょっと酸味のある味がした気もする」
「うーん。ちょっと探してみます、レシピ。見つかったら作ってみてもいいですか?」
「俺に食べさせてくれるの?」
「はい」
嬉しそうに笑う綾真に、誠史はまだまだだなあと口を押さえた。綾真はカウンター越しが
一番活き活きしている。絶対的な聖域。自分が踏み込めない境界線の中では、安心して
笑っていられるのだろう。
誠史は大して焦る様子もなく、綾真を見詰めた。
「な、何ですか」
「楽しみにしてるよ。懐かしいデザートに廻り合えるのを」
「頑張りますよ」
綾真の心はすっかり安定を取り戻し、もやもやしていた気持ちは袋小路に置き去りにして
もう手の届かないところに行ってしまった。
今はこれでいいのだ。どうにも立ち行かなくなったら、そのときに振り向いて考えれば
いいのだと、綾真は思うことにして、包丁を握った。
――>>next
よろしければ、ご感想お聞かせ下さい
nakattakotonishitekudasai ©2006-2010 kaoruko since2006/09/13