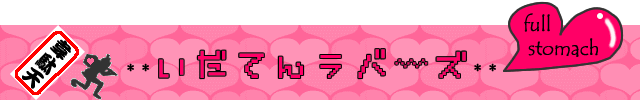
「動け!このデブ!」
ダーーーン。
体育館の床に叩きつけられたバスケットボールは激しい音を響き渡らせて、高城亜希
(たかしろ あき)の足元へと転がっていった。
タンタンタン・・・・・・ボールが軽やかに弾んで、亜希の丸い足に当たって跳ね返る。亜希は
重そうな身体を曲げてボールを拾おうと手を伸ばしたけれど、身体がつかえてしまった。
(ああ、ボールがいっちゃう・・・・・・)
亜希にぶつかったボールはコートの隅へと逃げていく。
けれど、踏み出そうという意思はすぐに薄れて、自分の足元から離れていくボールを目
で追っただけになった。
「いい加減にしろよ、高城!邪魔なんだよ!もたもたすんじゃねえよ!」
相手はその態度が益々気に食わないようで、亜希の75キロの丸々とした身体に向かって再び
罵声を飛ばした。
5月の清々しい風が体育館をすうっと通り抜けていく。開け放たれた入り口からは柔らかい
日差しが降り注いでいるのに、その場の空気は一瞬にして凍り付いて、真冬の嵐のような
冷たさすら感じる。
クラスメイトは動きを止め、一斉に声の持ち主を振り返っていた。怒鳴り付けているのは、
同じクラスの真野慧一(まの けいいち)で、その顔は怒りで目が釣り上がっていた。
つい数秒前まで体育の授業でバスケのゲームが行われていたのだが、真野の一言で中断
してしまっている。180センチを超える巨体は、今にも亜希の胸倉を掴みそうに掛かりそう
な勢いだった。
「ご、ごめっ・・・・・・」
突然の事で、亜希は激しく動揺した。
確かにこの身体――165センチに75キロ――では、バスケの授業なんて足手まといになる
こと間違いなしで、そんなことは亜希自身十分自覚していたけれど、いきなりこんな風に
怒鳴られるなんて思ってもみなかった。
なるべく邪魔にならないように、隅の方へと逃げていたのに、さっきから自分の行く方
行く方へとボールが飛んできて、その度亜希はボールをアウトにしてしまっていたのだ。
真野は亜希と転がって行ったボールを交互に見ると、イライラが収まらないのか、勝手に
コートから出てしまった。
「やってらんねえよ」
「高城、気にすんなって・・・・・・あいつバスケ部でエースだからさ」
「・・・・・・」
同じコートに入っていたクラスメイトがその場を取り繕うように慰めたが、亜希の心には
真野の後姿以外何も写らなかった。
超が付くほど苦痛の体育の授業が終わって、幸せのひと時、お昼ご飯タイムを自分の机で
過ごしていると、隣に座っていた女の子集団に亜希は声を掛けられた。
女の子達はグループになって、昼食をとっている。亜希なんかきっと3口くらいで食べ
終わってしまいそうな小さなお弁当箱を開いて、べらべらと楽しそうに、どうでもよさそう
な事をしゃべっていた。
亜希はさして気にも留めず、母の作ったお弁当を高速で食べ終わると、幼馴染の親が経営
するケーキ屋「ムーンウッド」の特製バームクーヘンを旨そうに食べていた。
「ねえねえ、高城君!」
声を掛けてきたのは5月の席替えで隣になった田中敦子だ。高校に入学して1ヶ月と少し、
自分のこの体形を敬遠してるのか、亜希は殆ど女子に話しかけられたことが無い。デブで
暗いなんて洒落にならないと、友達はたくさん作ろうとクラスメイトの男友達は出来たけれど、
目立つような存在ではなかった。
「高城君ってば!」
敦子はあんまり遠慮しない態度で亜希に話しかけてくる。一緒に昼食をとっていた女子も
興味深そうに亜希を見ていた。
亜希は慌ててバームクーヘンをイチゴミルク味のジュースで飲み込むと、彼女達を振り
返った。
「・・・・・・何?」
「この前、隣の席になってからずっと思ってたんだけどさー、高城君の食べてるバームクーヘン
って『ムーンウッド』のなの?」
敦子は亜希の机の上で丸まっているムーンウッドの紙袋を指さした。
「うん。ムーンウッド知ってるの?」
「やっぱりー。知ってる知ってる!あそこのケーキおいしいよね」
敦子は亜希というより、他の女子に同意を求めるように、おいしいを連発した。
亜希はムーンウッドが褒められたことが嬉しくて、いつもよりちょっとテンションの高い
声で頷いた。
「うん、無茶旨い。でも、焼き菓子も旨いよ。あ、あとちょっと残ってるけど食べる?」
「うわー、ホント?いいの!」
「あ、でも、これ、バームクーヘンの一番端の部分なんだけど・・・・・・いい?」
亜希は紙袋からバームクーヘンの切れ端を出すと敦子達に渡した。
「ありがとー!」
「何で切れ端〜」
ギャハハと声を上げて、敦子達は遠慮なく手を伸ばす。
「でも、高城君いつも切れ端食べてるよね」
女の子のキャッキャした声に囲まれて、亜希は得意げになって言った。
「俺ん家、ムーンウッドの隣なの。幼馴染のよしみで、切れ端部分をタダでくれるんだよね」
「いいなー!羨ましい!!」
「あたしもケーキ屋の幼馴染欲しい〜」
「また今度もらってきたら、分けてあげるよ」
「やったー!」
敦子たちは嬉しそうにバームクーヘンの切れ端を食べた。
食べてる間に、亜希は敦子たちとムーンウッドだけでなく周辺のケーキ屋の話で盛り
上がっていた。
「・・・・・・高城君って、結構話しかけやすい人だったんだね」
食べ終わると、別の女子にそう言われた。
「だから言ったでしょ?高城君って絶対面白い人だって思ってたんだもん」
敦子が自分の直感に満足そうに頷く。
「俺、面白いか?」
「うん!だって、甘いものをあんなに幸せそうに食べてる高校生男子なんて、可愛すぎる!」
半分馬鹿にされてるような気がするけれど、女子に囲まれて満更じゃない亜希は、照れた
笑いを浮かべた。
「人は見かけによらないのよねー」
「ホントだよ・・・・・・」
敦子が感慨深そうに呟くと、周りの女子はうんうんと頷いた。
「?」
亜希は(自分ではあるつもりだけど)殆ど無い首をかしげて、敦子を見る。
「そう思わない?だって、あんなカッコいい真野君は、あんなに性格悪いし〜」
真野の名前が出て、亜希は急に顔の表情を曇らせた。
先ほどの体育の授業の風景を敦子たちも見ていたのだそうだ。
「びっくりだったのよ。いきなり真野君の叫び声が響くから」
「俺もびびった・・・・・・」
「でもね、真野君性格きついってもう結構有名になってるらしいよ」
「そうなん?」
「真野君って入学早々バスケ部のエースって言われててね、実際練習試合でも大活躍してる
みたいなんだ。それで、女子バスケ部がファンクラブ状態になっちゃったんだけど、それを
見て『バスケに興味ないやつは体育館来るな』って一蹴したらしいよ」
「そうそう。3年の先輩に告白されて『趣味じゃない』って断ったとかねー」
「えー、あたしは『不細工帰れ』って言ったって聞いたよ」
女子の噂は怖い。どこまでが真実か分かったもんじゃないけど、少なくとも亜希に対して
怒鳴りつけたことは本当だし、お世辞にも優しい性格ではないのだろうと亜希は思った。
同じクラスになっても殆どしゃべったことは無いし、体育の授業で同じチームにならな
かったら1年間しゃべることもなかっただろう。それくらい自分と真野はかけ離れている。
性格も趣味も、何一つ接点はないし、真野とは人種が違うんだと亜希は思った。
「だからさー、真野君のことなんて高城君も気にすること無いよ。今時、顔がいいだけじゃ
モテないって!」
敦子はそう言ったけれど、周りの女子は苦笑いした。亜希もため息を吐いて、むっちりと
した腕に頬を乗せる。
「でも、カッコいいよ、真野って・・・・・・」
「高城君認めちゃうんだ」
「そりゃあ男から見たってアイツ、カッコいいよ。背高いし、顔いいし。スポーツだって
万能なんて、卑怯なくらいカッコいいだろ。女の子達だって、カッコいいって思ってる
でしょ?・・・・・・ムカつくけど」
「ムカつく?男の嫉妬はもてないよー?」
「違うよ。見た目カッコいいヤツにひどいこと言われると、なんかダメージでかくない?
カッコいいからきっと性格もよくて、優しいんだって勝手に勘違いしてたりするとさー」
ぶすっとして亜希が呟くと、女子が爆笑した。
「ぶはは、高城君いい!」
「でしょ!絶対面白いって思ってたんだ。だって名前から言って可愛いもん」
敦子が亜希に同意するように顔を向ける。
「高城君て名前なんて言うの」
「亜希だけど・・・」
「亜希ちゃん!可愛い!」
女の子達は、可愛いを連発して手を叩いた。何でもかんでも可愛い可愛い言う女の子達に
亜希も少し引いてしまいそうになる。
「俺、生まれる瞬間まで女の子だって言われてたらしくてさ、名前も服も全部女物。名前
くらい考え直せよって話だろ?」
「お母さん、名前変えなかったの?」
「女だって思い込んで、現実と俺の股間を直視出来なかったんだ」
また笑いが起きる。すっかりガールズトークの中に溶け込んでいる亜希は、5月半ばにして
クラスメイトの女子の間で「実は面白ろ可愛いデブ」と認識されるようになった。
「動くな!このデブ!邪魔なんだよ!ボールの行く方向へ動くな!」
今日も体育館に真野の声が響いた。ダンダンダン・・・・・・ボールがコートの外へと転がる。
「ごめん・・・」
亜希はぼそりと呟くと、真野と目を合わせないようにボールを拾いに行った。そこでまた
真野の怒鳴り声が亜希の背中を直撃する。
「走ってとって来い、このデブ!」
流石に真野の暴言を周りの生徒も眉をしかめ、チームメイトが真野の態度を諌めようと口
を出した。
「ちょっと真野、止めろよ。言いすぎだって・・・」
「うるせえな、アイツ見てるとイライラすんだよ。白くて丸くて甘ったるくて」
真野は同じチームになっている生徒をギロと睨み返す。見下ろされた生徒も、そこまで強く
言えず、真野に押されて黙ってしまった。
嫌な沈黙がコートを支配した。
亜希は息を切らせながら、ボールを拾うと自分としては精一杯の速度で真野の元へとボール
を運んだ。
「はい・・・・・・ごめん」
「ったく、ホント邪魔。お前さ、どうせいるだけで邪魔なんだから、わざわざ授業出て来な
くていいだろ」
「なっ・・・・・・」
「出てたって出てなくたって、お前の評価なんて変わらないんだろ?」
真野は亜希を見下したように鼻で笑った。
「!!」
どうせデブは体育の成績なんて最低ランクに決まってると決め付けるその視線に、亜希は
段々と腹が立ってきた。
手にしたバスケットボールがわなわなと震える。
「ああん?なんだ、文句あんのかよ。本当の事だろ」
プチン、亜希の中で何かが切れた音がした。
「俺だって一生懸命やってんだよ!」
だん、とボールを床にぶつけると、自分よりも20センチ近く高い真野を睨み上げた。
「大体なんだよ!真野が俺のところにばっかりボール投げるのが悪いんだろっ!」
亜希の高い声に、クラス中が手を止めて二人を振り返っている。けれど、亜希はそんな
周囲の目などお構いなしに、今まで溜めていた鬱憤を全て吐き出した。
「お前はバスケ部でこんな授業タルイかもしれないけど、もうちょっと考えろよ!部活と
授業を一緒にすんな!俺だってがんばってんだ!」
真野は亜希の逆キレに一瞬怯んだものの、亜希の態度にまた腹を立てた。
「開き直ってんじゃねえよ、このデブ!」
こうして、ついにバトルが勃発した。
デブは苛められる運命にある、なんて思っていた一部の男子は亜希の反逆に大いに驚か
されたし、体育館反対側のコートからは、敦子達のように亜希と仲のいい女子が、ついに
やったかとにんまり笑った。
その後、2人は取っ組み合いになりそうになっていたところを体育の教師に止められ、
2人して怒られる羽目になった。
けれどお互い懲りてないのか、体育の授業でチームになる度、2人は衝突し合い、いつしか
2人の喧嘩はクラスの名物にまでなってしまっていた。
今では「また始まった」と呆れる男子と「やってるねー」とほほえましく笑ってる女子が
亜希と真野の喧嘩を慌てることなく見守っているくらいだ。
だけど、この2人の関係はじわじわと形を変え始めていることに、周りの人間はまだ気づいて
いない。
真野の亜希を見る視線の中に、時々揺れが生じてる、亜希の真野に対する嫌悪の中に
何故かうっとりした気持ちがあること・・・・・・。
「動け!デブ!」
「うるさい真野!」
とりあえず、今日も体育館に2人の声が元気に響いていた。
――>>next
よろしければ、ご感想お聞かせ下さい
nakattakotonishitekudasai ©2006-2010 kaoruko since2006/09/13