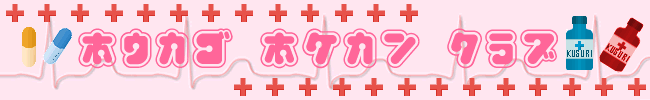
若いんだから、なんでもチャレンジすべきですよ・・・
「君の綺麗な桃尻を僕にも見せて?」
耳元で囁かれた声に煌成は目を見開いた。ここは一体何処だ。何でこんなことになってる?
・・・・・・前にもこんな状況になったことが・・・・・・あったような、なかったような・・・・・・
突然の展開に煌成は身を捩った。囁いている声は勿論聞いたことのあるあの声。保健の伊純だ。
「もっ、桃尻って!俺、違うしっ・・・・・・」
「そんなことないですよ。ほら、こんなにすべすべで・・・・・・」
煌成は尻を撫でられ、背中からぞわりと悪寒が走った。
「センセ、止めっ!!俺、無理だし!」
お尻の穴がきゅうっと引き締まって、煌成はブルブルと首を振る。この世に生まれ落ちて
17年。女の子のお尻を撫でたことはあっても、自分のお尻を撫でられた上に「桃尻」なんて
言われたことなどない。まじまじと見たことはなくとも、自分の尻が「桃」などと形容される
ような綺麗なものでないことくらい十分想像できる煌成は、撫で上げるその手を掴んで、
再び叫んだ。
「お、俺のケツが・・・・・・!」
焦る煌成に、伊純はニコリと笑って頷いた。
「大丈夫。君のココを狙ったりしませんから」
当たり前だと煌成は首を振りながら、伊純の手の中から逃れようとする。煌成の方が体格
もいいし、華奢に見える伊純なら簡単に逃げ出せそうなはずなのに、何度チャレンジしても
伊純の身体が重く圧し掛かって煌成は逃れられないでいた。
「それに、僕はこっちの方が好きだし」
「ひやぁっ」
お尻を撫でていた手はいつの間にやら股間に伸びていて、煌成の股を行ったり来たりして
いる。初めはくすぐったい感触だけだったはずなのに、段々と自分の股間が硬くなっていく
ことを煌成は悟ってしまった。
「先生っ、待って、止めて!!違うの!!」
「良いんですよ、気持ちいいって身体は正直に反応してるんだから」
「よくない!!」
「ほら、こんなになってる」
言われて視線を向けると、いつの間に脱がされたのか下半身は丸裸にされ、素手でペニス
を扱かれていた。
「はぁっ」
「気持ちいいでしょ?」
確かに気持ちはいい。自分で扱くよりも気持ちがいいのは何故なんだと煌成はぶっ飛んだ
思考でとろりとなった。
「もう大丈夫。出来るよ、海老原君なら」
何を根拠に、大丈夫なのかさっぱり分からないが、伊純に言われると納得してしまう。
そして、煌成もその気になっていった。
全てが歪でおかしいことを、どうして気づけないのだろう。冷静に頭の上から見ている
自分が存在していれば、容赦なく突っ込んでくる展開だ。
「俺、入れる方?」
「うん、そう。・・・・・・待ってて、今準備するから」
伊純は一度煌成の上から退くと、白衣を脱ぎ、パンツのベルトを外し始めた。その音を
聞きながら目を閉じると、見えてくる映像は「穢された桃尻」のパッケージ。
伊純がこちらを向きながら官能的な表情であられもない格好になって煌成を誘っている。
「うっ・・・」
ペニスの付け根が痛い。痛いほどカンカンに張り詰めて、その爆発を待っているようだった。
「海老原君、もういいですよ」
声を掛けられて、薄目を開くと、真っ白い肌の伊純が煌成の上に馬乗りになって、自分の
ペニスを煌成の腹に擦り付けているところだった。
伊純は身体を開いて、秘孔を煌成の尖ったペニスの上に乗せた。
「先生の中に入る!?」
驚きと興奮で煌成が口走ったのを、伊純は余裕たっぷりに頷いて、一気に身体を落とした。
「ああああああっ」
「ああああああっ!!!!」
気がつくと、煌成はベッドの上に寝転がっていた。
見覚えのある風景。煌々と天井の電気が部屋を照らしている。ここは間違いなく自分の
部屋で、自分は夢を見ていたのだと煌成は理解した。
「3回目って、流石にありえないだろ」
伊純と絡む夢を3度も見てしまった。それだけだってありえないのに、伊純がゲイだと知って
しまった直後にこんな夢を見るなんて、どういうことなのだと煌成は頭を抱えたくなる。
時計を見ればまだ9時前だった。
伊純の家から送り届けてもらい、夕食もそこそこに部屋に帰るなりベッドに倒れこんだ
のがついさっきの事。
伊純がゲイという事実は、気持ち悪いとかおかしいとかそういう感情を突き抜けて、ただ
ただ驚きだけが煌成の中を支配した。
短絡的に気持ち悪いと罵っていれば、この事態は別の方向に進んでいたかもしれない。
なのに、煌成は驚きと疲れからベッドに寝転がると直ぐに寝てしまい、そしてまたも
こんな夢を見てしまったのだ。
そして恐る恐る股間に手を伸ばすと、煌成は更に固まった。
「何で勃ってんだよ」
勃っていたペニスを握ると、意味も無く2、3度動かして停止する。それから急激に夢が
フラッシュバックしてきて、煌成はもう2、3度擦ってみた。
溜っていたのか、急激に性欲が沸きあがって来た。そのまま抜いてしまおうと、指を絡めて
動かし始めて、はっと気づいた。
「別のもの!」
夢なんか思い出して抜いたら、それこそ変態だ。
グラビアアイドルの水着、友人に借りたAV、お気に入りのエロ雑誌、好みの顔のAV女優を
思い浮かべながら、煌成は右手を動かした。
AV女優のお尻を撫でながらバックで突く。腰を振って肌がぶつかる度、女の桃尻がぷるん
と揺れて、腿に吸い付いていく様だ。その尻を撫でていると、掠れた喘ぎ声があがった。
随分とハスキーでセクシーな声・・・・・・
「ハスキー・・・・・・?」
妄想は止まらず、女優だったはずのお尻は、いつの間にか伊純に摩り替わっていて、煌成は
夢の続きをしていた。
「くそ、もういい!」
天頂は直ぐそこまできていて、早く出してしまいたかった煌成は、妄想の修正を簡単に
諦めてしまった。
伊純の桃尻に突っ込みながら喘ぐ伊純で頂点を極める。
「あっ・・・・・・」
右手が止まると、どろりとした液体が右手を濡らした。肩で息を整えながら、刺激臭で
煌成は我に返った。
「ど、どうしようっ・・・・・・先生で抜けた・・・・・・」
まさか本当に抜けるとは・・・・・・焦りと敗北感で煌成は虚脱した。
「だって、先生男だし!」
伊純がゲイでも自分は違う。男のケツに自分のを突っ込んだところを妄想して抜いたこと
など一度もなかった。そういう発想にすら達したことがなかったのに、なんであんなに綺麗
に抜けたんだろう。
ホモAV見て抜いてるのかと、ドン引きした伊純の事を詰れない状況になってしまった。
「夢の所為だ、こんな夢見たから・・・・・・」
だから思わず先生をオカズにして抜いてしまったのだと煌成は自分を無理矢理納得させたが
一度出来たら、明日も明後日も出来そうな気がして、その予感が煌成を震え上がらせた。
ゲイじゃないのに、男の身体に突き刺すところを想像して勃起した。ひょっとして、自分
もゲイなんだろうかと、煌成は不安に怯える。
けれど、これが例えばクラスメイトの袴田だったら?藤や井沢だったら?そうやって、
相手を選んで考えてみると、すぐに吐き気がして勃つどころの騒ぎではなかった。
どうして伊純だけは平気なのだろう。
伊純がゲイだと知って、見る目が変わってしまったからなのだろうか。
「あー、ヤダヤダ。忘れたい!」
そこにある感情に引っかかりながらも、煌成はそれ以上深追いするのが怖くて目を閉じた。
月曜日の朝は気だるく、いつもの貧血もあって煌成はローテンションのまま家を出た。
「煌成、いよいよ三角関係突入だって?」
登校すると、開口一番袴田がニヤニヤとした表情を浮かべて煌成の前に座った。
「はあ?」
勿論そんなものに覚えはない。どうせ井沢が流した噂の所為だろうと分かりきった顔で袴田
を見下ろすと、袴田はまだニヤニヤしていた。
「真桜ちゃんを巡って、保健委員内で愛のトライアングル発生中」
「マジでか」
他人事のように煌成は驚いた。
「藤って、あの超真面目な男だろ?何があったん?」
「・・・・・・語ることすらないほど、何にも無い」
「何だよそれ」
「大体、俺と真桜がもうそういう関係じゃないこと、お前は知ってるだろうが」
「そうだけどさー。面白そうじゃん」
「藤と真桜がくっ付いただけなんじゃないの?そんで井沢のヤツが、勝手に俺の名前も
混ぜて、噂をばら撒いてるってのがオチだろ」
「へえ、真桜ちゃんと藤はホントなのか。不釣合いっぽいのになあ」
「真桜が惚れてたんだ」
「マジ?」
「だって、俺に邪魔すんなって忠告してきた・・・・・・って結局三角関係とか噂流れたら、また
怒られるんじゃん!あー、ヤダヤダ」
煌成はローテンションで机に突っ伏して溜息を吐いた。貧血っぽいとは朝から気づいていた
けれど、処方された薬をついついおざなりにして、鞄の中に突っ込んだままになっている。
飲んだほうがいいのは分かっているけれど、血剤は副作用が強く、進んで飲みたいと思わせる
ものではなかった。
今回もそうやってギリギリまで逃げて逃げて、煌成は目の前がくらくらするまで逃げて
いたのだ。
そして案の定、3時間目が終わる頃、煌成は酷い眩暈で保健室に駆け込むことになった。
「・・・・・・失礼します」
伊純に会いたくないとかそんなレベルで嫌がっている場合ではなかった。
とにかくベッドで身体を休ませたくて、煌成は廊下をよろけながら保健室に向かった。
保健室は珍しくオバチャンがいて、他は1人怪我の手当てをしている生徒がいるだけだった。
「海老原君・・・・・・さては貧血ね?」
オバチャンは驚きもせず、煌成の顔色を見て頷いた。
「うん・・・」
「お薬持ってきた?」
「うん」
「じゃあ、白湯ね。飲んだらベッドに横になりなさい」
「うん、そうする」
「あんまり酷いようなら、病院いきなさいよ」
「へーい」
オバチャンはてきぱきと煌成のベッドの準備を済ませ、煌成の前に白湯を出した。
煌成は薬を飲むと、ベッド使用名簿に名前を書き入れて、いそいそとベッドに横になった。
目の前がグルグルと回っている気がする。けれどそれもいつしか消えて、煌成は眠りに
落ちていた。
桃の香りかと思ったけれど、それは間違いだったらしい。甘い匂いがしたと思って目を
開けると、伊純が心配そうに覗き込んでいるところだった。
「うわぁあ」
「・・・・・・っ」
煌成が驚いて大声を上げたので、伊純も身体を震わせて身を引いた。
「びっくりした」
「・・・のは、こっちの方です」
伊純は保健医の仮面を完全に被りきっているのか、昨日の事などまるで忘れたように煌成
の前に立っていた。
「貧血?」
「うん。胃腸が悪くて、貧血なんてかっこ悪い男の極み」
「そんなことはありません。格好悪いなら、他にもハゲとかデブとか色々種類もあるし」
「それ励まし?」
煌成は苦笑いして伊純を見上げる。
「そうですよ」
「高校生にハゲはありえねえってーの」
煌成が笑うと伊純ははにかんだ。
「・・・・・・傷心して寝込んでるのかと思った」
「は?」
伊純はパイプイスを持ってくると、ベッドに横たわったままの煌成の隣に座った。
「やっぱり違うみたいですね」
「傷心って何のことだよ」
煌成がもそもそと起き上がる。全く心当たりのないことを言われて、煌成の眉間に皺が
入った。伊純は少しバツが悪くなったのか、煌成の顔を正面から逸らし、小声で言った。
「藤君と塚元さんが・・・・・・」
伊純が言いかけたところで、煌成は頭を抱えた。
「ちょっと!先生、井沢に何か吹き込まれたん?」
「・・・・・・いえ、藤君と塚元さんが付き合いだしたって聞いただけです」
「だったら・・・・・・」
俺は関係ないだろと、煌成は言おうとして口が止まった。伊純との初めの接触を思い出した
のだ。保健室のベッドに(しかも今煌成が使ってるこのベッドだ)真桜を連れ込もうとして
いるところを、思いっきり見られた。あの現場を見れば、煌成と真桜が恋人同士か、もしくは
煌成が無理矢理連れ込んだかどちらかだと予測はつくだろう。どちらにしても煌成が真桜を
「狙っていた」と思われているには違いない。
伊純は自分達の関係を勘違いしている。自分と真桜と藤の関係を逐一説明して、訂正
するまでもないけれど、ホケカン倶楽部として活動していく以上、余計な気を使われるのも
面倒くさい。煌成は首を振った。
「先生さー、ひょっとして、俺が振られたとでも思ってる?」
「・・・・・・」
「まあ、外れてはないよ。先生が来るずっと前の話だけど」
「え?」
「女の子とやりたいだけでさ、元カノにそういうことしたらさー、先生軽蔑する?」
伊純は見詰められて、返答に詰まってしまった。
――>>next
よろしければ、ご感想お聞かせ下さい
nakattakotonishitekudasai ©2006-2010 kaoruko since2006/09/13