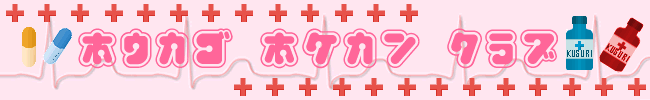
卵と鶏の問題みたいですね・・・
冷たくしていた理由は、好きだったから・・・・・・
伊純の謎はあっさりと解けてしまった。裏の顔を暴いてやろうと意気込んでいた煌成は
肩透かしどころか、肩パンチまで食らった。
そんな結末があっていいのだろうか。問いかけてみてもそれが事実なのだから、捻じ曲げ
ようとしても仕方はない。
冗談だと済ませたくなるが、口でイかされて、あんな顔で「ごっくん」されては、あれが
夢でない限り嘘だとはいえないだろう。
「海老原君の気持ちを強制して聞こうとは思ってないですから」
伊純はそう言って煌成から離れた。
答えを強制されなくても、あんなことがあれば、考えずにはいられないだろう。
自分はこれからどうなってしまうのだろう。いや、どうするべきか。伊純との関係は
もやもやと霧が掛かったまま、先の見えない道のようだ。
伊純が自分の事を好きなのは、百歩譲って真実だとしよう。
それを前提として、自分はどうなのか。流されたといえ、あそこまで許した自分は、一体
伊純をどう思っているのだろう。
煌成は目を閉じて今日の出来事を思い出していた。
告白されて、流されて、やってみたら出ちゃった、なんて強烈パンチ食らっても、煌成は
伊純に対して嫌悪感をもてなかった。
「おかしい・・・・・・」
どう考えてもおかしい。いや、おかしくなってしまったのか?
嫌じゃなかったという時点で、自分の気持ちがあやふやになっている。
「俺、ホモの素質あんの・・・?」
ただでさえ告白という強力なカウンター喰らってるのに、そんなトリプルパンチいらないと
煌成は首を振った。
釈然としない気分だけが煌成を包んでいた。
それから、煌成はひたすら悶々とした日々を過ごしていた。貧血や胃痛は相変わらずで
そうなると、煌成は保健室よりも早退を選んだ。
伊純に会わせる顔がない。会ってどんな顔をしていいのかさっぱり分からなくなって
しまったのだ。
休み時間、教室でいつものように突っ伏してると、前の席の袴田が覗き込んできた。
「お前大丈夫?」
「・・・・・・大丈夫に見える?」
「全然。何?貧血?胃痛?喘息?心臓発作?性病?あ、生理痛?それとも、恋の病?」
「アホか」
どれも当たってないが、恋の病の言葉に異常に心が反応した。
「煌成が病弱なのはデフォルトとしても、なんかお前おかしくね?早退早退で。あ、まさか
本当に早退して、女の子とイチャイチャしてんじゃねえよな?」
そうだとしたらなんて楽しい高校ライフなんだろう。
あの保健室の出来事が伊純じゃなくて可愛い女の子だったらどんなによかっただろうか。
煌成はまたあの場面を思い出して激しく溜息を吐いた。こんなに伊純の事ばかり考えて
しまうなんて、袴田の冗談でもないけれど、恋の病みたいだ。
・・・・・・恋の病。冗談じゃない。煌成はぶるぶるっと顔を振った。
伊純が自分を好きなのだ。自分が伊純を想うなんて・・・・・・ありえないだろう。
「なあ、袴田〜」
「何だよ」
「・・・・・・好きだから、やるんかな。それとも、やるとその人の事好きになるんか」
「ああ?!」
「あ、やっぱいい。今の聞かなかった事にして」
「何、何、何!!煌成が恋バナ!?」
「なんでもないって」
「なんだよ〜。恋の病じゃん」
「違うってーの。・・・・・・恋愛っつーか、下の話」
ぼそぼそと煌成が言うと、袴田はふふんと意味ありげに笑った。
「そりゃどっちもアリなんじゃないの?好きな子としたいって思うのは普通だと思うけど、
やったら情が沸くってーのも、あると思うし」
情か・・・・・・。
このモヤモヤした気持ちは情なのだろうか。
「俺は情が沸いたんだろうか・・・・・・」
「誰に?」
独り言はばっちり袴田に届いていて、袴田は乗り出してきた。
「別にっ」
「なんだよー。誰とやったんだよ、言えよな〜この羨ましい!顔のいいヤツはすぐ出来て
いいよなぁ」
「そんなんじゃねえよ・・・・・・」
生まれてこの方、顔がよくて得したことなど数える程しかない。周りがいくら騒ごうが
狙った女の子のゲット確率は極めて低いし、もてたくない人にばかりもてても全然嬉しく
もない。
袴田に言わせれば贅沢言ってんじゃないと怒られそうだが、煌成は自分の顔を武器と
して使おうと思うことは殆どなかった。
「そういえばさー、お前が早退ばっかり繰り返してる間に、伊純ちゃんの噂が流れてたの
知ってる?」
「噂?!」
まさか、伊純がゲイだとばれた・・?
自分は誰にも口外してないし、まさか、あの現場を誰かに見られていたのだろうか。
煌成は内心の動揺を悟られないように出来るだけゆっくりと袴田を見た。
「お、珍しく飛びつくねえ」
「飛びついてねえって。あんな仏頂面の先生にどんな噂が立つんだって思っただけ」
「仏頂面なのはお前にだけだろ。それに前にもイイ男っていう噂立ってただろ。まあその
善人ぽい噂が余計にダメージでかくしてるんだろうけど」
「・・・・・・もったいぶんなよ」
煌成が眉を顰めると、袴田は得意気になって言った。
「お前さ、先生の家に行ったとか言ってたじゃん?」
「ああ?・・・うん」
「あん時、なんかされなかった?」
「はあ!?」
思いの他、大きな声が出て周りの生徒までもが煌成を振り返った。
「・・・・・・やっぱり何かされちゃった?」
「何かって、何の話だよ?」
やっぱり保健室のあの一件を誰かに見られていたんだろうか・・・?
職員室に呼ばれて説教される自分の姿が情けなくなる。誰に怒られるんだろう。学年主任
生徒指導、どっちも強面で煌成の苦手な教師だ。
全てを伊純の所為にして逃げるのも気が引けた。流されたのは自分だけど、許したのも
自分なのだ。伊純と一緒に怒られて、一体どんな処分を下されるんだろう。
どぼんと落ちそうになっていたところに、袴田の話は別の衝撃を与えた。
「流石に、顔がいいからってお前まで餌食になったりしないよなあ」
「何の話だよ!」
「それがさあ・・・・・・一番初めの噂は、2年のクラスの男子生徒が伊純ちゃんにコクったって
いうのでさ」
「はい?!」
「まさかそんな展開で来ますかって思うよな〜」
「それ、ホントなんか?」
「さぁ・・・でも、発信源が井沢らしいし、信憑性は高いんじゃねえの」
「井沢が・・・・・・」
ハイエナみたいに恐ろしい男だ。ゲイの伊純に男子が告白なんて、ゲイにはゲイが集まって
来るのかと煌成は妙なところで感心した。
「でもさー、それだけじゃないんだよな」
「は?どういうこと」
袴田は、微妙に顔を歪ませてた。嫌悪とも卑下とも思える表情に煌成はチクンと胸が痛む。
煌成だって、全てのゲイに肯定的ではないし、普通に考えたらありえないと思うけれど、
伊純のことを否定されると自分まで胸が潰される気がした。
袴田はその表情を更に歪ませて言った。
「どうもさー、そのコクった男を、伊純ちゃんが食っちゃった・・・らしい」
「は?!」
煌成は思わず椅子を倒して立ち上がっていた。頬がぷるぷると震えている。握った拳に力
が入って、奥歯がキリキリと鳴った。奥の方から湧き上がってくるこの感情は一体何なのだ
ろうか。噂の域を過ぎない話に自分がこんなにも過剰に反応していることに、煌成自身恐ろしく
なった。
「煌成、驚きすぎ」
袴田に窘められて、煌成は慌てて椅子を直した。
「ちょっと、びびった・・・・・・」
「だよな〜。伊純ちゃんがモーホーの人だったとはなぁ・・・」
「う、うん・・・・・・」
煌成が驚いたのは勿論そこではない。自分はそのモーホーの人に食われた、言わば犠牲者
みたいなもんなのだから、もうそんな事実で驚きはしないのだが、もしその噂が本当だと
すれば、伊純の告白は一体なんだったのだろう。
自分の事を好きだと言ったくせに、簡単に他の男も食ってしまえる・・・・・・。
煌成は伊純の言葉を思い出して、声を上げた。
「あっ・・・」
「あ?」
怪訝そうな袴田を見て口を押さえる。
「いや、なんでもない」
「なんだよ、心当たりでもあんの?」
「ねえよ!」
伊純はやれるなら誰でもよかったといった煌成に、賛同してくれたのではなかっただろうか。
それと同じ事をしただけのことだ。伊純もそういう人種だったのだ。
別に自分とは関係ない。伊純が勝手に好きだと言ってきただけで、自分の気持ちは、一ミリ
だって向いていないはずだ。だから、伊純が誰とやろうと、誰を食おうと、一向に構わないのだ。
そう思う一方で、何故だか凄く傷つけられた気分になった。
言うならば、裏切られたような痛みだった。
「なんか煌成怒ってない?」
「はぁ?何で俺が怒ってなきゃいけないんだよ」
否定しようとした口調が厳しくなって、煌成は益々慌てた。
伊純に対してムカついている。けれど、根本的なところが見えていない煌成は上辺の気持ち
に翻弄されていた。
むしゃくしゃした気分で、煌成は再び机に突っ伏した。
「煌成〜?」
「やべぇ、ちょっとびっくりしたら胃痛がぶり返した」
「相変わらず繊細な胃だなあ」
袴田は妙に感心したように呟いた。
伊純の噂は思った以上に拡大もしくは誇張していった。
噂に疎い煌成の耳にもいくつか入ってきて、それを聞いては煌成は愕然としていた。
『男子生徒がコクった』
『コクった生徒を食った』
『実は伊純先生は真性のホモ』
『夜な夜な(というか昼間だ)保健室にやってきた生徒を片っ端から口説いている』
『口説いたあとは、保健室のベッドで美味しく戴いちゃっているらしい』
『伊純先生のテクは一級品』
『そのデカいブツで何人ものノーマルな生徒を天昇させた』
『白衣の下はいつでも戦闘態勢』
『下着は付けてない』
流石にここまで来ると、ありえないだろうとも思うのだが、否定する必要のある人物が伊純
一人だけでは、噂はどんどん膨らむ一方だった。
「どこまでがホントだと思う?」
「全部じゃねえの。最低なヤツ」
面白半分に聞いてくる袴田にも煌成は腹を立てていた。
「でもさー、あんな善人っぽい先生が本当にそんなことしてんのかなあ」
自分にされたことを考えれば十分ありえると煌成は思う。
「保健の先生だって、白衣脱げばただの男だろ」
「若い子がゴロゴロしてんだもんなー。そりゃあつまみ食いだってしたくなるか」
「職権乱用しすぎなんだよ」
煌成は荒んだ声を上げた。勝手にしろといいたくなる。
保健室であんなことをされて以来、煌成は保健室にも近づいてないし、伊純の顔だって
見ていない。伊純が今どんな気持ちでいるのかなんて、分かるはずもなかった。
そんな中、次に出て来た噂は出るべくして出て来たものだった。
「やべえよ、伊純先生懲戒免職だってよ」
「あ?」
「辞めさせられるんだよ」
「はぁ?!」
「やっぱりさー、授業中に生徒に手出しちゃったら拙いっしょ」
「マジで言ってんの?」
「職員会議に掛けられたって朝から噂になってんぜ?」
「でも、噂じゃなかったのかよ・・・?」
「だから、何個かは本当だったってことだろ」
伊純が辞める・・・・・・?
この学校から伊純がいなくなる。いなくなれば、もう二度と自分とは接点がなくなる
だろう。そうすれば、伊純とも会えなくなるのだ。
あれほど会いたくない、会わせる顔がないと思って逃げていたのに、こんな形で急に
いなくなるといわれて、煌成はいても立ってもいられなくなっていた。
「辞めるなんて、嘘だろ・・・」
胸が苦しい。自分が伊純をどう思っているのか、未だに答えは出ないけれど、好きだと
言って、あんな顔を見せた伊純に、もう二度と会えなくなると思うと、もどかしくて、耐え
られなくなった。
「ちょっと、3時間目、休むわ!」
そう言うと煌成は勢いよく立ち上がった。
「煌成!?」
背中で袴田のひっくり返った声が聞こえる。けれど、そんなのに振り返っている余裕は
なかった。
煌成はなりふり構わず保健室に走り出していた。
――>>next
よろしければ、ご感想お聞かせ下さい
nakattakotonishitekudasai ©2006-2010 kaoruko since2006/09/13