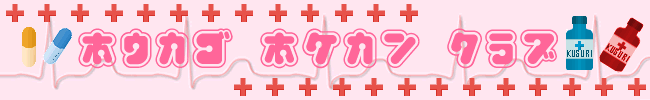
そういう意味では、本当に最低の出会いなわけで・・・
海老原煌成は、クラスで1、2を争うほど顔がいい。他校の女子に写真だけ見せたら、
誰もが口をそろえて「かっこいい」「イケメン」「彼氏にした〜い」と言う程だ。
顔の見た目も、身体の見た目も悪くない。なのに、海老原煌成はもてない。
それは、煌成の周りで次々と生まれる噂の所為だ。
『いつもサボって、保健室に女の子を連れ込んでいる」
『屋上でシンナーを吸っている』
『他校のヤンキーに絡まれて気を失った』
『やりすぎて、不能になった』
『初めてしたときも、極度の緊張でやっぱり不能になった』
と、まあ、かっこ悪い噂は尽きることは無い。
「お前さあ、ちょっとは否定したら?」
事情を知っている袴田は呆れているが、別に言いたいヤツは言わせておけばいいくらいに
しか思っていない煌成は、今更否定するのも面倒くさかったのだ。
「それに、あながち全部間違ってるわけじゃないし」
「いや、大分間違ってるだろ」
確かに煌成はサボって保健室にいるわけではない。直ぐに胃腸を壊すし、オマケに貧血
持ちで、保健室に駆け込まなくてはならない状況になってしまうだけだ。好きで保健室に
入り浸ってるわけではないのだが、見た目健康そうな煌成が何度も保健室を利用している
所為で、妙な噂が立ってしまったのだ。
女の子を連れ込んでいるあたりは、完全に背びれがついている。
「まあ、やりすぎて不能とかは、ありえんな」
ぼへーっと煌成が呟くと、袴田は他の噂も思い出して首を振った。
「っていうか、屋上でシンナーもないだろ」
「ああ、あれ・・・」
袴田達と昼食を屋上で食べていたときの事だ。一人遅れてきた煌成は、全力で屋上までの
階段を駆け上がった所為で過呼吸になってしまい、昼食の入っていたコンビニの袋を口に
当ててそれを吸ったのだ。
過呼吸の対処としては至極当たり前の対応なのだが、友人達やそれを見ていた他のグループ
の生徒が茶化して広めた噂が思った以上に広まってしまったのだ。
シンナーの噂は流石に教師陣も気になったらしく、煌成は職員室に呼ばれて問いただされる
はめになった。
「ヤンキーに絡まれたのも違うだろ」
「結果的に気を失ったのは同じだけど」
貧血が酷くて、ふらふらになりながら歩いているところを他校のヤンキーの群れに突っ込んで
しまい、気を失ったところを助けられたのだ。
「世の中には親切なヤンキーもいるんだ」
煌成は能天気にそんなことを言った。
かっこ悪い噂は次々に生まれ、そして、煌成は今や、モテ男の対象ではなく、ネタ男と
して、皆からもてはやされているのだ。
一目置かれている存在なら、モテるのも笑われるのも一緒だと煌成は笑った。
「勿体ないよなー、それだけかっこよかったら、そんな噂全部吹っ飛ばして、超モテ男に
なって、ヤリまくるのに」
「ヤリまくったら、それはそれで噂になるだろ」
「そこは、テクで黙らせる!」
袴田の直結の脳みそに煌成は苦笑いで首をすくめた。
別にどんな噂を囁かれようとも、自分の彼女になった子が自分の真実を知ってくれれば
煌成は構わないと思っていたし、そんな噂でやれる、やれないが決まるとも思っていな
かった。
ちなみに、噂に上がった煌成の『はじめて秘話』は、極度の緊張で不能になったわけ
ではなく、前日から胃腸の調子が悪く、性欲が負けた所為で失敗に終わったのだった。
「どっちにしろ、これはかっこ悪い」
「我ながらそれは同感・・・」
保健室から、慌てて逃げ出してくると真桜は完全に怒っていた。
「真桜〜」
「もう!ホント最低!!」
真桜は瞳を潤ませて、泣きそうな顔をしながら煌成を見上げた。
「ごめんごめん、悪かったって〜」
「悪かったで済んだら、怒ってないわよ!!」
「済まないのかよ」
「あんた、あそこにいたの誰だと思ってんの!」
顔を真っ赤に膨らませて真桜が睨んだ。拗ねながら怒ってる真桜は可愛いと思ったことが
あるが、今の真桜は本気で怒っているようで、煌成は背筋が寒くなった。
「誰って・・・新しい保健の先生だろ」
「その後ろにいた生徒よ!」
「ああん?・・・・・・そんなのいたか」
「いたわよ!去年の保健委員の井沢!歩く拡声器!!」
「なんだそりゃ」
「あんた、井沢を知らないの!?」
「・・・・・・いや、井沢は知ってるけど、歩く拡声器って・・・」
何だそれ?の勢いで煌成が呟くと、真桜は信じられないと言う目で煌成を見上げた。
「煌成、あんたの噂があれだけ広まってるのも、井沢の所為なのよ!?」
「そうなん?」
「・・・・・・信じられない。アイツだって中学校からの上がり組よ!もう4年も一緒の学校に
いるのに、井沢の実態知らないって、ありえないでしょ!」
「だって、別に友達じゃないし」
「あたしだって友達でもなんでもないわよ!でもね、アイツは見たり聞いたりしたことを
何十倍にもして広めるヤツなんだから。・・・・・・絶対さっきの事だって、噂になるんだわ」
普段から噂を垂れ流されている煌成にとっては、今更だったが、真桜にしてみれば、堪った
もんじゃない。
「悪かったなあ」
「済まないわよ!!・・・・・・私、本気で狙ってる人いるんだから!!・・・・・・そんなふしだらな
噂があの人のトコまでいっちゃったら、どうすればいいのよ。ああ、もう!全部煌成の
所為だからね!!」
「・・・・・・ごめん」
真桜はツンと怒ったまま煌成を置いて歩き出した。当分許してくれそうもないし、仕方なく
煌成は、教室へ戻っていく真桜の背中を見送った。
しかし、煌成の夢精から始まった被害はそれだけではすまなかった。
保健室では、歩く拡声器井沢が、早速、煌成のあることないことを伊純に吹き込んでいた
のだ。眉間に皺を寄せながら伊純は井沢の話を聞いていた。
「守備はどうだったよ」
次の日、登校してきた煌成を待ち構えていたのは、ニヤニヤ顔の袴田だった。
「ああん?」
「真桜ちゃんと保健室でエロエロプレイしてたんだろ」
袴田は煌成の席に乗り出して煌成の反応を待っている。
「・・・・・・すげえ、井沢ってホント、人間拡声器」
煌成は、真桜の激昂した姿を思い描いてぶるっと震えた。当分真桜には近づくまい。
「保健室プレイなんて、おいしすぎるじゃん」
「ばーか。手出す前に見つかって、エロエロプレイどころか、乳にだって触らして貰え
なかった」
「なんだ、ガセか・・・・・・って見つかったの、お前。ばっかじゃん」
「だってさー、いきなりあの保健の先生が来てさー」
「ああ、いずみちゃん?」
「ちゃんはないだろ、27だか8のオッサンに」
そこまで言うと、袴田は豪快に溜息を吐いた。袴田にももう伊純の正体は伝わっているの
だろう。
「てかさ!保健の先生が男とかありえねえよな!」
「オバチャンがいるだろ」
「冗談。俺の夢とロマンを返せってカンジ」
「お前のロマン、小さいな」
笑いながら雑談をしていると、チクリと胃の辺りに痛みが走った。いつもの胃痛で、思い
当たる節もある。
勿論、昨日の真桜の怒りの所為で、胃が痛くなっているわけではない。神経はそれほど
デリケートには出来ていないのが煌成のいいところだ。
「・・・・・・痛っ」
「何?」
「ちょっと、胃が・・・・・・」
「またか」
「昨日の夜のトンカツ、油がやばかった」
実は今朝は胃もたれで、朝食すら食べられなかったのだ。
「お前の胃って、どうしてそこまでデリケートなんだよ。面の皮はこんなに厚いのに」
「関係ないだろ・・・うぅ。ちょっとトイレ・・・・・・」
結局、煌成は胃痛と戦いながら2時間目まで頑張ったが、3時間目の途中でギブアップして
しまった。
「せんせ〜、俺、保健室〜」
痛む胃を押さえながら手を上げると、またかと呆れられたが、担任は事情を分かっている
ので、それ以上言及されることはなく、教室を後にして保健室に向った。
けれど、保健室に向かいながら、別の痛みがこみ上げてくるようだった。
「昨日の今日で忘れるわけないよなぁ。オバチャンがいてくれるといいんだけど」
珍しく躊躇いがちなことを思っていた煌成だが、その淡い期待はあっさりと崩れ去った。
保健室のドアを開けると、出てきたのは昨日のしかめっ面の男、伊純だった。
「・・・・・・どうしましたか」
「えっと・・・・・・胃が痛いんで、ちょっと休ませてもらいたいんだけど」
そう言うと、伊純は煌成を足元から頭のてっぺんまでゆっくりと見上げた。体格だけはいい
煌成よりも、伊純は少しだけ背が低い。しかし、痩せているせいが、ずっと小柄に見えた。
「あの・・・・・・」
声を掛けると、伊純に思いっきり睨まれた。
お互い、昨日の事をはっきり覚えている証拠だ。当たり前だが、忘れてくれないかなと
いう煌成の願いは全然届いてなかった。
昨日、保健室のベッドでいかがわしい事をしようとした男子生徒として、伊純の中には
きっちりインプットされているようで、煌成を見る目つきが厳しくなっていた。
「・・・・・・」
「本当に、胃痛?」
「は?」
「君はサボり癖があるとか」
誰だそんなこと吹き込んだのは。ああ、井沢か。
「そんな癖はありませんけど」
「体調が悪いようには見えませんよ。ここは具合の悪い生徒が一時的に休息を取る場所です」
「・・・だから、俺、体調悪いんですけど」
「昨日、保健室のベッド使用記録を見ましたけど、随分、ここに来てるようですね」
サボりだと決めて掛かっているのか、伊純は厳しい口調で煌成を問い詰める。サボりなら
教室に返すのが養護教諭の勤めだと言わんばかりの態度で伊純は保健室の前に立ちはだかる。
煌成は、初めて井沢を呪った。
こうしている間にも胃がキリキリと痛んで、煌成は思わず前屈みになって、伊純の方へと
身体が揺れた。
「ちょっ・・・何っ・・・やっ・・・・!」
倒れこまれるとでも思ったのか、近づいてきた煌成を伊純は思い切り突き飛ばす。びっくり
したのか頬が赤くなっていたのだが、煌成は伊純の様子など見ている余裕は無かった。
「うげぇっ・・・」
胃痛で苦しい上に、伊純に突き飛ばされて、煌成は保健室から転がり出てしまった。
「せんせ・・・何すんだ、よ・・・・・・」
煌成は胃と口を押さえて、伊純を見上げる。額には脂汗が浮き出ていた。
流石にそこまで来ると、伊純も漸く煌成が芝居ではなく、本気で体調が悪い事を悟った。
「・・・・・・本当に、体調悪い?」
「さっきから、そう言ってるだろっ」
保健室の前で言いあっていると、漸く助け舟がやってきた。
「あらあら、海老原君、また胃痛でも起してるの?」
「あ〜、オバチャン!・・・助かった・・・・・・」
「・・・・・・国村先生!」
保健室のオバチャン、国村先生は、にこやかな笑顔のまま2人に近づいて来る。それから
ゆっくりと煌成を起き上がらせると、保健室の中に運ぶように伊純に言った。
伊純は眉を顰めながらも、煌成に肩を貸して、保健室の長椅子に座らせた。
「うげぇ・・・・・・もう、オバチャン、遅いよ〜。もう少しで俺、サボり決定で追い出される
所だったんだから」
「あはは、噂がこんな新しく赴任してきた先生のところまでもう届いてんの」
「笑い事じゃないよ・・・・・・」
煌成が脂汗を拭っていると、オバチャンは煌成の前に湯冷ましを差し出した。
「日ごろの徳が足りないんじゃないの?・・・・・・はい。湯冷まし。薬持ってるでしょう?」
「ありがと」
煌成はブレザーのポケットから病院で処方されている薬を取り出すと、湯冷ましでそれを
飲んだ。
「一応、血圧と体温だけは測っておいて。それ終わったらベッド使用表に名前書いて、
寝てていいから。緑川先生、お願いね〜」
そう言うと、オバチャンは事務机に座って、さっさと自分の仕事に取り掛かってしまった。
「え、あ・・・はい」
オバチャンと煌成のやり取りを見て、伊純は煌成が保健室の常連であるのはサボりではない
と漸く察知したが、それでも腑に落ちない顔をしていた。
「先生」
「・・・・・・はい」
「血圧、測ってくれんでしょ」
煌成はブレザーを脱いで、シャツを捲りあげた。そこそこ筋肉の付いた腕がむき出しに
なって、伊純は思わずそれに見とれてしまった。
「・・・・・・先生?」
「いや・・・はい。今測るから・・・・・・」
血圧計を取り出して、伊純は煌成の手を取った。
伊純のその手が緊張で小さく震えていたのも、耳の先が妙に赤くなっていたのも、勿論
いつもよりも倍のスピードで心臓が波打っていたのも煌成は知らない。
なんと伊純は、煌成のこの顔に一目惚れしていたのだ。
最悪な出会いでも、自分の好みの顔に出会えれば、忘れられない思い出にはなる。好み
の顔に出会えた喜びと、その男が10も年下で、しかも保健室で女子生徒といかがわしい事
を起そうとしていたという怒り。全く逆の感情を突きつけられる羽目になった伊純にとっても
最悪な出会いだったのだ。
「・・・・・・?」
そんなことはつゆ知らず、煌成はやたらと険しい顔をした伊純をあまり歓迎できずに見下ろ
していた。
――>>next
よろしければ、ご感想お聞かせ下さい
nakattakotonishitekudasai ©2006-2010 kaoruko since2006/09/13