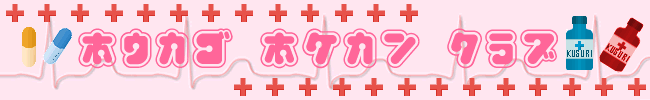
夢の中で会えますように、毎日願ってるんですが・・・
気がついた時は煌成はベッドの上に押し倒されていた。
アップで近づいてくる顔は艶かしく、それだけで自分が置かれた状況を煌成は把握した。
「せ、せんせいっ・・・・・・ちょっと待って・・・・・・」
「いいよ、大丈夫」
せんせい――勿論煌成がそう呼ぶのは養護教諭の伊純だ。何故こんな状況になっているのか
ましてや、どうして自分と男の伊純がこんなことをしなければならないのか、煌成の頭の
中は大パニックになっている。
けれど、そんな煌成を尻目に伊純は余裕たっぷりの笑みを浮かべてもう一度、大丈夫と
呟いた。
「大丈夫って・・・ここ、保健室だし!」
何が大丈夫なんだと煌成が食って掛かると、伊純は全体重を掛けて煌成をベッドに縛り
付けた。身動きが取れなくなると、煌成は不安げに伊純を見上げる。それにうっとりした
表情で伊純が答えた。
「うん。今は『使用中』にしてあるから大丈夫だよ」
「何の使用中だよ!」
「だって、ホケカン倶楽部でしょう?」
ホケカン倶楽部。そうか、自分は真桜とそんな馬鹿げた倶楽部を作る約束をしてしまった
のだ。メンバーは自分と、真桜と・・・・・・やっぱり責任者として伊純も参加することになった
のだっけ?自分の曖昧な記憶に煌成が戸惑っていると、伊純の行動は益々エスカレートした。
ブレザーを脱がされ、シャツのボタンが一つずつ外れていく。襲われているのは確実で
これから先、自分がどんな目に遭うのか想像するだけで、身体中が痺れた。
「ほ、ホケカン倶楽部ってこういうことするところなのかよ」
「違うんですか?」
「違うだろ!大体、ホケカン倶楽部って・・・」
「保健室官能倶楽部でしょう」
んな馬鹿な・・・!と叫ぼうとしたところで、煌成はわき腹にぞぞっとする伊純の手を感じた。
見れば、伊純が煌成のシャツを全開にして、長い指で煌成の素肌を楽しそうになぞっている。
「ちょっと、止めてって・・・・・・あっ」
「ふふ、感じてる?」
伊純の顔のいやらしさに、煌成は身体の芯が疼いてしまった。ありかもしれないと思った
のはどうか一瞬の過ちでありますようにと、首を振る。
「む、無理だから!俺、男となんて絶対無理」
「そう?やってみなきゃわかんないよ?」
「やれないって!勃つわけないっつーの!」
煌成が喚き散らすと、伊純はそうでもないよ、と煌成に指をさした。
指された場所は煌成の股間。しかもいつの間にかベルトを引き抜かれ、ズボンもパンツも
半降ろしになって、実にすばらしく「コンニチワ」している自分のモノを煌成は目の当たり
にした。
「〜〜〜〜〜〜〜〜!!!!!」
「とわああああぁっ!!!!」
叫び声と共に目を覚ました煌成はバク付く心臓を押さえ、慌てて自分のパンツを覗いた。
「・・・・・・違う。これは朝勃ちだ〜〜〜!!違う。絶対ちがーっ。男の生理現象!」
立派に勃ち上がっている自分の股間を眺めながら、泣きたい気分になった。
目覚める直前の夢の所為か、大筋は大体覚えている。というか、ありえないシチュエー
ションに頭の中を支配されているようだった。
「ありえない。ありえない。・・・・・・てか、ホケカン倶楽部って何の略なんだよ!!」
なんでこんな夢を見てしまったのか。頭をガシガシかきながら、枕元の携帯電話を引き
寄せて時間を確認した。既に遅刻気味の時間だ。それでも身体が重くて、ベッドから降りる
気力が起きない。無駄に携帯電話を弄っていると、今日は二度目の保健管理委員会がある
ことを思い出した。
「ちっ、これの所為かよ・・・・・・」
あんな変な夢を見たのはこれの所為だ。真桜に、ホケカン倶楽部なるものを結成する約束を
させられ、今日の保健管理委員会でそれを提案するのだ。しかも、上手いこと、藤もその
倶楽部に誘い込まなくてはならない。
そんなしち面倒くさい委員会に参加しなければいけないと思うと一ミリとも動きたくなく
なってしまった。
「ちょっとー!煌成、起きてんの!!あんた、学校遅れるわよ!!」
階段の下から母親の怒鳴り声が聞こえてくる。
「・・・・・・分かってるよ!!」
煌成も怒鳴り声でかえしたが、寝起きの声で半分は掠れてしまった。
こう言う日に激しい胃痛とか起きてくれたらいいのにと煌成は、今朝は元気ハツラツの
自分の胃を擦りながら、仕方なくベッドから降りた。煌成は胃腸は弱いけれど、精神は
それ程弱くない。ストレスから胃痛になることなどありえなかった。
不貞腐れながら身支度を整え、その怒りの矛先を階段にぶつけながら降りていくと、
ダイニングで、母親と妹が冷たい視線で煌成を迎え入れた。
「お、そ、よ、う!さっさとご飯食べなさい!学校遅刻するわよ」
「分かってるっつーの!・・・・・・ご飯いらないから、水くれよ」
「馬鹿たれ。そんなことしてるとまた胃痛で倒れるわよ」
母は煌成の背中をばんと叩いて、椅子に座らせると、ご飯をもりっとよそった。
「朝から、こんなに食えるか。こっちの方が消化不良で胃痛になるわ」
文句を言えば、リビングで携帯を弄ってた妹が食って掛かってきた。
「お兄ちゃん!」
「何だよ」
「朝からうるさい!大体、階段くらい静かに下りて来れないの?」
「はいはい、そりゃどうもすんませんね。お前もさっさと学校行けば?」
「言われなくても今から行くわよ!お兄ちゃんと違って、遅刻したくないからね!」
ストレートの髪の毛を揺らしながら、妹はリビングを出て行った。
「煌成、ちゃっちゃと食べちゃいなさい!」
慌しい海老原家の朝は、煌成の内心以外はいつもと同じ光景だった。
「伊純、おはよう。のんびりしてて大丈夫?」
洗面所で身支度を整えていた伊純は声を掛けられて振り返った。そこに立っていたのは伊純
の姉で、臨戦態勢よろしくキャリアスーツをかちっと着こなした姿は、伊純にすら眩しく
映った。
「姉さん、おはよう。僕もそろそろ出掛けるよ」
「今日は遅くなる?私、仕事が残ってるから今日は遅くなるし、きっと帰りに皆で飲んで
くると思うから、晩ご飯いらないんだけど」
「わかった。僕も今日は委員会があるし、その後で仕事して帰るから、ちょっと遅くなる
かな。晩ご飯は適当に済ませるよ」
「そう。分かった。遅くなるなら、夜道気をつけてね」
「それはこっちの台詞だよ、姉さん」
伊純は苦笑いして、姉を送り出す。一緒に玄関まで行くと、伊純は思い出したように言った。
「あ、そういえば、来週末、母さん達が来るって」
そう言うと、途端に姉は顔を曇らせた。
「・・・・・・また見合い話持ってくるんじゃないの?伊純、さっさと結婚してお母さん達の
不満を少しでも減らしてよ」
「それを言うなら姉さんの方でしょ。僕よりも心配してるのは姉さんの方だよ」
「私は嫌よ。仕事ガシガシしたいんだから。・・・・・・まあ、伊純に結婚しろっていうのは、
酷か」
姉が苦笑いした。伊純はそれに答えられず、曖昧な表情を浮かべる。
「・・・・・・じゃあ、先に行くわ。戸締りよろしくね」
「いってらっしゃい」
姉がマンションの玄関を開けると、爽やかな風が舞込んで伊純の髪の毛を優しく揺らした。
伊純は玄関前の姿見を振り返ると、自分の顔を覗き込んでそして盛大に溜息を吐いた。
「酷というより、相手に失礼っていうんだよ」
姉は伊純の性癖を知っている唯一の親族だ。姉と2人でマンション暮らしをするときに、
思い切って告白した。頭の固い姉ではなかったので、自分の事も多少は理解してくれている
らしいけれど、あまりフォローはない。
伊純はそれでもいいと思っていた。変に親身になって根掘り葉掘り聞かれるより、そっと
しておいて欲しい。
なにせ、自分の欲している相手は、男なのだ。しかも、今や狙っている相手は、年下の
高校生となれば、相手が男じゃなくても白い目で見られるに決まっている。
なんであんな若いだけがとりえのような男に惚れてしまったのか。自分の趣味をつくづく
恨みたくなる。嫌いだ、嫌いだ、あんな顔趣味じゃない、と呪いの様に言い聞かせてみても
彼が保健室にやってくるたび、やっぱり心臓がきゅんと反応してしまうのだ。
「顔だけが好みなんて、相手にだって失礼なのに」
いや、正確に言えば伊純は煌成の顔だけでなく身体にも惚れているのだが、それをプラス
しても、なお失礼なことだ。
けして外見重視のつもりはないけれど、見た目は必要だ。趣味じゃない男と恋愛する程
若くもないし、どうせ毎日見るなら、好きな顔の方がいいに決まってる。
伊純は、煌成と自分が隣同士並んでイチャイチャする姿を想像した。高校生の煌成に
どんな台詞を言わせようかと考えて、姿見に映った自分が凄い顔をしていることにぞっと
した。
「・・・・・・僕は変態か」
10も年下の高校生に抱かれたいなんて、どうあっても夢のまた夢だ。奥手と言うほど奥手
ではないけれど、こんな大きなハードルを越えていけるほどパイオニアでもない。
せめて煌成がゲイであったらもう少し可能性はあるのかもしれないが、初めての出会い
がアレでは、それもありえないだろう。スーパーストレート、万が一があって「両刀」だ。
「どうせ無理なら、妄想で消化するしかないデショ」
そう思って、昨日の夜も夢くらい美味しいコトしたいと煌成との濃厚セックスを妄想しな
がら眠ってみたが、見れたのは趣味じゃない男子高校生がわんさか出てくる身体測定の夢
だった。
伊純は盛大に溜息を吐いた。近づきたいけど、近づくだけこの恋愛が困難すぎることを
突きつけられるようで、伊純は自分で自分の首を絞めている気分だった。
今日は保健委員会がある。確実に煌成が保健室にやってくる日だ。校内を無駄にうろつく
訳にいかない伊純が煌成に会えるのは、体調が悪くて保健室にやってくる時か、保健管理
委員会のときだけだ。
会わなければ心も掻き乱されることはないと分かっていても、会える日はやっぱり気分
が浮つく。それを悟られないように、伊純はいつも必死に仮面を被っていた。
けれど、それが逆に印象を悪くしていることに、伊純はあまり気づいていないのだった。
放課後の保健室では、保健管理委員会が開かれていた。
明日から始まる身体測定の打ち合わせに、その後の記録整理の手伝いや、日常の仕事の
確認など、一方的な説明で、それほど盛り上がることもなく委員会は終盤に差し掛かって
いた。
「では、最後に何か意見のある人はいますか」
進行役の藤が回りを見渡して言う。どうせこんなところで意見する人間など誰もいないと、
藤を含めて誰もが思っていた。
「・・・・・・」
「痛っ」
沈黙の中で、煌成の声が小さく響いた。数人が煌成の方をちらりと見ている。煌成は顔を
顰めて真桜を振り返った。真桜に蹴られた脛がジンジンと痛む。
「・・・・・・」
真桜は煌成を睨んで、もう一度煌成の足を蹴った。
『はやく言いなさいよ』
その表情を見れば、真桜の言いたい事は嫌でもわかる。煌成は逃れられないことを悟って
渋々手を上げた。
「あ、あの・・・・・・」
「海老原君、意見ですか?」
「えっと、その・・・・・・」
煌成がもぞもぞ言い始めると、更に注目が集まって、煌成は身体の中から熱くなってくる
のが分かった。
「・・・・・・今まで委員会の活動して思ったんすけど、あんまり保健委員の重要性が他の生徒
に伝わってないっていうのが、ちょっと気になって・・・」
煌成が切り出すと、別のクラスの男子が面倒くさそうに呟いた。
「伝わる必要なんてあんの?」
「つ、伝わる必要があるかどうかは・・・・・・俺もよく分からんけど、校内の安全の事とか、
この学校、美化委員ないから、美化や清掃の事とかも保健委員がやってるし、そういう事を
もっと皆で考える機会を作った方がいいかと思って・・・・・・」
その発言に、大半の生徒は迷惑そうな顔をした。煌成だって内心は大迷惑だ。そんなこと
微塵も思っていない。
「それで、海老原君はどうしようと思ってるんですか?」
伊純に振られて、煌成はピクリと頬を揺らした。
そうだ。全てはこの男の真意を暴く為にやっていることだ。伊純の横顔は穏やかそうで
それでいて自分に向かってくる言葉は冷たく乾いて聞こえた。
「皆も忙しいと思うから、とりあえず保健管理委員の有志だけで、この学校の保健や美化
の事を考える会を作ったらと思うんですけど」
有志の言葉にほっとした溜息があちらこちらから聞こえてきた。参加者などいるはずが
ない。保健管理委員会に出席するのだって半分は義務で来ているのだから、進んでそんな
会に出ようなどという奇特な生徒などいるはずなかった。
勿論それは煌成の――いや、真桜の作戦で、ホケカン倶楽部に参加する生徒は、真桜と
煌成、そして藤さえいればいいのだ。
「委員会内クラブみたいな感じで考えてもらえればいいんすけど、委員長、どうっすか?」
煌成はそう藤に振って逃げた。後は藤を巻き込むだけだ。そう思ってほっとした顔を見せた
とき、人間拡声器の井沢が煌成の方を訝しげに見ていたことに、煌成は気づいていなかった。
「海老原君は発案者なので、当然参加すると思うけど、他にいるかな・・・・・・」
藤も困ったように周りを見渡した。
「お、俺は、委員長は真面目だし、広い視線で周りを見渡せるから、是非委員長にも参加
してもらえたらって思うけど」
「俺?」
藤が驚いて煌成を見た。煌成は遠慮がちに頷く。保健委員で一緒になるまで殆どしゃべった
こともない藤に、そんな無茶振りをするのは煌成だって気が引ける。
「駄目、かな・・・・・・」
「う、ん・・・まあ、いいけど・・・・・・」
根が真面目なのか、藤は断ることが出来ず、渋々返事をした。
「・・・・・・」
その様子を複雑な表情で見ていたのが、伊純だった。伊純フィルターで覗いたこの光景は
完全に煌成からの「お誘い」に見えてしまうのだ。ちくりと胸が痛んだ。ただの高校生に
どうしてこんなに心を掻き乱されてしまうのだろう。
「他に参加してくれる人いないかな」
藤が周りを見渡すと、次々に生徒が目を逸らした。誰も手が上がらないことが分かると、
真桜は内心ほくそ笑んで、おずおずと手を上げた。
「・・・・・・他に誰もいないのは可哀想だし、私参加してもいいよ」
「本当?」
藤が安堵の笑みを浮かべた。煌成と2人よりは随分マシなのだろう。その笑みに真桜も頬を
ピンクにして頷いた。
「3人だけの小さな会だけど、何かやれることあるかもしれないしね」
「じゃあ、この3人で決まりでいいですか?・・・・・・先生、どうでしょう?」
藤が纏めて伊純に話を渡すと、伊純は一瞬言葉を詰まらせた。
会の内容について異論はない。というか、殆ど耳を素通りしてしまった。伊純が躊躇した
のは養護教諭の立場でその会の必要性を問うたのではない。伊純個人の問題だ。
そういう会が発足されれば、煌成が保健室に来る頻度も上がるだろう。煌成に会えるのは
やっぱり嬉しい。けれど、もしも煌成が本当に「両刀」で、しかも藤を誘っているのだと
したら、自分はその恋の過程を見守っていかなければならなくなってしまう。
そんな嫉妬だらけの自分など見たくない。
この瞬間、煌成が伊純の心を覗き見できていたら「そんなこと1ミリもありえない」と
大声で喚き散らすのだろうが、恋は人を盲目にするのだ。
伊純は心の中のぐるぐるした気持ちを全包囲して、無表情で彼らを見下ろした。
会える機会を取るか、嫉妬に明け暮れる日々を取るか・・・・・・。
「わかりました」
伊純は覚悟を決めた。もし、煌成がバイならば、自分だって入り込める余地はあるのだ。
それこそチャンスだと、プラス思考に考えると、いつもの穏やかな笑みを浮かべた。
「保健委員会がそれだけ積極的に動いてくれるというのはとても嬉しいことです。僕も
担当教諭として参加しますので海老原君、藤君、塚元さん宜しくお願いします」
参戦すればいいのだ。高校生だと思って、躊躇っていたらあっという間に他のヤツと恋愛
始めてしまう。高校生はそういう人種だ。
伊純もやっと決心がついて、話はこれで纏まったと誰もがそう思ったときだった。煌成
も真桜もそれぞれ安堵をかみ締めているところに爆弾は投げ込まれた。
「先生、やっぱり俺も参加してもいいですかー」
煌成と真桜がその声に反応して振り返ると、そこには人間拡声器井沢がニヤニヤして手を
上げていたのだった。
「!」
「!!」
ホケカン倶楽部の運命はいかに・・・・・・?
――>>next
よろしければ、ご感想お聞かせ下さい
nakattakotonishitekudasai ©2006-2010 kaoruko since2006/09/13