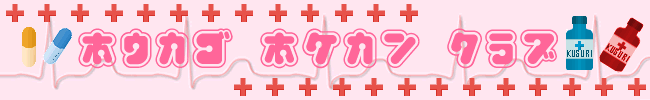
これでも一応、保健の先生なんですよ・・・
今日は朝から保健室が騒がしい。次から次へと保健委員が「あるもの」を持ってやって
くるからだ。
伊純はそれを事務机で作業しながら受け取っていた。
「失礼しまーす。先生、3年5組、検尿集めてきましたー」
「ご苦労様。未提出の人はいないかな」
「えっと、出せない女子が2人いる以外は全部入ってます」
「分かりました。じゃあそこの名簿の自分のクラスにチェック入れて、検尿はそっちの箱
に入れておいてくださいね」
「はーい」
生徒は自分のクラスにチェックを入れると、保健室を後にした。
始業まであと3分。伊純が名簿を引き寄せて確認すると、あと一クラス分だけ未提出の
クラスがあった。2年3組だ。
伊純は、2年3組の保健委員が誰であるか考えなくても分かっていた。校内で一番会いたい
相手だけど、会うと一番気持ちを揺さぶられてしまう相手、煌成がまだやってきてないからだ。
最後の一人の提出者を待つというより、煌成を待ちながら、伊純はそわそわしていた。
身体測定の日から毎日想像している煌成の裸。寝る前には散々弄繰り回して、本人に会う
たび、自分が教師の顔をしていられるか正直自信がなくなっているのだ。
始業まであと1分を切った所で、バタバタと廊下を走ってくる音がした。
「・・・・・・はっ、はっ・・・・・・失礼、しまー・・・検尿持って、来ましたー」
煌成が額にうっすらと汗をにじませて、保健室のドアを開けた。
「ご苦労様です」
どれだけ走ってきたのか、息の上がった煌成に、伊純はまた余計な妄想をしてしまう。
そうして、我に返った瞬間、自分の恥ずかしさに伊純はいつもの倍以上の仮面を被って
いた。
冷徹な表情で言われて、煌成は小さくちっと舌打ちをした。
「未提出の人はいませんか?」
「え?そんなの調べてくるの?・・・・・・俺、さっき学校着いたばっかりで、担任にコレもって
保健室行って来いって言われただけだし・・・・・・」
「じゃあ、ここで確認していってください」
「えー!授業始まっちゃうって」
「いつもサボってるような君が、そんなこと気にするんですか」
無表情で煌成に言うと、煌成はむっとして口を尖らせた。その拗ねてる顔も可愛く見えて
しまうのに、伊純は自分でも末期だと思った。
「保健室で寝てるのはサボってるんじゃないっつーの!」
「ちょっとくらいサボれるなら嬉しいでしょ」
「・・・・・・先生、俺の事なんだと思ってんの。1時間目の数学、サボるとうるさいっつーの」
「正当な理由があれば、大丈夫ですよ」
「世の中にはそういう理由も通らない理不尽なこともあるの!ってか、これ俺の仕事〜?」
「保健委員ですからね」
「何が楽しくて他人の尿なんて触らなきゃならないんだよ・・・」
ブツブツ文句言いながらも、煌成は手に持った検尿の袋を机の上に置くと名簿と検尿の名前
をチェックし始めた。
検尿の入った小袋の隅を手で摘みながら、煌成は名前をチェックしていく。
その姿に思わず顔が綻びそうになって伊純は顔を擦った。
「これは、袴田か・・・。うげー袴田のシッコ手で触っちゃったー。ソッコウ手洗いたいっ」
「・・・・・・海老原君、袋まで尿が洩れてるわけじゃないんですよ」
「気持ちの問題だろ、いやあいつのことだからトイレから出てても洗わずにきっとコレを
触ったんだ。うー、萎える」
煌成は袴田の検尿の小袋を出来るだけ隅を摘んで袋に戻すと、次の検尿を手に取った。伊純
がちらっと煌成の手元を見ると、次に煌成が手にしていたのは、煌成自身の検尿だった。
伊純は朝から妄想天国になっていて、煌成の検尿姿を卑猥チックに思い描いた。
後ろから煌成の腰に手を回して、煌成のペニスに手を伸ばし、検尿コップに尿を入れる
のを手伝いながら、「別のものも出ちゃいそう」という煌成に「蛋白で引っかかりますよ」
と耳元で囁く伊純。
「再検査になっちゃうっ・・・」
「僕が幾らでも再検査してあげますよ」
そう言いながら煌成のペニスを擦って、煌成を困らせている姿を瞬間で思いついてしまった。
思わず晩のオカズが出来てしまった伊純は、煌成の検尿に目が釘付けになったまま、
冷徹な表情が明らかに緩んでいた。
検尿プレイ・・・僕は変態かと、心の中で突っ込みを入れると、取れかかった仮面を再び
かぶりなおした。
「・・・・・・先生、終わったー」
「じゃあそこの箱に入れて置いてください」
「はぁーい、じゃあね、先生」
伊純の事務的なしゃべり方にも、煌成は大して気にもせず返事を返すと、ともかく手洗い
と言わんばかりに手を洗ってそのまま保健室を出て行ってしまった。
「妄想くらいで罪悪感感じる年じゃないからね。それに精液じゃ蛋白はひっかかりませんし」
伊純はセルフ突っ込みに苦笑いして煌成を見送った。
子どもじゃないんだから、自分の性格はそれなりに理解しているつもりだし、その自分
の性格が、少々捻くれている事も分かっている。
好きな相手に素直になれないのは昔からで、漸く心を打ち解けた頃に「絶対嫌われてる
と思ってた」と言われる確率は100%だ。
便利な言葉ができた今では自分みたいなのをツンデレというらしいけれど、そんな造語
が流行る前から自分はツンデレだった。
ましてや今好きな相手といったら10歳も年下の未成年で、そんな相手にデレデレ出来る
訳がない。
だから、自分が煌成に対してツンツンしている自覚はあるけれど、それをどうすることも
できないのは、仕方ないのだと伊純は半分諦めていた。
そうやって接した相手なのだから、当然煌成だって伊純に対してプラスのイメージを
持つことはなかったし、暫くは打ち解けることもなかった。
しかし、永遠に埋まらないとまで思われていた2人の溝は、ここに来て少し風向きが
変わってきているように感じている。
どんな事務的な言葉で返しても、煌成は離れていくこともなく、伊純の隣にいるのだ。
初めから保健医を敬うような言葉遣いはしてこなかったが、前よりもフランクな言葉で
煌成は伊純に声を掛けている。無理矢理距離を縮められている気分で、じわじわと逃げられ
なくなっているようだった。
頻繁に会っていれば、慣れてしまうものなのだろうか。
「ホケカン倶楽部」が結成されて、煌成は面倒くさそうにしながらも、毎回、倶楽部に
参加している。必然的に煌成と顔を会わせる頻度は上がり、事務的なやり取りの中にも、
煌成の出してくるジャブに思わず乗ってしまうときがあった。相手にその気がないのは十分
承知しているけれど、心をこじ開けられそうで伊純は益々切なくなっていた。
それにしても、と伊純は思う。
ホケカン倶楽部の結成には疑問が付きまとう。
伊純は曲がりなりにも養護教諭で、保健室登校の生徒の話や、悩みを抱えた生徒の相談
にも乗ったりしているので、それなりに洞察力はもっているつもりだ。
伊純のぶれていないフィルターで覗いたホケカン倶楽部は、神聖な者の集まりではなかった。
一番初めに分かったのは、真桜の気持ちで、保健委員長の藤に惚れているのだと伊純は
気づいた。
それから、井沢の存在理由。これは簡単だった。彼はただのデバガメで、そして藤は
完全に巻き込まれた心優しい、あるいは心弱い優等生だ。
だから、ある程度は想像がつくのだ。この集まりは思惑で出来ていると。
けれど、未だに分からないのが煌成だった。
彼を見る目にはいつも100%のピンクフィルターが掛かっている所為で、まともに分析
できたことがない。
初めは藤を狙っているのかと思ったが、そのわりには藤に対して積極的な行動に出る事
もなく、かと言って尻切れトンボのようにフェードアウトしていくこともなかった。
伊純には煌成の真意が見えない。そして勿論、煌成にも伊純の気持ちは見えない。
ただ、お互い微妙にすれ違ったままだが、最近感じることは、ツンツンしてるはずなのに、
妙に煌成の距離が近い気がするということだった。
放課後、ホケカン倶楽部のメンバーがやってきて、保健室は賑やかになった。
真桜と藤が隣同士に座って、藤は律儀にノートを開いていた。
「いい加減、今日こそクラブの方針を決めた方がよくない?」
「いいけど、どうする?」
「ホケカン倶楽部便り作るんだろ?」
藤の正面に座った煌成が突っ伏しながら呟くと、真桜と藤が煌成を見下ろした。
「内容どうする?」
「煌成、何か案出しなさいよ」
煌成は顔だけ2人の方を向けて、うーんと唸った。
「風邪予防とか?」
「それは普通の保健便りに載るわよ」
「じゃあ、トイレの掃除をちゃんとやろう」
煌成が言うと、真桜から冷たい視線を浴びた。
「そんな小学生みたいな広報作ってどうすんのよ」
「そういうお前らはどう何だよ」
煌成に振られて、藤は真面目に答えた。
「・・・・・・学校で問題になってることとかはどう?」
そうして、一斉に井沢の方を振り返ると、
「そういうのはお前が一番詳しそう」
と煌成は言った。
「問題ねぇ。学校の噂で多いのなら分かるけど」
「何?」
真桜が興味深そうに井沢を振り返る。
「エンコウ、性病、妊娠」
「妊娠?!」
「噂だって。アレが来ない〜っていう女子には噂が立つんだろ?」
「そう簡単に妊娠の噂なんて立たないわよ!」
「まあ、妊娠の噂は大抵がガセだけど、エンコウと性病はあながち嘘じゃないだろうな」
井沢はしったかぶった顔で頷いた。
煌成は噂話にはそれ程興味はないし、そんな話は聞いたこともないから、井沢のデマに
しか聞こえなかったのだが、それを聞いていた伊純が溜息を吐いて、話に加わってきた。
「そうやって噂になるから、余計に盛り上がっちゃうんでしょうかね・・・・・・」
「先生、何か知ってるの?」
「・・・・・・守秘義務もありますからあまり大きな声では言えませんが、この学校に来てから
既に何件か相談に乗ってます。・・・・・・確かに生徒同士で、セックスについて問題提起する
のは良い事だと思いますよ。教師側から援助交際するなとか、避妊しないセックスの危険性
について説いても、鼻で笑われて終わりな部分もありますからね。実際、前任の学校で、
そういう取り組みをしてましたし」
自分の時代もそうだったけれど、高校生は性に貪欲だ。もし自分が高校生の頃、自由になる
お金や時間がたっぷりあって、尚且つゲイの世界に堂々と飛び込めていたら、馬鹿になる
までやっていた気がしてならない。
今でも、はけ口の為に生徒の前では堂々と宣言できないこともしているけれど、それは
大人の自分の責任の下やっていることであって、やっぱり高校生には許されるべきことでは
ないのだろう。
この問題を考えると、教師としての今の自分と、過去の自分の間でいつも悩まされていた。
「じゃあ、それで行けば?」
煌成はムクリと身体を上げて呟いた。
「どれ?」
「フリーセックス、性病、エンコウ、どれでも選びたい放題だろ。ホケカン便りの題材」
「結構大きなテーマだね」
藤は律儀にノートにテーマを書き並べていく。真桜が覗き込んで
「何回かに分けて載せるべきかも」
と言った。文化祭のノリに似ているのか、真桜は明らかにテンションが高くなっている。
「でもさ、テーマがでか過ぎてイメージ沸かなくない?」
井沢が言うと、真桜が振り返って伊純に聞いた。
「先生、前の学校ってどんなことしてたの?」
「そうですねぇ・・・。生徒にアンケート取ったりして、最終的には文化祭で発表してたかな」
「すげぇ、本格的」
「アンケートかあ、面白そう」
井沢が企んだ顔で言う。
「でもどんなこと聞けばいいのよ?」
「先生、前の学校でやった資料とか残ってないの?」
「家に帰ればありますけど・・・・・・」
「持ってきてもらえますか?」
藤に言われて、伊純は渋い顔をした。
「ダンボール4箱くらいに資料が点在してるので、それを探すのは・・・・・・」
「俺達手伝います!」
乗り気で井沢が手を上げた。
「手伝うって言ってもねえ。ダンボールごと持ってくるのも大変だし」
「じゃあ、先生のうちにお邪魔してもいいですか?」
「ウチに?!」
「あ、私も先生のお家行きた〜い」
「俺も手伝います」
藤も手を上げた。
「えっと・・・・・・」
突然振って沸いた生徒の訪問案に、伊純は焦った。家の中を思い出して、見られて困るもの
がどれだけあるか数えてみる。
とりあえずゲイのDVDとローションやら道具は絶対封印するとして、後は大丈夫だろうか・・・
渋い顔のまま、煌成を振り返ると、煌成も困惑気味だった。
「海老原君も来ますか?」
「・・・・・・皆が行くっていうなら、俺も手伝ってもいいけど・・・・・・」
煌成が部屋にやってくる。理由はどうあれ、他に余計なものが沢山ついてくるとしても、
煌成が家にやってくるというだけで、伊純のテンションは上がり始めた。
あわよくば、なんてシチュエーションにはなるはずもないのに、妄想住人と化した伊純
の脳の中では既に煌成が部屋の中にいて、好き勝手動いている。
「分かりました。じゃあ、次の日曜日、うちに来てください」
「やったー」
真桜が純粋に手を叩いて喜んだ。井沢は含んだ笑いを込めて頷き、煌成は複雑な顔をして
伊純にはその表情の意味は読み取れなかった。
――>>next
よろしければ、ご感想お聞かせ下さい
nakattakotonishitekudasai ©2006-2010 kaoruko since2006/09/13