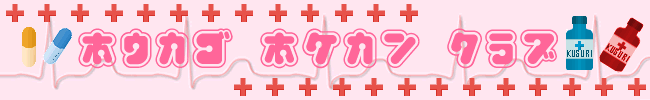
理由なら、そこに君がいるからで十分だ・・・
「ねえ、分かってるんでしょうね?」
「は?」
真桜に小声で話しかけられて、煌成はぽかんと口を開けていた。
「は?じゃないわよ、は?じゃ!」
真桜は正門前で少々イライラしながら辺りを見渡していた。
今日は約束通り、ホケカン倶楽部のメンバーで伊純の家に行く日なのだ。日曜日の10時
に正門前に集合、伊純は渋々迎えに来ると言ったのだ。
私服姿の真桜はいつもよりセクシーに見えるのだが、多分コレをアピールしているのは
自分でなく、藤だということくらいは煌成にも理解できた。
「いい?あたしと藤君の邪魔しないでよ?」
「・・・・・・誰がするか」
もう、真桜とは終わったことだ。やらせてくれるならホイホイ着いて行く自信はあるが、
恋愛をする気にはなれない。いい身体の女だと思うけれど、キツイ性格を知っている分、
愛おしいとは思えないからだ。藤に恋していると知った瞬間、面白くないと思ったのは恋愛
感情からではなく、もう二度と真桜とセックスできないと悟ったからに過ぎない。自分の
おもちゃを取り上げられた子どもと同じようなもんだ。
だから真桜が誰と恋愛しようと煌成は一向に構わないし、勿論応援するつもりもなかった
・・・・・・のだが、事情が変わってしまった今は、仕方なしに真桜の言う通りにせざるを得な
かった。
「分かってると思うけど、煌成が邪魔しないのは当たり前として、井沢からも守ってよ!」
真桜は正門の前の道をきょろきょろしながら煌成に言った。
正門前にはまだ煌成と真桜しか来ておらず、真桜はさっきから藤が本当に現れるのか
不安で仕方ないようだった。
「そんなこと言われても、俺は何すりゃいいんだよ」
「適度に会話に加わって、適度に遠慮してくれればいいのよ」
「分かるか、そんなの」
「空気読めってコト!」
「・・・・・・大体、お前はそれでいいかもしれないけど、俺のメリットはあるのかよ」
「伊純先生の家に行くんでしょ?それだけで先生のルーツを探る大チャンスじゃない」
「全然ギブアンドテイクになってねえ・・・・・・」
「先生の家に行くのをごり押したのは私よ、感謝しなさい」
「はいはい、そうですか・・・・・・」
そう言われても、実際のところ煌成は伊純のルーツなど知りたいとは思っていなかった。
確かに自分にだけ冷たくしてくる理由は気になるし、今でもそれを暴こうという思いはちゃんと
ある。
けれど、それを突き動かしている思いは恋愛感情ではなく、ただ気になるからだと煌成
自身そう思っていた。
嫌われているより、好かれている方が気分は悪くないのは当たり前で、それは誰に対しても
同じことだ。特別伊純に対して興味があるではなかった。ましてや恋愛対象になどなる
はずもない。
ただ、時々夢で見てた伊純との濃厚な絡みを思い出して、いたたまれない気分になったり
するだけだ。
本物の伊純がゲイで煌成の事をそんな視線で見ているなど思いも寄らない煌成は、自分
が見てしまったあの夢に、伊純に対して少しだけ罪悪感を抱いていた。
罪悪感を持ってしまったのは、自分が思った以上に気持ちよさそうにしていたことと、
伊純が色っぽく見えてしまった所為だ。
天地がひっくり返ったってありえないが、もし現実にそんなシチュエーションになったら
本物の伊純もあんな顔をするんだろうかと、想像してまた罪悪感が膨れた。
俺はホモじゃない!と分かりきった否定をして脳内から伊純の映像を無理矢理かき消す。
煌成はいつもそうやって思考の迷宮から強制退去していた。
真桜と煌成がそれぞれの心情を抱えて正門前で待っていると藤と井沢が現れた。
真桜は井沢なんて来なければいいのにと小さく舌打ちしたが、井沢はやる気満々で、五感
を研ぎ澄ませているように見えた。
暫くして煌成達の前に現れたのは、白色のRange Roverで、そのゴツイ車体に似合わず
いつもどおりに穏やかな顔をして伊純が顔を出した。
「おはよう。みんな早いね」
「うひょー、先生カッコイイ!」
井沢が伊純と車を見比べて声を上げた。車から降りてくると、煌成は違和感を覚えた。
しかしそれは直ぐに解決した。真桜が上から下までじっと見て溜息を吐いて言ったからだ。
「先生、白衣姿じゃないと学校の先生じゃないみたい」
「そう?でも、先生じゃないってあんまり褒め言葉じゃないなあ」
「えー、これでも褒めてるよー。先生、すっごく若く見えるもん」
確かに、私服姿の伊純はいつもより若く見える。流石に出勤する時は白衣を着てないだろう
から、見ようと思えば白衣姿ではない伊純を目撃することも出来るだろうが、煌成は伊純
の私服を今まで見たことがなかった。白衣の殻を脱いだ伊純は少しだけ表情が柔らかく、
煌成にも優しい眼差しを向けてくれるような僅かな期待が膨らんだ。
「ありがとう。まだ若いつもりではいるんですけどね。・・・・・・さて、みんな揃ってるみたい
だし、行こうか」
煌成は後部座席に隠れるように座って、伊純のやや乱暴な運転に目を回したのだった。
「先生のお家、ここ〜!?」
「高級そうなマンション」
エントランスを通り抜けると生徒達は真新しいマンションに口を開けていた。
いかにも伊純に似合いそうなマンションに煌成も呆然としながら皆の後をついて歩く。
玄関の前まで辿り着くと、丁度部屋から女性が出てくるところだった。
「あら伊純、帰ってきたの」
「うん。今から出かける?」
「仕事ー、立て込んでて」
「じゃあ帰りは遅い?」
「そうね。適当にご飯済ませてくれたらいいわよ。・・・・・・伊純の生徒さん達?」
「うん、そう」
淡いピンクのスーツをきっちりと着こなした女性は煌成たちに軽く頭を下げた。
「こんにちは」
藤が礼儀正しく頭を下げると、他のメンバーももそもそと頭を下げた。女性はそんな姿を
品定めでもするかのように一瞥して、最後にニコっと笑った。
その笑顔につられて全員が顔を緩めると、女性はそのまま歩いていってしまった。
「先生の彼女?奥さん?」
小さな声で井沢が聞くと、伊純は一瞬きょとんとしてそして苦笑いした。
「姉ですよ。姉と2人で暮らしてるんです」
「へえ、美人なお姉さん!」
「・・・・・・似てないですけどね。さあ、どうぞ」
通された部屋を見て、生徒達はまたテンションを上げた。
一通り、部屋を探索したりお茶をもらったり、挙句の果てには何もしてないのに昼食に
突入してしまったりして、やっと本題に取り掛かれたのは、昼をちょっとすぎてからだった。
皆でリビングのクローゼットからダンボールを引っ張り出して、伊純の前任の学校の資料
を読み漁った。
「あ、ねえねえ藤君、この辺りとか使えそう?」
「見せて?・・・うん。そうだね」
真桜は計画通り藤の隣に座って、さりげないアピールを繰り返している。煌成は真桜の
面倒くさい「空気を読め」という指示を半ば放置して、ただ資料を見ていた。
井沢はそんな3人の姿を色眼鏡でじっくりと観察しているようだった。
4人がリビングで資料に埋もれていると、伊純がやってきて、生徒達を見下ろした。
「寝室のクローゼットにもう一箱あるんですけど」
「俺、取ってきましょうか?」
藤が立ち上がろうとして、伊純が手で制す。
「ちょっと高いところに無理矢理仕舞ってあるので、背の高い人の方がいいかも」
伊純に言われてメンバーが全員煌成を振り返った。
「はいはい、俺がすればいいんでしょ」
煌成はのそのそと立ち上がった。
「・・・・・・じゃあ、海老原君、お願いしますね」
伊純は顔が緩むのを我慢して煌成をリビングから連れ出した。
「これ?」
「そう。その上の」
「なんだ、全然先生でも届くじゃん」
煌成は重そうに顔を歪めながらも、さほど高くない位置に積まれたダンボールを引き出した。
「高いところのものはちょっとでも重いと大変なんですよ」
「・・・・・・うぇっ、ホント重い」
寝室のクローゼットから取り出したダンボールをそのまま床に置くと、煌成は大きく呼吸
を整ええた。
「リビングに運ぶの大変なら、ここで見てもいいですよ」
「へーい・・・・・・先生はこっち、手伝ってくれんの?」
まさかの煌成からのお誘いに、伊純の顔が緩みかける。目論見通りの展開に、妄想の中で、
煌成がとんでもないことになっているのを悟られないように、伊純は再び仮面をかぶり直した。
「・・・・・・わかりました。手伝いましょう」
ぶすっとした返事に、煌成はやれやれと首を振った。
関係ない「保健便り」の資料を除け、調査に必要な資料を抜き出し、煌成は真面目に仕事
をこなしていく。
伊純は不純な自分の妄想を申し訳なく思い、煌成と一緒に資料の山に手を伸ばした。
「・・・・・・先生?」
「・・・・・・何ですか?」
「先生ってさー・・・・・・」
歯切れの悪い質問に、伊純は身体を強張らせた。見られては拙いものが出てきてしまった
のだろうか。
「何でしょう?」
「・・・・・・なんで俺だけに冷たいかなあって思ってさ」
ふっと顔を上げると、煌成は資料に目を向けたままだった。
「つ、冷たい、ですか?」
「うん、すげー」
冷たくしているつもりなどない。心の声が駄々漏れにならないように自分を戒めている
つもりが、煌成には冷たく当たっているように思われていたのだ。
寧ろ誰よりも仲良くなりたいと思っている相手にそんな風に指摘されるとは、伊純も
動揺した。
伊純の手が止まっているのに気づいて、煌成も漸く顔を上げた。
「・・・・・・海老原君?」
「ひょっとして、先生自覚なし?」
「自覚なしっていうか、冷たくしてるつもりは全然ないよ。皆と同じようにしてるつもり
ですが・・・・・・」
「先生、それマジで言ってる?」
「はい」
煌成は呆れた顔で溜息を吐いた。
「・・・・・・マジかよ〜。先生、ちょっと酷くないそれ。俺だけ明らかに扱いが違うんだけど!」
「そう?・・・・・・そう思うのなら、海老原君に後ろめたいことがあるからじゃないの?」
冗談ぽく伊純が言うと、煌成はハイハイと言って手を振った。
「先生って時々、絶妙なタイミングで冗談言うよな」
「だから僕は生徒に人気があるんですよ」
伊純は益々冗談ぽく言って、全力で笑って見せた。今ここで煌成にこの気持ちを知られる
訳には行かない。まだ落とす道筋だって出来上がってないのに、土砂崩れなんてされたら
永久的に通行止めになってしまう。伊純は教師面を3枚くらい被った。
「とかなんとか言ってごまかしてるだろ、先生。絶対なんか裏あるんだよなー」
煌成は全然納得していないようで、ブツブツと文句を言っている。
「何にもないよ」
「簡単に見破れるとは思ってないから、気長にがんばるからいいよ」
「それ、どういう意味・・・・・・」
「こうなったら先生の裏の顔、見ないと気が済まなくなってきた」
覗かれた裏の顔がこんな妄想天国だと知られたら、煌成にドン引きされることなど想像に
難くないけれど、飛び込んで来られるものなら、このアリ地獄みたいな泥沼に身体ごと
溺れさせてしまいたいとも思う。
「伊純せんせーい」
伊純が何かを言おうとした瞬間、廊下から真桜の声が聞こえて、伊純はバネみたいに勢い
よく立ち上がった。
「はーい・・・・・・よ、呼ばれているんで行きますよ」
挙動不審になっていることはバレバレなようで、煌成も苦笑いして返事をした。
伊純が寝室から出て行くと、煌成は伊純のベッドに座って盛大に溜息を吐いた。
「敵城を落とすのはやっぱり一筋縄じゃいかないってーのな。でも、何か隠してるって言う
のはよーく分かったけど」
煌成は手にした資料を広げると、そのままベッドに仰向けにひっくり返った。
「海老原君もちょっと休憩にしましょう。お茶持って来ましたよ」
再び寝室に戻ってきた伊純を待っていたのは、おなかの上に資料を乗せたまま、眠りこけて
いる煌成の姿だった。
規則正しくおなかの上の資料が上下して、すっかり熟睡モードになっているのを伊純は
悟った。
「海老原君?」
声を掛けても、クウクウと口から寝息を立てている。伊純は思わず生唾を飲んだ。
後ろ手で寝室のドアを閉め、鍵まで掛けた。カチャリと生々しく鍵の掛かる音が響いて
伊純の心臓は跳ね上がっていく。煌成は起きる様子もなく、無防備に眠っていた。
一歩一歩慎重に近づいて、ベッドサイドにお茶を置くと、そっと煌成の隣に腰を下ろした。
ベッドのスプリングが沈んでも、煌成は動かなかった。
「海老原君」
伊純はもう一度名前を呼ぶ。返事はなく、その代わり煌成がうーんと小さく唸った。
寝顔のあどけなさと綺麗な骨格に、伊純の気持ちがドキドキからムラムラに変わっていく。
いけないと分かっているのに、手が伸びて、煌成の髪の毛を掬っていた。
「んん・・・」
くすぐったいのか、悩ましげな声が煌成から洩れてくる。半開きになった口元に伊純の意識
は奪われた。
「海老原、君」
伊純は先ほどよりも顔を近づけて煌成の名前を囁いた。掠れた声にも煌成は目を覚ます
ことはなく、伊純の顔はどんどんと煌成に近づいていく。
教師の仮面はぼろぼろと剥がれ落ち、そこにあるのは、目の前の若い青年を欲している
唯の男の顔だ。
気持ちを知られるわけにはいかないのに、どうしてこんな大胆なことをしているのだろう。
今目覚めてくれれば、起そうと思ったといい訳も出来る。早く目を覚ましてくれと焦り
ながらも、目の前に横たわるご馳走に涎をたらしているのは自分だ。
こんな行為は教師じゃなくても、卑劣で、自分本位過ぎると自覚はしている。けれど、
自分の欲望を抑えることが出来ず、伊純は吸い込まれるように煌成の唇に近づいていった。
「んっ・・・・・・」
触れ合ったのは一瞬。痺れに似た甘さが伊純を襲った。
――>>next
よろしければ、ご感想お聞かせ下さい
nakattakotonishitekudasai ©2006-2010 kaoruko since2006/09/13