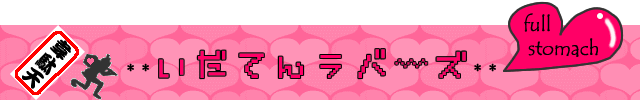
桜の季節はあっという間に過ぎ、セミの声が聞こえ始める頃になると、亜希の周りが少し
ずつ騒がしくなっていた。
1年から一緒のクラスメイトは素直に頷いて、
「高城、最近かっこよくなった」
と賞賛し、敦子達は、亜希の姿に感動して、
「痩せたら美少年って本当だね、きっと」
と早くもスリムの亜希を想像してはしゃぎ、
「やっば〜い。なんか惚れそうなんだけどー!」
新たにギャラリーに参戦してくる野次馬も増えた。
もともと、自分の容姿に頓着してなかった所為で太った亜希は、痩せて評価が上がっても
過度に反応することなく、相変わらずマイペースでダイエットを続けていた。
亜希が気にするのはただ一人、真野の視線だけだ。真野が自分に惚れたかどうか、それ
だけが亜希のダイエットを左右している。
すっかり、どっぷり真野に嵌っている自分を亜希は、糸の切れた凧みたいだと思った。
コントロールが効かない。自分の手元で引いたり緩めたり出来ればいいのに、上昇気流
に乗ってどこまでも飛んでいってしまう。真野への想いがどこまで膨らんでいくのか、亜希
は自分でも怖くなった。
「だって、毎日顔合わせてるんだから仕方ないじゃん」
自分にすら言い訳をしないとやってられないほど、自分の中で真野が溢れている。
真野と少しでも一緒にいたい。喧嘩しても一緒にいたい。悪口を言われても、足蹴に
されても一緒にいたい。
「俺、おかしいだろそれ」
自虐的に笑って、亜希は教室の窓から外を眺めた。
運動場では、隣のクラスが体育の授業をしている。その中に一人、長身の生徒がしなやか
な動作でグランドを駆け抜けていった。
(真野だ)
どこにいたって、一目で見つけられるのは、真野が目立っているからなのか、亜希の恋する
乙女パワーなのか。
真野の姿を見つけて、亜希はきゅんとこみ上げてくる気持ちを掌で潰した。
結局、真野とはクラスが別れてしまった。体育の授業で喧嘩することもなければ、クラス
が盛大にお祭り騒ぎでダイエットを盛り上げることも無くなった。
けれど、亜希はそれほど落ち込んだりしなかった。1年最後の日に約束したことを、真野は
律儀に守り続けているからだ。
日課のストレッチと筋トレに付き合い、更にダイエットノートには一言を欠かさず書いてくる。
その原動力が本当はなんなのか、亜希にはよくわからなかった。自分が痩せるか賭けを
したり、自分の挑発に面白がって乗ってきたり。真野は何を考えてるんだろう。
面白いから、飽きるまで付き合ってやると言った真野の心の内が亜希には見えない。
亜希は分からないからこそ不安で、分からないから痩せるしかなかった。
実際、真野は既に賭けなんてどうでもよくなっているし、挑発なんて、初めから負けて
いるようなものだったのだが、真野は気持ちを亜希以上に隠していた。
痩せた亜希が見たい。その気持ちが真野を動かしている。悟られたくないのはお互い様だ。
手を伸ばせばすぐそこにあるものに、亜希はまだ気づいていなかった。
体育館にもセミの声が鳴り響いて、暑さを3倍くらい膨らませていた。1学期の期末テスト
も終わって、授業が午前中でだけになると、午後一で亜希は扱かれていた。
午後の日差しが熱い風を体育館に運んで、立っているだけでもじとじとと汗が沸く程だ。
「あっつーい!アイス食べたい〜!」
亜希はスクワット50回を終えると、大粒の汗が床に落ちた。首に巻いたタオルで、顔の汗を
拭うと、亜希は力尽きたようにその場にどたっと座り込んだ。
「アイス?そんな高カロリーなもん食べたいなら、あと100回やれ」
相変わらずな口調で真野が言う。
「・・・・・・ちょっとくらいいいじゃん!」
「ちょっとが重なって、今のお前があるんだろうが。デブはみんなそう言うんだろ。ちょっと
くらい食べたって平気。全然ちょっとじゃない」
「・・・・・・いいじゃん、最近ちょっと痩せてきたって皆も言ってくれるしさ〜」
「ふうん?これのどこら辺が、痩せたって?」
真野はわき腹を掴むと、波を立たせるみたいにその肉を揺らした。
「止めろよ」
亜希は身体を捩って、真野の手から抜け出す。屈辱的な事をされたはずなのに、触れられた
だけで亜希の身体は熱くなった。
「お前が55キロになるまで、手加減しないからな」
「うっさい。ちょっと言ってみただけだ!」
亜希は半年前よりもかなりすっきりした頬を丸く膨らませて拗ねた。
俯くと二重顎になっていた顎も以前よりシャープになり、真野が感触を楽しむほどあった
肉もあまり目立たなくなった。
わき腹だって、ダイエット始めた頃よりも、はるかに引き締まった。腹回りの肉がなく
なったとは言えないけれど、真野が呆れるほどの脂肪はもうない。
色々なダイエットを試してきたけれど、結局最後は、真野の言うとおり、身体を動かす
しかなかったようだ。
亜希はマッタリした気分になりつつ、体育館の壁に掛かる時計を見上げた。
いつもなら部活が始まる時間なのに、バスケ部の面々は誰一人体育館に来ていない。
「あれ?今日、部活は?」
「今日は海」
「海?!」
「砂浜で筋トレ」
亜希達の学校は海岸近くに建っていて、10分も歩けば海に着くのだ。それを利用して多く
の運動部が砂浜でのトレーニングを導入している。
「うげぇ」
「今年の一年は体力無いヤツばっかりで、鍛え直しなんだよ。そうか。お前も来い」
亜希は砂浜のマラソンを想像して首を横に振った。
冗談じゃない。そんなスポ根に付き合えるか。
「やだよ!!」
「痩せるぞ」
「今日はもうこれで十分だ!!」
「‥‥‥まあいいから来い」
嫌だと言ってるのに、真野は亜希を足蹴にして催促した。
「嫌だってば」
亜希はぶうたれて、真野を睨み上げた。なんでバスケ部員でもない自分が海なんか行か
なくちゃならないんだ。
海なんて‥‥‥海なんか‥‥‥海、か。
海・・・・・・。
亜希は突然乙女スイッチが入って妄想の住人となった。
海といえば、ラブロマンスじゃん。
真野と海を眺めながら、語ったり、あわよくば告白しちゃったり?そんなウフフな展開
があるかもしれないのが海ってトコだ。
夕日の砂浜を真野と駆け抜ける一昔前のドラマのシーンを思い浮かべて、亜希はムフフと
心の中で笑った。
真野に頭の中を覗かれたら筋トレだと突っ込まれそうな暴走妄想を亜希は天秤にかける。
真野と浜辺デートを取るか、筋トレ地獄からの脱出をとるか。
天秤はぐらぐら揺れた。
「いいから来い。やれば、アイス1個くらいなら食えるくらいは消費できるぞ」
「アイス!」
浜辺デートにアイスがプラスされて、天秤は、がこっと傾いた。
「‥‥‥仕方ないなあ。行ってやるよ」
最後の決め手は甘い食べ物。結局食いしん坊亜希は、食い気に負けた。
夕焼けが海を赤く染めて、キラキラと光る波が目を閉じても瞼を刺激した。背中に伝って
来る砂浜の熱は未だ熱い。じりじりと背中が焼けるようだったけれど、亜希は起き上がる
事ができなかった。
「‥‥‥いつまで寝てるつもりだ」
真野に声を掛けられて、亜希はだるそうに目を開けた。
「‥‥‥真野に・・・・・・騙された・・・・・・」
未だ息が整わない。額に浮かび上がる汗は次々と砂浜へ滑り落ちていく。胸が激しく上下
して、酸欠状態の脳みそは倒れているのに更にクラクラした。
砂浜マラソンは平地のマラソンと比べ物にならないほどきつかった。ただでさえマラソン
嫌いなのに、こんな足を取られる砂浜でなんで走らなきゃならないんだと、亜希は始まって
3分も経たない内から文句を言い続けた。
けれど、その文句もすぐに出てこなくなった。あまりに辛すぎて、口を開くのも出来なく
なってしまったのだ。
バスケ部員と同じだけ走らされて、亜希はそこでぶっ倒れた。
どこがラブロマンスだ。どこが青春だ。真野の腐れ野郎。
完全な八つ当たりで、寝転がったまま真野を睨みつけると、真野は薄暗くなった景色の
中に溶けてしまいそうなほど小さく笑った。
「高城にしては、よくやった」
珍しく褒められて、一瞬の間が出来た。
乱れた呼吸もぴたりと止んで、その代わり心臓が更に早く波打った。腐れ野郎は撤回
してやろう。
「アイスは無いけど、これで我慢しろ」
いきなり視界に現れたのは自販機で買ってきたらしい冷えたお茶だった。
真野はそれを亜希の頬に当てた。キンと冷たい感触が頬を冷やす。自分がどれだけ火照って
いるのか亜希は実感した。
「ありがと・・・・・・」
真野からお茶をもらって暫くその冷たさを味わった。それから、重い身体を起こそうと
力を込めた。
「あ、れ・・・・・・」
身体が言うことを利かない。腕がプルプルと震えて、途中まで起き上がらせた身体が再び
砂浜に埋もれた。
「なにやってんだ」
「だって・・・・・・起き上がれないんだよ」
真野にため息を吐かれて、亜希は口を尖らせた。けれど、意外な行動が亜希を待っていた。
真野は亜希に向かって手を差し伸べてきて、亜希は尖らせた口が半開きになって、干からびた
蛸みたいに不細工な顔になってしまったのだ。
「はやく、手出せ」
真野の差し出された手におずおずと捉まると、亜希は信じられないくらい強い力で一気に
引っ張り上げられる。
世界がやっといつもの視線に戻った。
「真野って力持ち」
「重い!!」
「いい筋トレになるだろ」
「重すぎて腰痛める」
真野はふんと鼻を鳴らした。
「あー、喉カラカラ」
亜希は服や髪の毛についた砂なんてお構いなく、真野のくれたお茶を飲み干した。
夕焼けが次第に濃くなって、太陽が水平線の彼方に食べられていく。その光に照らされて
真野の小麦色に焼けた肌がキラキラと光った。
「・・・・・・みんなは?」
「お前がここでくたばってる間にとっくに帰った」
「え?」
振り返れば、バスケ部のメンバーは誰一人残っていなかった。
「高城死んだんじゃないかってみんな呆れてた」
「こんなにきついなんて、詐欺だ」
亜希が文句を言うと、真野は組んでいた腕を外して亜希の隣に座った。
「・・・・・・お前、砂まみれだな」
真野が亜希の柔らかい髪の毛に手を伸ばす。乾いた砂がばらばらと髪から剥がれ落ちた。
「あー、もう。ホント最悪。こんな砂まみれだし、じゃりじゃり気持ち悪い」
「さっさと帰って風呂でも入れ」
「言われなくてもそうするよ!」
亜希は真野を振り向かず、沈んでいく太陽を眩しそうに見つめて言った。
夕日が揺れながら姿を消していく。完全に消えてしまうまで、2人は暫く無言でそれを
追っていた。
静かになると、波の音が心地よく耳に届く。ずっと波はあったはずなのに、波の音を
聞いている余裕すらなかったのだと、亜希は驚いた。
波の音がどんな効果をもたらすのかよく分からないけれど、耳を傾けていると、どんどん
まったりとしてきて、無言の間はますます広がった。
真野がその沈黙を撫でるように柔らかく破った。
「高城がここまでやれるとは思わなかった」
「・・・・・・」
「結構根性あるよな、お前」
「い、今頃分かったの」
「初めなんて、ただのダメなデブだったじゃないか」
「お前、俺になら何言っても許されると思ってない?」
「思ってるよ」
「なっ・・・!」
「これくらいのことで、高城は沈まないだろ。沈ませても、沈ませても、すぐ浮かんでくる。
ああ、そうか。デブは浮力があるからか」
「真野!!」
亜希は手元の砂を握り締めると、それを真野に向かって投げつけた。けれど、さらさらと
指の間から抜け落ちて、真野のところには届かずに、微かに吹いていた潮風に消えていく。
ザザ。波の音がまた2人を包んだ。
「・・・・・・お前、本当に55キロまで痩せられるかもな」
「ちょっと信じてないのかよ!」
「お前の事は信じてなかったけど、俺が協力してやってるんだから無理でもやらせるけどな」
「どんだけ偉そうなんだよ、お前は」
薄暗くなっていく中で、真野の横顔も闇の中に溶けていきそうになる。
「・・・・・・まあ、がんばれよ」
真野は珍しく、亜希を励ました。波の音と一緒に亜希の耳の中でそれはこだまし続けていた。
別れ際に真野はノートを手渡していった。いつものダイエットノート。時にぞんざいに
扱われて、隅がぼろぼろになっているが、これが2人の絆のようで、亜希は大切にノートの
表紙を撫でた。
電車が来るまで、あと数分。今日はどんな言葉を残してくれたのか、はやる気持ちを抑えて
亜希はページを捲った。
一番新しい記録に目を落としたとき、丁度電車が駅に滑り込んできた。
吐き出された乗客に亜希は思いっきりぶつかる。けれど、それを避けることもせず、亜希
はただ、そのノートを凝視していた。
「真野・・・・・・?!」
真野の一言の最後の文字を追って、亜希は固まってしまった。
どういう意味なんだろう。不安が黒い雲のように心を一気に陰らせる。嫌な予感がした。
「電車出発します。黄色い線までお下がりください。駆け込み乗車は危険です」
駅員のアナウンスが構内に響く。
亜希の前を電車がゆっくりと走り出していた。
□□亜希のダイエット記録□□
7月某日――ダイエット270日目
実行中のダイエット:地獄の筋トレ+ストレッチ
朝食:ご飯、味噌汁、サラダ、ヨーグルト
昼食:購買のコロッケパン。今日は我慢して3つ!
夕食:冷やし中華(母さんが手抜きのため)
体重:67.5(暑い・・・・・・アイス・・・・・・高級アイスを食わせろ・・・・・・)
一言:とにかく、唐揚げと焼き肉は禁止。肉が食いたかったら豚かササミでも食え。
スナック菓子も当たり前だけど禁止。アイスは論外。アイスの存在は忘れろ。
あと、筋トレはサボってもストレッチは忘れるな。特に腰周り。1ヶ月分のストレッチ
と筋トレのメニュー書いておくからな。
――俺がいなくなっても、ちゃんとやれよ(真野)
――>>next
よろしければ、ご感想お聞かせ下さい
nakattakotonishitekudasai ©2006-2010 kaoruko since2006/09/13