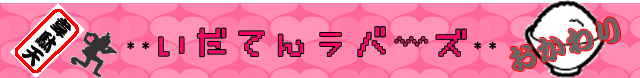
「・・・・・・亜希ちゃん、また太ったの?」
美咲が目をクリクリさせて亜希の姿を眺めた。殆ど毎日顔を合わせている所為で、100グラム
200グラムの体重増減なんて分かるわけもない。
「ううん・・・太ってない・・・っていうか、寧ろ減ってる・・・・・・」
「じゃあ、会わないってどういう意味よ」
「その・・・色々あって・・・・・・」
「亜希ちゃん、2週間以上も前に55キロまで減ったって自信満々で言ってたよね?これで
真野君に負い目無く戦えるとか。真野君に言ってないの?」
「・・・・・・うん。実は・・・言ってない・・・・・・」
もじもじと身体を動かす亜希を見て、美咲は長年一緒にいる勘で、亜希が何を躊躇っている
のか察した。
「分かったー。亜希ちゃん、怖いんでしょ」
「ええ?!」
過剰な反応を示す亜希に苦笑いする。
「55キロになって、真野君との今の関係が変わるのが怖いんでしょ」
なんだ、そっちか。
呟いたつもりが、美咲の耳にはしっかり届いていた。
「そっちって、どっちよ」
「あ、いや。うん。まあ、大きく言っちゃえばそう言う事」
言葉を濁して、美咲の探るような視線をかわした・・・・・・つもりだった亜希だが、美咲は別に
そこまで追い詰める気も無かったので、心の中で納得してそれ以上は突っ込まなかっただけだ。
「亜希ちゃん考えすぎよ。55キロになったからって、何もかもが急転するわけじゃないでしょ?」
「そうだけど・・・」
「亜希ちゃんの体重が4年間かけてゆっくり減っていったように、これからの関係だって、
ゆっくり変わって行くと思うけど」
「そうかなあ」
「そうよ。真野君だって、少しは変わったでしょ?」
「何処が?全然だよ。4年経ったって、あのドS体質は何にも変わってない!」
「でも、この前亜希ちゃんの事「高城」じゃなくて「亜希」って呼んでたよねー。あれいつ
から呼ばせてるの?」
美咲が意地悪そうにニコっと笑うと、亜希は手元にあったタオルで顔を拭きまくった。
「よ、よ、呼ばせてるとか!違うって・・・なんか知らないけど、大学になったら急に真野が
そう呼びはじめて・・・・・・」
分かりやすい狼狽の仕方だと美咲は笑い転げた。
「うれしいんでしょ」
「べ、べ、べ、別に!」
若干どころか、茹蛸くらい赤くなって、亜希は絶えられず立ち上がった。
「か、帰る〜」
「もういいの?」
「いい!自分で、考える!」
「はいはい。じゃあそうして。死んじゃいそうなくらい辛くなったらまたおいで」
「・・・・・・そうする!」
亜希はよくわからない返事をすると、美咲の部屋を出た。
美咲の部屋を出ると、ムーンウッドの店舗のところで亜希は声を掛けられた。
「あれ、亜希君来てたんだ」
見ればカウンターの中で、真っ白な白衣に身を包んだ青年がこちらに手を振っていた。
「あ、結貴(ゆうき)さん。こんちは」
結貴と言うのは、この店で働いている青年だ。亜希が中学3年のときに専門学校生のバイト
としてやってきて以来、そのまま就職してしまった人で、亜希もよく知っている。
今では仕上げまで任されている美咲のおじさんにも信頼されている人物だ。
「おじさんは?」
「厨房だよ」
「そっか。俺、そろそろ帰るんで、宜しく言っておいてよ」
「うん。あ、そうだ。ちょっと待ってて。・・・・・・ゼリーの試作があるんだけど、よかったら
食べてみてよ」
結貴はそう言うと、奥の冷蔵庫からゼリーを2つ出してきた。
「えっと・・・」
「あ、ダイエットしてるんだっけ?」
「うん、まあ・・・」
「そっかー。残念だなあ。秋の新作に向けて、亜希君の感想が聞けたらって思ったんだけど」
「結貴さんが作ったの?」
「そうだよ」
見れば、ゼリーの上に果物がキラキラと輝いている。
ごきゅん、亜希は思わず唾を飲み込んだ。
それから、自分の体重と、自分の置かれた状況をぐるぐるかき混ぜてみて、
「ちょっとくらいなら・・・」
とおずおずと手を差し出していた。
「ホント?嬉しいなあ。亜希君、舌が肥えてるから、また感想聞かせて」
「うん。ありがとう」
55キロ切ったし、どうせ真野とは3週間会えないんだし、これくらい食べても罰当たらない
だろうと亜希は、上機嫌でムーンウッドを後にした。
学生の夏休みは朝が遅い。ただでさえ朝寝坊気味の亜希は夏休みに入って、真野にも
会えないときてからは、10時前にベッドから起き上がったことが無い。隣市の大学に通って
いるので、真野は一人暮らしをしているが、亜希も美咲も自宅生で、今朝もだらだらと
自分のエアコンの効きまくった快適な部屋で惰眠を貪っていた。
亜希が身体を起こしたのは、外から聞こえてくる美咲の声だった。
「お父さん、大丈夫!?・・・・・・歩けるの?寝てた方がいいんじゃない?・・・運転?!馬鹿な
事言わないでよ!こんな身体でどうやって・・・・・・」
亜希は何事かと窓から外を覗くと、美咲の父がよれよれと車に乗り込むところだった。
一気に目が覚めて、慌てて着替えて外に出て行くと、そこには美咲たちの姿はもうなく、
結貴が複雑な顔をして見送りをしていたところだった。
「亜希君、おはよう」
「結貴さん!おじさん、どうしたの!?」
「ぎっくり腰みたい。動いちゃダメだって言うのに、早く直さなきゃいけないからって、
自分から病院行くって、強行してちゃったよ」
「おじさん、ぎっくり腰?!大丈夫かなあ・・・」
「暫くは安静だろうね。はー、困ったなあ」
「お店どうするの?」
「僕がやれる商品だけで回してくことになるかな。美咲ちゃんも奥さんも店長につきっきり
になりそうだし・・・・・・」
「そう・・・。おじさん大丈夫かなあ。あ、俺で手伝えることがあったら、何でも言ってよ。
夏休みでどうせ暇だしね」
「ありがとう。そう言ってもらえると心強いな」
「でも、あんまりハードルあげないでね。俺、ホント料理とか出来ないから・・・・・・」
あははと頭を掻くと、結貴もそんなことは分かっているようで、柔らかい笑みを湛えながら
「とりあえず、新作の評価を沢山してもらえるといいな」
と言った。
「そんなことなら・・・・・・大得意ですから」
亜希もニヒヒと笑った。
その日から、亜希は美咲のいない時間でもムーンウッドに顔を出すようになっていた。
「亜希ちゃん、結貴さんの手伝いしてくれてるってホント?」
「手伝いって程でもないけど・・・」
「なんだか悪いわね。バイト代、あとでお父さんに請求してもいいよ」
「いいよいいよ!俺が勝手に出入りしてるだけだから・・・。それより、おじさん大丈夫?」
「口だけは元気よ。店がどうなってるのか気になって仕方ないんんだけど」
美咲の父は、病院に送られた後、美咲の母の実家に強制的に連れて行かれた。家に帰したら、
意地でも店に立つと言い出しかねないのを母親が先回りして、幽閉したのだ。
母親の実家は美咲の家から車で10分程度のところで、何かあれば直ぐに駆けつけられる
けれど、ぎっくり腰の人間には到底行くことのできない、当にうってつけの場所だった。
「それで、こっちに帰ってこなかったんだ・・・入院でもしてるのかと思った」
「ううん、全然。実家で肩身の狭い思いしてるわ」
美咲は鼻をふんと鳴らした。
「おじさん働きすぎだから、たまには休むのもいいんじゃない?」
「うん。みーんな同じこと言ってるわよ。本人だけは納得してないみたいだけど。結貴さん
には負担掛けちゃうけど、この際ちょっと休んだほうがいいわ」
「そうだね。俺も全然役に立ってないけど、何かあれば手伝うから・・・・・・」
「ありがと。・・・・・・でも、家に入り浸って、甘いものに手を出しすぎないようにね」
「え?」
「・・・・・・ちょっと太ったでしょ」
「わ、かる・・・?!」
「顔がちょっとふっくらしてる。甘いもの止めた身体って、吸収がいいってホントなのか
しら。気をつけたほうがいいわよ。体重計乗ってる?」
「・・・・・・あれから、乗ってない・・・・・・」
美咲に呆れられて、亜希は内心焦った。
ムーンウッドに顔を出すと、結貴がなんだかんだで必ずケーキを出してくれるのだ。
1個くらいは・・・今日だけは・・・・・・これくらいなら・・・・・・そう思いながら、どれだけのカロリー
を摂取してきたか。
亜希はハラハラしながらその夜体重計に乗った。
「ご、ごじゅうろく・・・・・・?!」
真野には55.2から減っていないと嘘を吐いていたけれど、実は亜希の体重は54キロ近くまで
落ちていたのだ。それがここ数日で一気に2キロも増えてしまった。
「や、やばい・・・・・・」
亜希はカレンダーに目をやった。真野の合宿が終わるまであと2週間あまり。
そうか。2週間もあるのか。
そう思った時点でダメだということを、亜希は分かっていない。この余裕が、後で自分
を苦しめることになるというのに。
「・・・・・・まあ、2週間あれば1キロくらい、余裕!」
亜希はほんの少しふっくらとした白い肌をぴよんと摘んで楽観的に笑った。
「亜希君、手伝いありがと。今日はもういいよ。いつもありがとう」
「全然いいよー。俺もムーンウッドのケーキ大好きだし」
「あんまりお礼にもなってないけど、売れ残っちゃったの持ってく?」
「・・・・・・」
「どうしたの?」
「きょ、今日は・・・止めとく」
亜希は物欲しそうな視線のまま、無理矢理言葉をひねり出した。
「なんで?!おなかでも壊した?」
「えっと・・・ちょっと、最近ケーキ食べ過ぎちゃって・・・・・・」
「ああ、そっか。亜希君、ダイエットしてたんだっけ。そっか」
「まあそんなとこです。せっかくくれるっていうのに・・・・・・」
「仕方ないね。でも亜希君は、もっとぽっちゃりしてた方が可愛くていいよ」
「え・・・?」
「ぽっちゃりしてた頃の亜希君、血色もよかったし、可愛かったし、何よりあんなにおいし
そうにケーキ食べてくれて、僕は好きだったんだけどなあ・・・・・・」
呟かれて、亜希は返答に困った。
「可愛いって・・・」
「人間って、ぼっちゃりしてる方が絶対可愛いと思うよ。男の子でも女の子でも」
「そ、そうかな・・・・・・」
「ほら、高校に入学したての頃の亜希君とか、ぷりっぷりの肌で、見てて気持ちよかった
もん。ああいう子がガツガツケーキ食べてくれるとうれしいよ。今じゃこんなに痩せちゃって
勿体無いなあって、ダイエットしてる亜希君には怒られそうだけど、正直なところ、そんな
こと思ってた」
「ふ、太ってた方がよかったってこと?!」
驚いて亜希が結貴を見返すと、結貴ははにかんだように頷いた。
世の中には、変な趣味の人がいると思う。真野が自分を選んだことも相当変だとは思って
いるけれど、太っていた方の自分の方がよかったなんていう人間はもっと変だ。
昔、真野に言われた台詞が蘇る。
「さっさと痩せろ!今のお前なんかを認めるやつは、D専だけだ!」
「D専?!何それ!」
「Dって言ったら、デブのDに決まってるだろ!」
「ひどい!」
「ひどいのはお前のその腹の肉だ。そのたるたるした腹をさっさと無くせ」
あの後、真野に腹の肉を思いっきり引っ張られたのだ。そんなことまで思い出して、ふっと
結貴を見た。
えっと・・・・・・その・・・・・・もしかして、真野の言う、で、で、D専・・・・・・の方?
あんぐり開いた口が、ぱくぱくと動いても声にすることは出来ず、亜希は餌を欲しがる
金魚みたいになっていた。
「なあに?」
「えっと、あの・・・俺は・・・・・・もう、あんなに太りたくないっていうか・・・せっかく痩せた
のに、またあれになるのは・・・・・・」
「あはは、ごめんごめん。別に亜希君に太れなんて言ってるわけじゃないから」
「そ、そう?」
「うん。ただそう思ったってだけ。まあ、ちょっとくらい太っても気にしない人もいるって
ことだよ。だから、はい。お土産。これくらいなら大丈夫でしょ」
そう言って結貴が渡してきたのはムーンウッドの売れ筋ケーキ3つ。
これくらい・・・・・・なら・・・・・・いいんだろうか。
「・・・・・・あ、ありがとう・・・・・・」
それくらいしか言えず、亜希はあははと引きつった笑いでムーンウッドを後にした。
それから2週間。
結貴の誘惑に負けに負けた亜希を待ち受けていたものは、思わず目を逸らしたくなる
体重だった。
「ご、ごじゅうなな・・・・・!」
どうしよう!どうするんだ、亜希!真野はもう直ぐそこまで帰ってきてるんだぞ。
セルフ突っ込みも虚しく、亜希は体重計の前でたらりと冷や汗を垂らしていた。
――>>next
よろしければ、ご感想お聞かせ下さい
nakattakotonishitekudasai ©2006-2010 kaoruko since2006/09/13