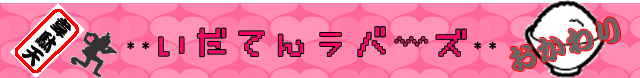
自分ほど間の悪い人間はいない。今日ほど自分の運の無さを呪ったことはないと、亜希は
目の前の光景を見ながら呆然としていた。
8月も後半。暑い中、気まぐれで出かけた駅前の本屋の前をちょうど通りかかったとき
だった。
「亜希」
名前を呼ばれて、猫がびっくりしたときみたいにぴょんと跳ねたのは、その声に聞き覚え
があることと、今その声の持ち主に一番会いたくなかったからだ。
「・・・・・・亜希」
二度呼ばれて、亜希は恐る恐る振り返った。
「やあ、真野君。お久しぶり。合宿はどうだったかね」
上ずった声で切り返すと、真野は不審な顔で亜希を見下ろした。
「・・・・・・お前、なんか・・・?」
「何!?何にも変わってないよ!?」
明らかに動揺した声で亜希は自分の腹回りを押さえた。
それが墓穴というのよ、亜希ちゃん。
美咲が見ていたら絶対に突っ込まれそうなことを亜希は思わず口走っている。
「ふうん。・・・・・・久しぶりじゃん」
「真野こそ、合宿で、焼けまくり」
「引き締まった筋肉が見たい?」
「誰もそんなこと言ってない!」
「まあ、遠慮するな。うちまで近いし、ちょうどいいから来い」
「え、いいよ。遠慮しとくって・・・・・・お、俺、急用あるし」
やばい、逃げなきゃ、亜希の本能が生命の危機だと訴えている。いくら、好きな真野と
言えど、今はのこのこと真野の家についていくわけには行かないのだ。
亜希の身体を4年間もの間こまめにチェックしていた真野がこの僅かでもデカイ体重増加
を見逃してくれるわけが無い!
亜希は「母さんに大至急醤油を買って来いって言われてるんだ〜」と吐くならもう少し
マシな嘘を吐けと言われるような、嘘を吐き捨てて真野の前を通り過ぎようとした。
「・・・・・・」
真野の前を、一歩、二歩。よし、今だ。走って逃げよう。そう思った瞬間、亜希の腕は
ガッツリと真野に掴まれていて、気持ちだけが前のめりになった。
「ちょっ、わっ、おうぅ!」
「何で逃げるんだ、お前は」
「逃げてなんてない!俺は、母さんに頼まれた用事が!」
「醤油くらいなくても料理くらい出来るだろ」
「あ、そうだ!今週号のジャンプーを買って来いって、兄ちゃんが!」
「小一時間くらい読まなくても、死にはしない」
「あ、違う!えっと・・・じいちゃんが」
「お前は何回じいさんを殺せば気が済むんだ?」
「・・・・・・じゃ、じゃあ・・・・・・」
もはや、嘘もバレバレのレベルになっても、亜希はまだ逃げ出そうとしている。真野は頭
の弱い恋人に半分呆れて、苦笑いになった。
「もういい。とにかく来い。お前は久しぶりに会ったのに嬉しくないのか」
「え・・・・・・」
そりゃあ嬉しいですとも。2キロ分のお肉が無ければ。
亜希の中の2キロ分の贅肉――主な成分はムーンウッドのケーキ――が全力で真野を拒んで
いるのだ。
困惑の表情で見上げた亜希を真野は有無を言わさず引き寄せた。
「家でたっぷり聞いてやるよ。俺がいなかった間の事」
「はいどうぞ」
部屋に入って差し出されたのは、カラカラに乾いた喉を潤してくれるお茶でも、汗を拭き
取るタオルでもなく、体重計だった。
「・・・・・・!」
入ってきていきなりそれは失礼だろと亜希が反論の目で真野を睨むと、真野は平然と言い
放った。
「お茶でもコーラでも飲んでもいいけど、それだけ更に体重増えるだけだけど?」
「そうじゃなくて!なんで今体重計に乗らなきゃならないんだよ!」
「いい訳より先に事実確認だから」
「事実確認って・・・・・・」
真野は亜希の後ろに回ると、気持ちふっくらとした頬と腹の肉をダブルで抓った。
「俺の記憶には、こんなモノ無かったんだけど。何これ」
「うっ・・・」
「3週間でこんなによく太れるなあ」
「う、うるさい!・・・って、あっ!止めろっ」
亜希が喚いているうちに、真野は亜希の身体をひょいと持ち上げて、体重計の上に乗せて
しまった。
「・・・・・・」
「・・・・・・」
デジタルの表示がぴたりと止まって、その数値を無言で見下ろす。
「57.3、か」
冷たい声が頭の上から降ってきた。
「ふ、服着てるから!」
「どうぞ。脱ぎたきゃどれだけでも脱げ」
「体重計、壊れてるんだ!」
「お前、何処まで往生際が悪いんだ?」
「・・・・・・って」
「この3週間、お前何食ってきたんだ」
「それは・・・」
言い淀んでいる亜希に、真野は後ろから亜希のお尻をぱあんと叩いた。
「痛っ!」
「ああ、いい、いい。どうせ、隣のケーキ屋だろ」
「だって・・・・・・」
亜希が言い訳をしよと真野を振り返ると、真野は意外にも傷ついた顔をしていた。
「真野・・・・・・?」
「お前、そんなに55キロになるのが嫌なのか」
「!?」
そういうわけじゃない。それとこれとは亜希の中ではまた別の話で、太ったのは何にも
考えずただ誘惑に負けただけの事だ。
「そんなに、俺と・・・・・・」
言いかけて、真野はきっと口を結んだ。俺と繋がるのがそんなに嫌なのか、思わず弱音を
洩らしてしまう自分にも嫌気が差したのだ。
「なんだよ・・・」
「別に。もういい。お前の事はよくわからんけど、お前の態度がどういうつもりなのかは
よくわかった」
「真野〜!?」
「お前みたいな、ダメなヤツに期待した俺が馬鹿だった。あー、疲れた。お前、もう帰れ」
「ちょ、ちょっとぉ〜!?なんだよ、確かにちょっと太った俺が悪いかもしれないけど
人を連れてきておいて、それはないだろ」
「お前みたいなヤツみてると、ムカムカすんだよ」
その言葉の裏側を読み取るだけの余裕は今の亜希には当然無い。
デブだの馬鹿だの罵られていた頃の記憶が一気に蘇ってきて、亜希は一気にぷちんと
切れた。
「なんだよ!真野の馬鹿!」
「はあ?!」
「どうせ、俺なんかダメなヤツなんだよ!お前みたいに頭もよくないし、スポーツも出来
ないし!そんなに、ムカつくなら俺なんかに構うなよ!」
「ココに来て逆切れかよ」
「うるさい!真野は、俺に理想ばっかり押し付けて、それに俺が嵌らなきゃ気がすまない
んだ!」
「そんなこと言ってないだろ」
「俺はお前のおもちゃじゃない!」
どうしてこういう展開になってしまうんだと、亜希は自分の口から出てくる言葉が止め
られなかった。
「お前、俺の事そんな風に思ってたのか?!」
「思ってないよ!でも、そうなんだろ!!」
「・・・お前、本気で馬鹿か」
真野が豪快に溜息を吐く。その姿を切れ気味に見詰めると、
「もういい!お前なんて、知らない!」
そう言って亜希は涙目になりながら、アパートを飛び出していた。
真野の制止を振り切ってしまったことも、何度も呼び止められたことも全部頭の外に
吹っ飛ばして、亜希はひたすら走って逃げた。
亜希が家に着くと、丁度ムーンウッドから結貴が出てくるところだった。
「あれ、亜希君?」
「・・・・・・こ、こんにちは。今日はもう閉店?」
「うん。そう。・・・どうしたの、目真っ赤だよ?」
「え?」
亜希は慌てて顔を擦った。なんでもない風を装うことにかけては、3歳の子どもだって騙せ
ないほど、嘘が下手な亜希は、「なんでもないです」といった瞬間に結貴に
「なんでもないって顔じゃないよ」
と指をさされてしまった。
「・・・・・・」
「辛いことあったら、甘いもの食べるといいよ」
今はそれが一番辛いことなのだ。結貴は自分が持って帰るはずだったケーキの箱を亜希に
差し出したが、亜希はそれを受け取れなかった。
「・・・・・・」
「食べたくない?」
「や、そういうわけじゃ、ないんだけど・・・・・・」
ケーキを作った本人に食べたくないというのはとても失礼な気がするし、かといって受け
取るわけにも行かず、亜希は察してくれ!と眼力を込めたが、結貴がキャッチしたのは
更に奥深いところの電波だった。
「分かった。ダイエットの事で、彼女と喧嘩でもしたんでしょ?」
正確には彼女ではないが、この際そんな些細なこと(亜希比)はどうでもいい。
それだけ分かったのなら、もうケーキなんて勧めないで欲しい、と更に目で訴えると
結貴はその視線を無理矢理曲げに掛かってきた。
「別に亜希君、太ってるようには見えないけどなあ。ムーンウッドのケーキ、自信作ばかり
だから、亜希君の彼女も一度食べてみれば、ちょっと位は寛大になってくれると思うんだ
けど」
「・・・・・・ケーキとか好きじゃないんで・・・・・・」
真野がケーキなんて食べてるところ見たことが無い。
「そっか。それじゃあ辛いね」
「・・・・・・うん。・・・・・・俺、ちょっとミサちゃんとこ寄ってくんで・・・」
そう言って、亜希が結貴から離れようとすると、結貴が亜希の腕を取っていた。
「ん?」
「美咲ちゃんは今日はいないよ。店長のところ。相談があるなら、僕でよければ聞いて
あげるよ?」
「いや、えっと・・・」
「ウチのアパート、そんなに遠くないし、おいでよ」
やけに強引に肩を掴まれて、亜希は返事もしないうちに結貴と共に歩き始めていた。
「亜希君の彼女は、亜希君の本当のよさをわかってないなあ・・・」
結貴の呟きは夕暮れの空に消えていった。
結貴のアパートは歩いて10分もしないところにあって、1LDKのこざっぱりした部屋だった。
部屋に入ると、リビングの本棚には製菓の本がずらりと並んでいて、リビングテーブルの
上にも数冊、お菓子の本が置かれていた。
「適当に座ってて。お茶入れてくるから」
「・・・・・・うん」
亜希はどうしてこんな展開になってしまったのか、よく分からないまま、居心地悪げに
クッションを抱きながら座った。
手持ち無沙汰でテーブルの上の本をペラペラと捲る。出てくるケーキに思わず見とれて
いると、アイスティーとムーンウッドの残りのケーキを持って結貴が亜希の隣に座った。
「お菓子やケーキの本があるとついつい買っちゃうんだよね」
「・・・・・・おいしそう」
「食べたかったら、どうぞ?」
差し出されたのは、さっき断ったケーキだ。ムーンウッドの残りのケーキが4つもお皿の上
に並んでいる。本の中のケーキを見て、それからもう一度ムーンウッドのケーキを見た。
試されてるのか。亜希は誘惑に負けそうになるのを我慢して・・・・・・したはずで・・・・・・
「ひ、一口だけとかでも、いいですか・・・・・・」
「どうぞどうぞ。全部味見してってもいいよ」
ごきゅん。亜希の喉がなった。
手がフォークに伸びる。一口だけなら・・・・・・嘗て陥った罠にまたも亜希は嵌ってしまった。
真野と喧嘩してることも、その原因が自分の体重増加にあることも・・・・・こんな風に意思の
弱いことを悔いたことも、ケーキの前では全て無効だ。
いっただっきまーす、と音符マークでもつきそうな勢いでショコラに手を伸ばしかけた
時、いきなりインターフォンが鳴った。
びっくりして亜希の手がそこで固まる。
「誰だろ」
結貴が玄関に向かうのを、亜希は目で追った。ケーキ、食べてもいいのかな、と止めた手
を動かそうとして、亜希は更に固まった。
結貴が玄関を開けた瞬間、よく通る声で名前を呼ばれたのだ。
「亜希、いるんだろ」
「!?」
びっくりして振り返ると、玄関の向こうに立っていたのは真野だった。
――>>next
よろしければ、ご感想お聞かせ下さい
nakattakotonishitekudasai ©2006-2010 kaoruko since2006/09/13