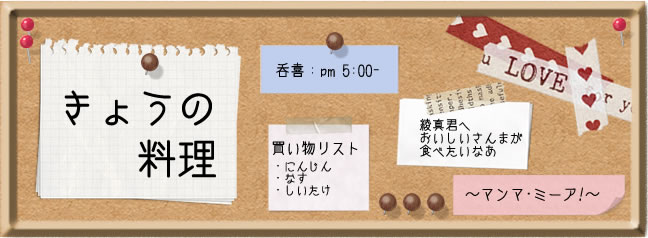
レシピ7:ほっこり粥で良薬口に苦くない!―過去編
「……誠史君、誠史君!」
給食後の雑踏とした廊下を誠史は小走りで急いでいた。午後からは学校を休んで東京に
仕事に向かうのだ。急がなければ新幹線に乗り遅れてしまう。学校の通用門には母の運転
する車が既に停まっていて、イライラしながら待っているはずだ。
誠史は他の児童を避け、玄関までたどり着いたところで名前を呼ばれた。振り返れば、同じ
クラスの女子が誠史を追いかけて走ってきたのだ。走ってきたのは友野という女子で、周り
の女子がきゃあきゃあ騒ぐのに対し、わりとフランクに話しかけてくる女子だった。
「ああ、友野。何?」
「これ、忘れ物。先生が渡してって」
手渡されたのはここ数日分のお知らせのプリントや宿題、誠史のためだけに作られた課題
などだった。
「ありがと」
「あと、これも」
課題を全て手渡した後、友野は誠史の課題の上に今日の給食についていたデザートを乗せた。
「え、いらない……」
「なんでよ」
「食べてる時間ないし」
「美味しいよ?クレープアイス食べたことあるでしょ?」
「別に、もっと旨いもの一杯食ってるし。そんなに欲しいなら、友野が食べろよ」
「なんであたしが食べなきゃなんないのよ。それ、誠史君が残したやつだよ?」
「知ってる。いらないから残したんだもん」
給食は大抵誠史の口に合わず、一口も手につけずに片付けることもしばしばだ。デザート
にだって他の同級生ほど執着はなく、じゃんけんして取り合ったことなど一度もない。
理由は簡単だ。自分はもっと旨いものを好きなだけ食べられるから。同級生を小馬鹿にした
態度に友野は腹を立てた。
「とにかく、それくらいは食べてよね」
母親にだって食べ物を強要されたことはない。苛立ちながら誠史は課題の上に乗せられた
クレープを友野に返そうとした。けれど、友野も頑なにそれを受け取ろうとせず、押し付け
合っているうちにクレープは床に落ち、不運なことに、クレープの上に誠史の足が乗って
しまった。
「あっ……」
「きゃあ!!」
誠史は潰れたクレープよりも真っ先に自分の足の裏を見た。上靴の裏にクレープは付いて
おらずほっとしたところでクレープを見下ろす。袋の口は破れてはいなかったが、クリーム
がクレープを破って外にはみ出していた。
「あーあ……」
「勿体無い」
友野の非難の目も気にすることなく、誠史は拾い上げると玄関のゴミ箱へと持っていこう
とした。
「それ、捨てるの?」
「当たり前だろ?」
「まだ食べられるよ!」
「こんなもん、食えるか!」
誠史のイライラが最高潮になると、友野は急にトーンを落とした。
「……誠史君ってかわいそうだよね」
「はあ?」
「誠史君って、小学生の楽しみとか幸せを知らないんだね」
「……何が言いたいの?」
「給食食べる前、クラスの男子がじゃんけんで休んだ子のクレープ取り合ってたの見て
ないの?」
「見てたよ。それで?」
「ああやってるのが楽しいんだよ。誠史君はそれが分からないんでしょ?だからかわいそう
って事」
説教は大嫌いだ。そんな事言われても誠史はうざいとしか思わなかった。
大体、友野の言っている意味もわからないし、時間も押していたので、適当にあしらって
誠史は逃げに走った。
「俺仕事あるし、もういい?」
その台詞に友野は更に機嫌を悪くした。
「それ、逃げてるの?言い訳?」
「はあ?!」
「誠史君って、何かあるとすぐ仕事だしって言うよね」
「だって本当だから」
「なのに、仕事仕事って言う割りに全然楽しそうじゃない」
「当たり前だろ。忙しいんだから、楽しいことばっかりじゃねえよ」
「仕事で忙しいってうちの親みたい。仕事ってそんな疲れて嫌そうな顔してまでしなきゃ
いけないことなの?」
「は?」
「誠史君ってさ、いつもつまらなそうな顔で学校早退してくよね」
「だから、楽しい仕事ばっかりじゃないんだって」
「だったら楽しい仕事だけ選べばいいじゃん」
「親が仕事取ってくるんだから、そんなの選べるわけないだろ」
「そういうもんなの?……誠史君って親の操り人形なんだ」
「なっ……!!」
瞬間、誠史は殴りたいほどの衝撃を受けた。相手が女子だろうと誰だろうと構わず殴って
しまいたいほど誠史は動揺したのだ。
「前も思ったんだけど、誠史君ってお母さんにやらされてるって感じ凄いするよ?」
「違っ……」
「うちら、もう小5だよ?そんな親の言いなりばっかりで楽しい?」
誰にも指摘されてこなかったけれど、自分の意識の中にひたすら隠してきた事実を、彼女
ははっきりと見破った。わなわなと震える拳がもう少しで上がりそうになった時、友野は
一歩後ろに引いて、頭を下げた。彼女の表情は自分を恐れているように見えた。
「怒ってる?……ごめん」
「……」
「急いでるんでしょ?車の中で食べるといいよ、それ」
友野は潰れかけて捨てようとしていたクレープを指して言った。誠史が握った所為で更に
クリームが外にはみ出て、いつもの誠史なら到底食べる気など起きるようなものではな
かった。友野はそれだけ言うと、走り去っていった。
誠史は思い出したように玄関で靴を履き替えると、母親の運転する車までダッシュした。
「遅い」
「しかたないじゃん」
「新幹線間に合わないかもしれない。飛ばすわよ」
母親の運転はとても乱暴だった。けれど、不安定な車内の中で誠史は手に持っていたクレープ
の包みをゆっくりと開いた。
べとべとな上に食べにくい環境で、誠史には旨いか不味いか判断がつかなかった。ただ、無性に
涙が零れそうになって、母親に見られないように必死に食べたのだった。
「些細なことだったんだよ。ただそれだけ。クラスメイトの女の子もそれ以降、そんな話
してこなかったし、重大な何かがあったわけじゃない」
だけど、その一件があってから誠史は自分の生き方を見詰め返すことになったのだと言った。
「親の操り人形って言われたのは流石にきつかったね。でも、本当の事だったから、反論
出来なかった。それで自分の意思はどうなんだって、やっと自分に向き合えた」
そして、誠史は1年後、ついに芸能界を辞める決意したのだった。
「母親は猛反対されたよ。やっと映画の主役貰って、子役から俳優の道へと進めるかも
って時にあっさり辞めるなんて言い出したからね。でも、俺は自分の意思を曲げる気には
なれなかったし、気持ちも全く役者の方を向いてなかったから。……そういえば、何時
までもネチネチ言ってくる母に切れて最後は家出したんだった」
誠史は懐かしそうにふふっと笑った。
自分にはない痛みだと綾真は思う。とても幸せな子ども時代を過ごして、家族の愛情を嫌
と言うほど注がれた自分は、誠史の語る子ども時代が別次元の話に聞こえるのだ。幸せな
時代の後に突然訪れた不幸を思うと、自分の人生もけして平坦ではないけれど、誠史の
無機質に聞こえる子ども時代は、暗闇の中で無数に受けた切り傷のように唐突で苦しい
痛みに感じた。
誠史の胸の中で綾真は縮こまって誠史の過去を受け入れる。綾真が自分の話に傷ついた
ことを誠史は悟った。
誠史は苦笑いしながら、また綾真の髪を優しく掬った。
「そうそう、ここからが本題ね」
誠史は声のトーンを明るくした。
「この前のテレビね、本当はもう何年も前から「あの人は今」に出ませんかって話が俺の
所に入って来てたんだよ。でも、事あるごとに俺が断ってたら、ついに母親の方に話が
行ってしまってね……。俺が芸能界ドロップアウトしたことで、一部には俺が大御所に
やっちゃいけない発言したからだとか、新しい子役のせいで干されたとか、ないことづくし
の噂が立ってさ。母親はそりゃあもう悔しくて仕方なかったんだよね。この恨み晴らさで
おくべきかってね、二つ返事でOKしちゃってて、俺がそれを知ったのは取材当日だった
って結構ありえない展開。だけど、そこまでして拒否するのも大人気なくて、数年分の
親孝行だと思って出たってわけ」
誠史と母親の間にある見えない溝がどれだけのものか自分にはわからない。けれど溝の底
には愛情が流れてるのだとも思った。
誠史は一通り語り終わると、綾真の頭に顔を埋めて、さり気なく綾真の匂いを嗅いでいた。
誠史の過去に呆然としていた綾真も、誠史の行為がエスカレートしていくと我に返って
声を上げた。
「あの!……そろそろ離してもらえませんか」
「えー。折角、抱き枕手に入れたのに」
「全然抱き心地よくないと思います」
ぴしゃりと言い切ると、誠史はあっさりと引き下がった。
「風邪うつしても悪いしね」
誠史は素直に綾真を解放すると、力なくベッドに沈んだ。綾真はすっかり誠史の体調が悪い
事を失念していて、誠史が腫れぼったい目を瞬かせると慌てた。
「大丈夫ですか!?」
綾真は手を伸ばし、誠史のおでこに掌を当てた。その姿があまりにも自然で、誠史はおかしく
なって笑った。いつか綾真のアパートでみた家族写真には幼い弟と妹が写っていたのを思い
出す。あの子達の看病になれているのだろうと誠史は思った。
「熱い」
「うん。多分ね」
「熱測ってください」
「熱なんて測っても意味がないでしょ。測ったところで熱が下がるわけでもないし」
「子どもみたいな……」
「本当の事でしょ。熱があるの知って、余計に気が滅入ったらどうするの」
「……こんなときまで屁理屈ですか!もう、病人は病人らしく熱を測って寝てください」
「ヤダね。綾真君が看病してくれるなら、測ってあげなくもないけど」
「はい?」
誠史は急に子どもっぽい表情を作って綾真を覗き込んだ。
「残ってくれたってことは、俺のお世話してってくれることでしょ?」
完全に否定出来ないところを突いてくるのはずるいと、綾真は恨みがましい気持ちで誠史を
見下ろす。病人に何かしてあげなくてはいけないと思う気持ちに他意はない。ただ病人だ
からだ。だから綾真は残ったし、今もこうしている……はずなのだ。
「と、とにかく、まず熱を測ってくれないと看病するにもしないにも対応できませんから!
体温計、どこですか」
「えー、どこだったかなあ……。リビングに薬箱があるからその中かも……」
「探してきます」
綾真は誠史から逃げるようにリビングに向かった。
――>>next
よろしければ、ご感想お聞かせ下さい
nakattakotonishitekudasai ©2006-2010 kaoruko since2006/09/13